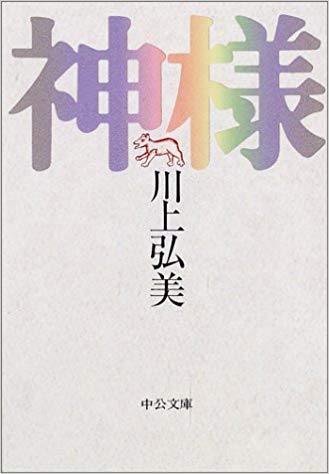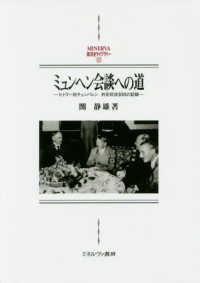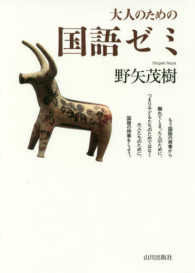文学部 1年生 匿名さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名:神様
著者:川上 弘美
出版社:中公文庫
出版年:2001年
小説の物語は常に現実が描かれている必要は無いと私は考える。私は現実の中に当たり前のように非現実的なものが混ざり合っている物語が好きだ。共に居合わせないものが共存する短編集、それがこの小説だ。
くまにさそわれて散歩に出る。この一文から始まる「神様」から、四季折々に現れる不思議な〈生き物〉たちとのふれあいと別れが9つの物語で描かれる。この小説は一冊を通して、全ての物語に共通することとして、[不思議な生き物・出来事との遭遇、それを当たり前に受け入れるわたし]がある。そして、それに伴う[切なさ・喪失感]がテーマとなっている。
著者のデビュー作でもある「神様」は、最近3つ隣に引っ越してきた【くま】と河原に散歩に行く様子が描かれる。【くま】にまるで当たり前のように人として接する【わたし】と、【くま】の熊としての一面がとても対象的に印象深く感じられる。梨の畑に現れる不思議な生き物との夏の思い出が描かれる「夏休み」は、まるで夏の終わりのような小さな喪失感が胸に広がる物語となっている。5年前に死んだ叔父がふと現れてはとりとめのない会話を続ける「花野」では、【思ってもいないことを言えば消えてしまう】という設定が最後の叔父のひとことに切なさを含ませていると考えられる。壺から現れた【コスミスミコ】とのクリスマスが描かれた「クリスマス」では痴情の縺れで壺に閉じ込められたコスミスミコと過ごす倦怠感をまとった一夜が描かれている。雪の降る日に迷い込んだ世界で不思議な男と恋をした【カナエさん】が語る「春立つ」では、春と冬で変わる季節感の描写にちなんだ不透明な恋愛が幸せと答えの一つを描き出している。そして最後の話となる「草上の昼食」では、「神様」に続き私とくまの日常の終わりが描かれる。人として馴染めきれなかったというくまが私に永遠の別れを切り出して去ってしまう中、わたしはまた次の約束を手紙で求めてしまう。心情の描写が現れる言葉と行動が切なく、小説中で一番の喪失感を感じる物語となっている。
様々な解釈のできる独特な世界感に溺れてみてはどうだろうか。