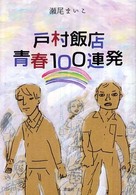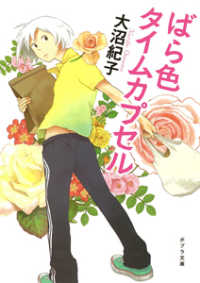書名: 旅をする木(星野道夫著作集3)
著者: 星野道夫
出版者: 新潮社 出版年: 2003年
場所: 1階開架一般 請求記号: 295.394/3/2001
「アジール」という言葉をご存知でしょうか?
ギリシア語で「害されない」「神聖不可侵」といった意味をもつ「asylos」から派生したドイツ語です。
歴史学でよく使われるのですが、近代以前の社会で、社寺や教会のように、社会的な暴力から避難できる聖域を指す言葉です。
法律が整備された現代では、こうした「アジール」は消えてしまいました。
ですが、誰しも一度は社会の圧力から逃げ出したい、と思ったことがあるのではないでしょうか?
現実に逃げ出すことはできなくても、本を使って自由な世界へ旅をすることはできます。
と、こう書くと、「本は全部そうでしょ」と突っ込まれるところですよね。
ですから、今回は、本当に現代における「アジール」へ旅ができる本、星野道夫著『旅をする木』をおすすめします。
星野道夫の肩書は写真家ですが、優れたエッセイストでもあります。
満点の星空、怖ろしいほど美しいオーロラ、沈まない太陽、此方から彼方へ移動するカリブーの大群。
圧倒的に広大な自然と共生し、古い生活を続ける人々と触れ合いながら生きる日々。
星野氏の純真な言葉は、現実に存在する異世界を実感させてくれます。
大勢の人が押しこめられた都会の日常から、遥か遠くへと旅をしたくなったら、頁を開いてみてください。
『旅をする木』は文春文庫から発売されていますが、図書館では文庫版は所蔵していません。
『星野道夫著作集3』に収録されていますので、そちらをご利用ください。