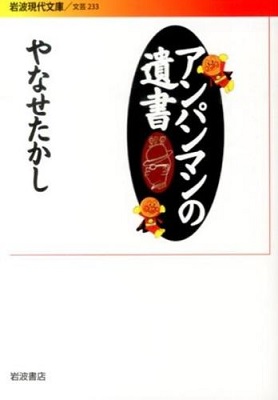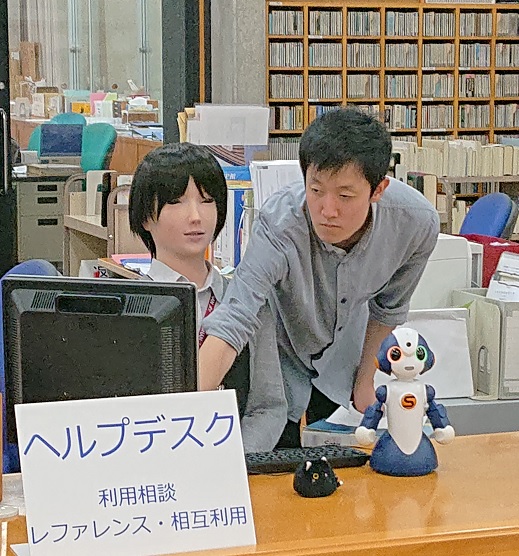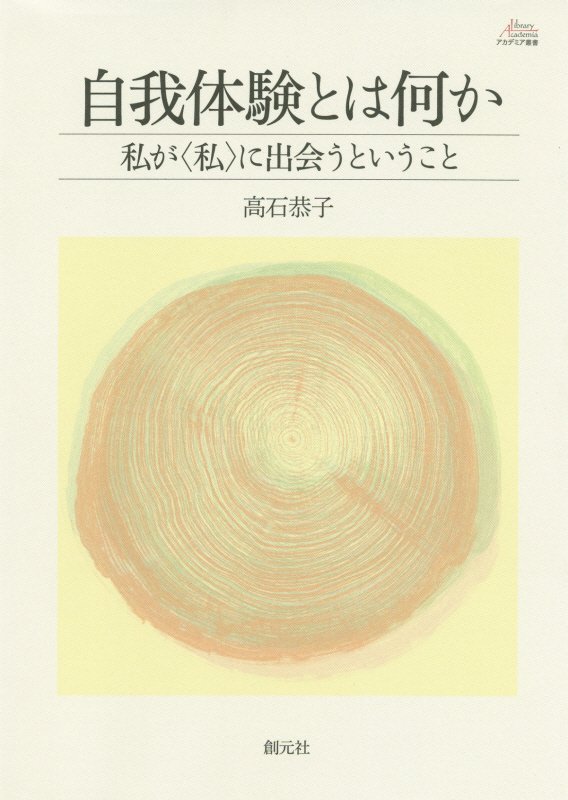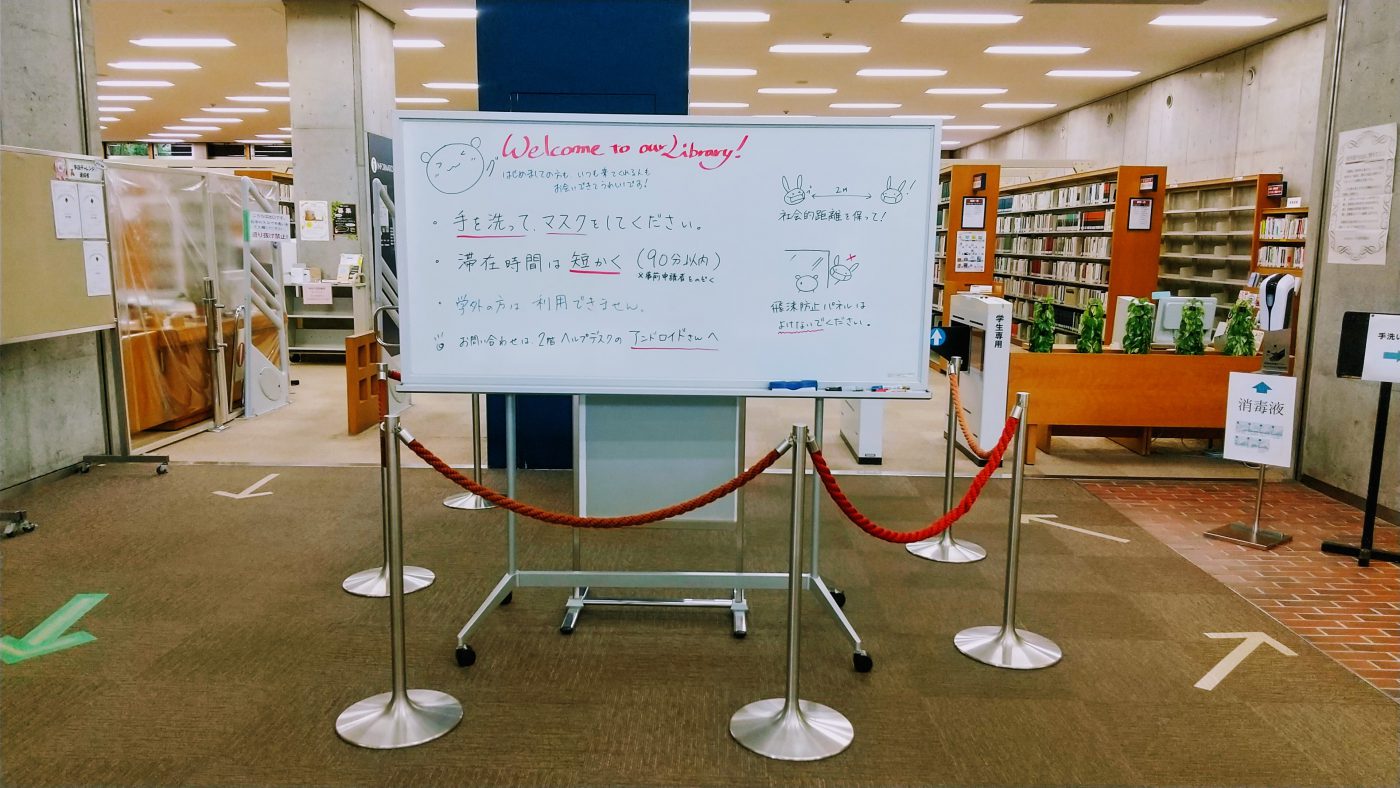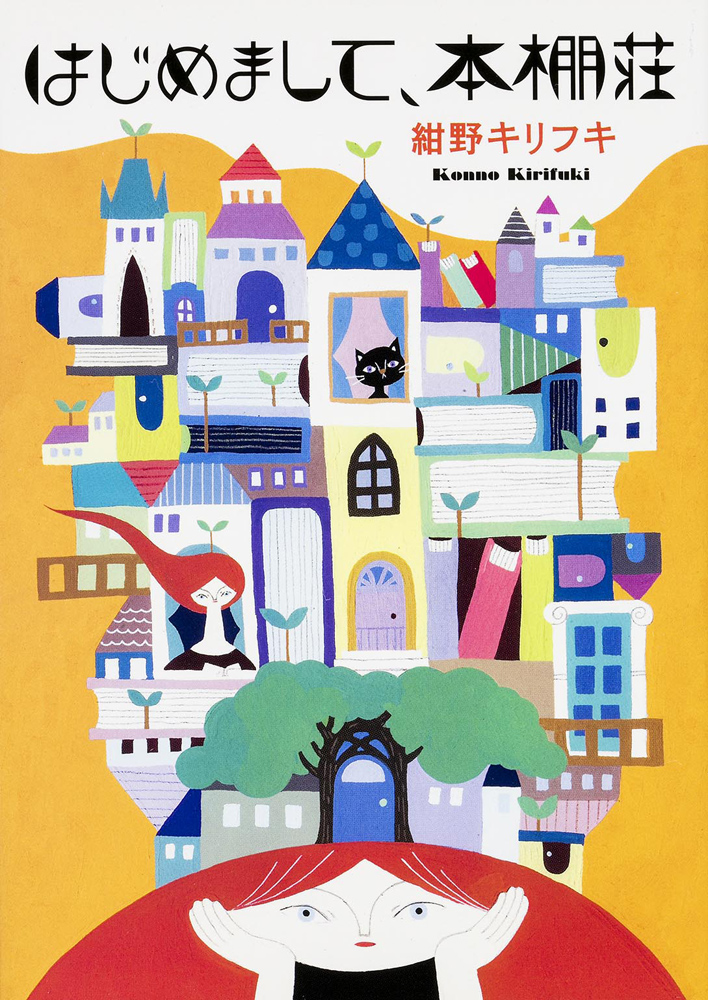図書館報『藤棚ONLINE』
文学部・友田義行先生 推薦
コロナ禍の下、「自粛警察」という言葉を耳にするようになりました。営業を続けるお店や、県外からの来訪者を探し出し、休業や自宅待機などを要請するそうです。報酬のない「ボランティア」活動であり、正義の心で動いておられるのかもしれません。
悪をくじき、弱きを助ける、正義の味方。ヒーローはいつの世もあこがれの存在です。アンパンマンが最初に出会ったヒーローだった方も多いのではないでしょうか。ウルトラマンや仮面ライダー、鉄腕アトムなどに比べると、アンパンマンはずいぶんとしょぼいヒーローです。困った人に自分の顔を食べさせたり、水に濡れてふやけてしまったり。すぐに顔を失い、力が出なくなって、悪者にぶっ飛ばされてしまいます。ジャムおじさんに新しい顔を焼いてもらわないと、ろくに活躍できないヒーロー。
本書はアンパンマンの作者・やなせたかしの自伝です。著者が76歳のときに遺書(?)として発行されました。ご紹介するのは手に入れやすい文庫版で、著者94歳の挨拶文が追記されています。
読んで意外だったのは、アンパンマンの話が終盤に少し登場するだけということ。著者は大人相手の漫画家を目指していましたが、手塚治虫ら輝かしい活躍を見せた同時代の漫画家たちとは違い、絵本作家として幼児の間で人気を得ました。むしろ日陰に生きてきたのだと、自らの半生を捉えています。顔のないアンパンマンは、無名性の象徴でもあるのです。たしかに、アンパンマンがアニメ化されたのは1988年で、著者はすでに70歳近くでした。この翌年、手塚治虫が亡くなっています。アンパンマンと鉄腕アトムはすれ違いました。
「なんのために生まれて なにをして生きるのか わからないままおわる そんなのはいやだ!」、「ぼくらはみんな生きている 生きているからかなしいんだ」、どちらもやなせたかしの作詞です。彼はアニメーターや絵本作家である前に、詩人でした。
アンパンマンの原型となった絵本『あんぱんまん』のあとがきに、著者はこう書いています。「ほんとうの正義というのは、けっしてかっこうのいいものではないし、そして、そのためにかならず自分も深く傷つくものです」。他人を傷付けるばかりの正義が横行する世界を、顔の欠けたアンパンマンはどう見つめているでしょうか。