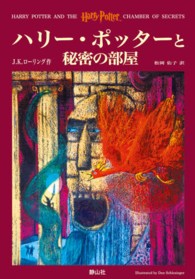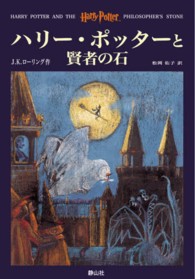文学部 3年生 中西聖也さんが文学部のT先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
・小さい頃に本は読まれていましたか?
幼稚園の頃は、母親によく読み聞かせてもらっていました。今思うと、宮沢賢治や新見南吉の童話など少し文学チックな本が多く、良い本を選んでもらっていたと感じます。小学生になってからは、偕成社の「少女名作シリーズ」を読み始め、次に「少年少女世界の名作シリーズ」に出会いました。オルコットやゲーテ、シェイクスピアなどが子供向けに面白く書かれていて、子供の文学の裾野がすごく広い、豊かな時代だったなと思います。
・大学で日本文学を勉強されたきっかけは何でしたか?
中学二年生の時に、樋口一葉に出会ったことがきっかけです。NHKの「一葉日記」というドラマを見て、一葉を読み始めました。女性が文章を書いて生きていこうとする姿に惹かれたのだと思います。その頃から、日本文学を学んでみたいなと思うようになりました。。
・近代文学に興味を持ったのはなぜですか?
日本の古来の江戸時代までの文化的な流れから、明治以降の文化は大きく転換していきます。その激動の時代のダイナミックさに惹かれて、感心が広がっていきました。そこから、文学を勉強しながらも、背景にある風俗や文化、政治、制度などいろんな面に目を向けていきたいなと思っていきました。一葉がその時代の大きな転換点に立っていたというのも外せないポイントですね。
・最後に、学生におすすめの本を教えてください
やはり大学の時間のある時に、一番重たい本を読んでおいてほしいと思いますので、ドストエフスキーの『罪と罰』を選びました。日本の近代文学は『罪と罰』にものすごく影響を受けています。ぜひ一度チャレンジしてほしいです。
あんまり長いものは嫌だと言う方には、山本文緒さんの『絶対泣かない』を選びました。15人の働く女性達の姿を描いている短編集です。職業・社会が垣間見える本として、学生に良いと思います。
・インタビューを終えて
たくさんの面白いお話を聞かせていただきました。この短い文章では、先生の本への想いや、魅力の全てを伝えきることなんて出来ません。それほどまでに深い本への愛情を、直に感じることが出来たので、インタビューをして本当に良かったと思いました。
<T先生おすすめの本>
① ドストエフスキー著 『罪と罰』 新潮社,1987年
※図書館注: 図書館には複数出版者の邦訳を所蔵していますが、光文社古典新訳文庫が一番新しいです。
②山本文緒『絶対泣かない』角川書店,1998年
(インタビュアー:文学部 3年 中西聖也)