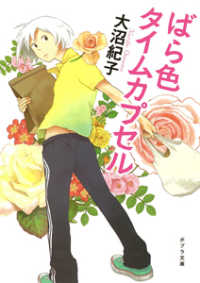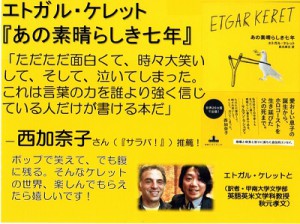文学部 3年生 匿名さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名:ばら色タイムカプセル
著者:大沼紀子
出版社:ポプラ社
出版年:2012年
この小説では、La vie en rose 「あなたたちの人生が、薔薇色であることを祈っています」という意味が込められた、女性専用有料老人ホームが舞台となっています。父と、その再婚相手のことを思って、家出を決行したが、何もかもに疲れて崖へと駆け出してしまった、主人公の森山奏(13才)は、先述した老人ホームの入居者達に助けられ、自分の年齢を20才と偽り、食事と住居完備の条件で雇われ、入居者達と深く関わっていき、自分が忘れていた大事なことを思い出したり、「生きること」「死ぬこと」について教わったりしながら、自分の人生を見つめ直していくというストーリーです。
この作品に登場する、入居者達は、皆すごく魅力的です。バラの手入れに力を注ぐ遥さん、クラブ登紀子を営業する登紀子さん、明るくかしましくプロの乙女の友情を育む仲良し3人組の佐和子さん・千恵さん・万里さん、健康を気にせず、自分が食べたいものを作って食べる長子さん。彼女達は、自分に正直で、自由気ままに伸び伸びと過ごしている点は共通しているけれど、それぞれ個性的で愛すべきところや面白みがあるように描かれていると感じられました。そして、主人公の奏が、彼女たちの行動や姿から感じ取ったことや、彼女達が奏にかけた言葉を、読者が、自分の中で反芻し、「生きること」「死ぬこと」について考えを巡らせるように自然と促されてしまう点も、この作品の魅力の1つだと感じました。また、気を張って、物わかりのよい子であろうと背伸びしていた奏が、入居者達や等身大の中学生の山崎和臣との関わりを通して、少しずつ変わっていく様子も、読み応えがあります。
この物語を通して、あなたの人生が薔薇色であるためのヒントを見つけてみませんか。