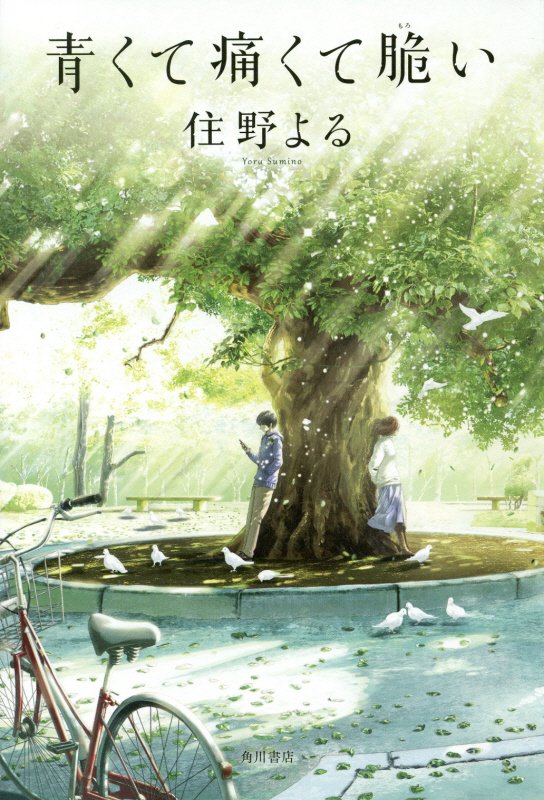知能情報学部 4年生 Sさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : ソードアート・オンライン7 マザーズ・ロザリオ
著者 : 川原礫
出版社:KADOKAWA
出版年:2016年
本作は、ライトノベル作品のソードアートオンライン第7巻にあたるものですが、キリトとアスナという二人が過去にソードアートオンライン(以降SAO)という現実とゲームの死がリンクしているゲームの世界を無事クリアした後のお話ということさえ理解していれば読める内容となっています。
キリトとアスナはSAOクリア後に、SAOのシステムを用いてサービスしているアルヴヘイムオンライン(以降ALO)というゲームを楽しんでいました。そこで、「絶剣」と呼ばれる剣技において最強と呼ばれるプレイヤーの噂を耳にします。絶剣は何故か自分を楽しませてくれるような強いプレイヤーを求めていました。キリトとアスナは噂を聞いて現地に行き、絶剣と試合を行います。そしてアスナが絶剣に気に入られ仲間に入ってほしいとお願いされます。絶剣は可愛らしい少女のアバターをしており名前はユウキといいます。そしてユウキとパーティーを組みとある理由でボスの討伐に仲間だけで挑みたいと言いました。そこから、ユウキとアスナは仲を深めていき、ユウキの悲しき深層を知ることとなります。本作は、謎に包まれた省三ユウキとアスナの短い旅路のお話となります。
私は本作を読んで、ユウキの悲しい深層とアスナとのやり取りに心を打たれました。是非読んで頂きたい作品のため内容の多くは語りませんが、ALOはフルダイブVRというゲームの世界にそのまま入り込むことができる最先端のゲームです。この設定を上手く利用した物語であり、ユウキや仲間のボス討伐への執念などが上手く描写されています。
本作は、ソードアートオンラインの続編ということもあり、今までの章節全てを読んでいないと理解に苦しむ内容と想像できますが、前提をほんの少し知っているだけで読み進めることができる作品です。ソードアートオンラインという作品自体が短いスパンでお話が進む小説となっているため、ソードアートオンラインという作品に興味がある方にはぜひとも読んでもらいたい作品です。もちろん前作を読んでいた方がより理解が速く細かい感情の描写に気付くことができる作品でもあります。
本作は、ライトノベル作品に興味がある、ゲームの世界に興味があるといった方々には非常におすすめの作品であり、ソードアートオンラインという作品を読み進めていくキッカケになってくれる作品です。