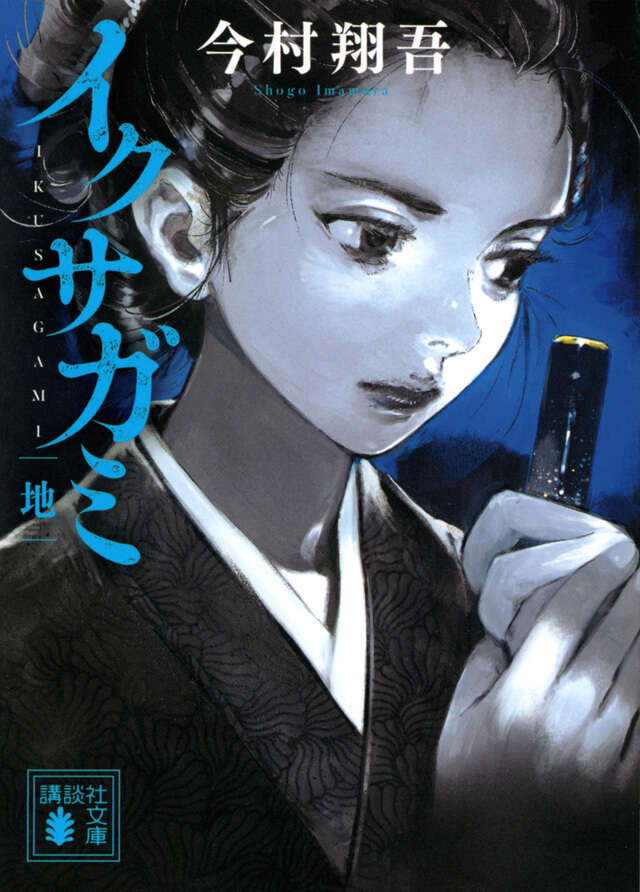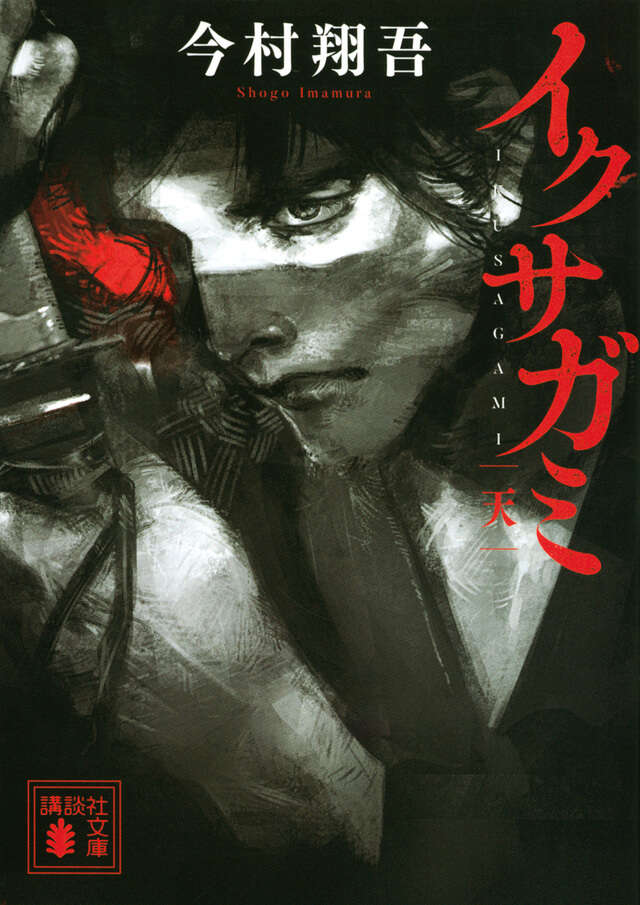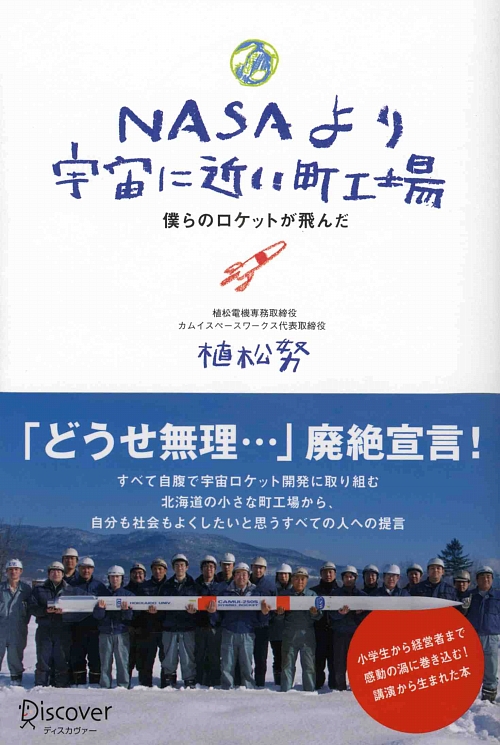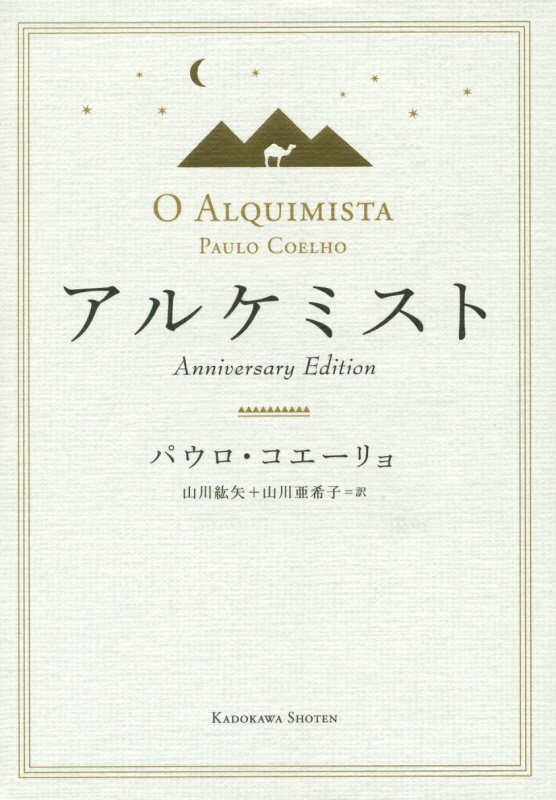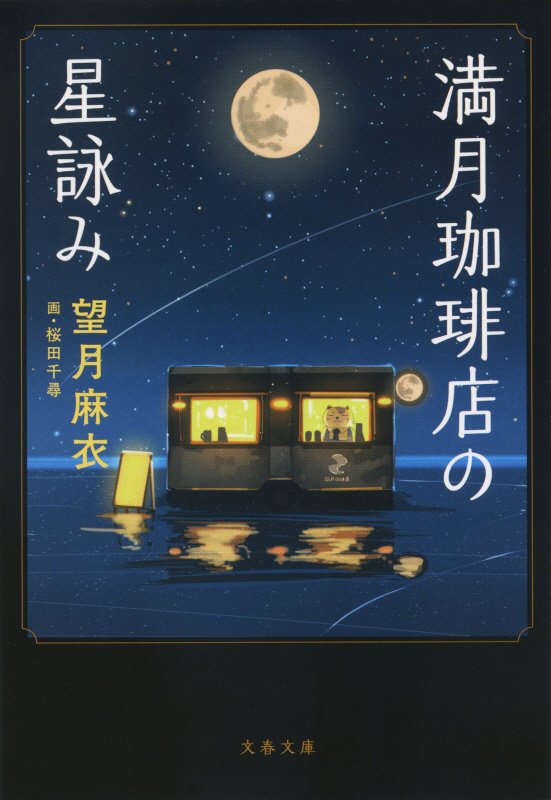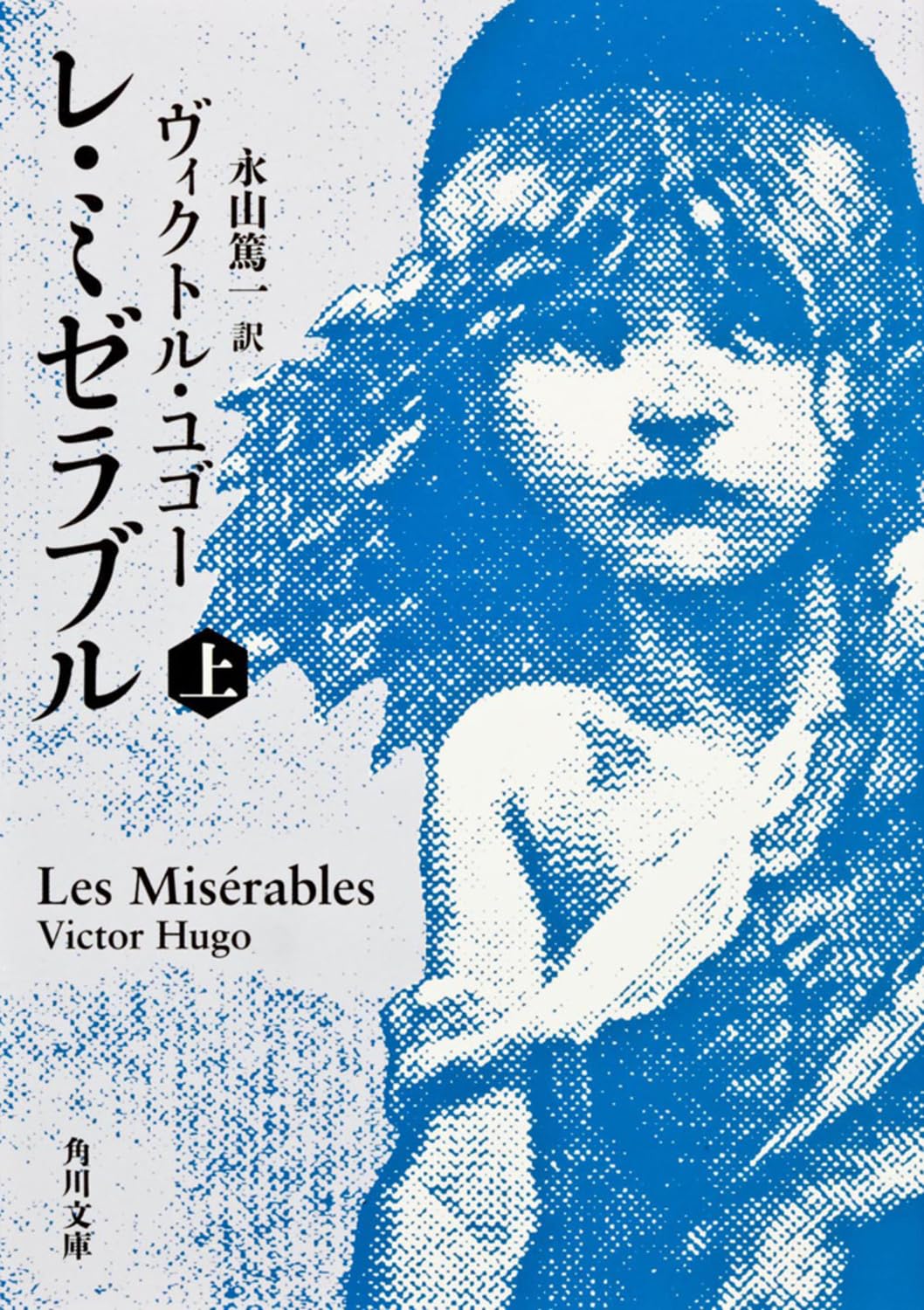
文学部 1年生 Oさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : レ・ミゼラブル
著者 : ヴィクトル・ユゴー [著] ; 永山篤一訳
出版社:角川書店
出版年:2012年
『レ・ミゼラブル』は19世紀前半のフランスを舞台とした歴史小説である。日本では過去に「あゝ無情」というタイトルで翻訳されており、そのタイトルならば聞いたことがあるという人もいるかもしれない。今回はそんな『レ・ミゼラブル』について、少しでも知ってもらうことが出来れば幸いである。
この物語は窃盗の罪を犯したジャン・ヴァルジャンが数十年間の服役を経て、出所するところから始まる。どこにも受け入れてもらえる場所は存在せず、各地を放浪する彼はディーニュにあるビアンヴニュ司教の屋敷を訪れる。司教はそんなヴァルジャンを心優しく受け入れて、一晩泊めることを快諾する。しかし長年の投獄からすっかり心が荒れていたヴァルジャンは、司教が大切にしていた銀の食器を盗み出してしまう。翌日、ヴァルジャンを連れてきた警官たちに対して、司教は「それは元々彼にあげる予定のものだった」と彼を釈放するように求める。さらに、釈放されたヴァルジャンに対して司教は残りの銀の食器、燭台を手渡し、彼にこれからは正直者であるように諭す。ヴァルジャンはそんな司教の振る舞いに感動し、心を入れ替えて生きていくことを誓うのである。
物語中には物事や社会の本質を突く言葉が数多く存在する。例えば窃盗の罪で捕まった当初、ヴァルジャンは「俺がこういった罪を犯したのは貧しさのためであり、そういった状況を許している無慈悲な人間社会に人を裁く権利はあるのか」と考える場面がある。ヴァルジャンは幼い頃に両親を亡くし、7人の子供を持つ姉の一家のもとで育った。しかし姉の夫が亡くなってからは、状況が変わってしまったため、このような盗みを犯したのだ。そこから私は、こういった過去を持つ彼を一概に悪とは言えるのだろうかと考えた。
本書には感動する場面も、また存在する。先ほど述べたヴァルジャンが改心するきっかけになった出来事もそうだ。巧みな表現で描かれた文が更にそういった感覚を助長させる。無情な社会の中でも、自分が正しいと思うことを貫くヴァルジャンの姿は、見ていてとても考えさせられる。いったい彼はどのような生涯を送るのか、実際に読んでみて、様々なことを感じて欲しい作品だ。