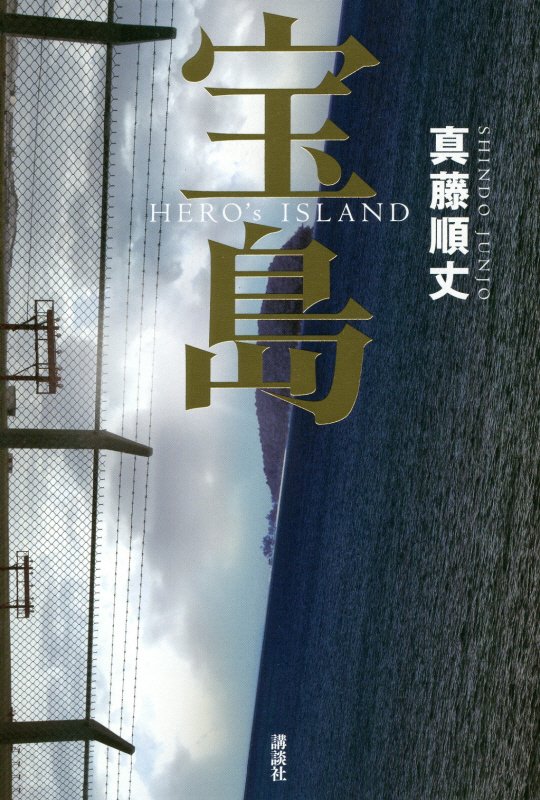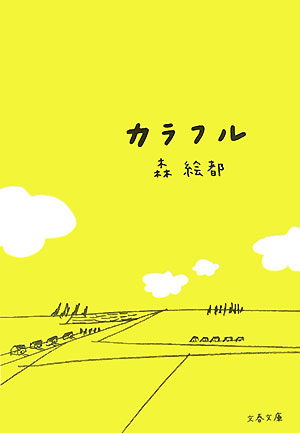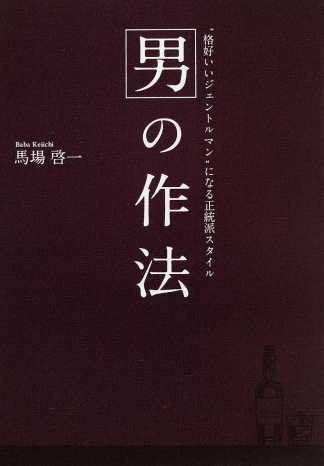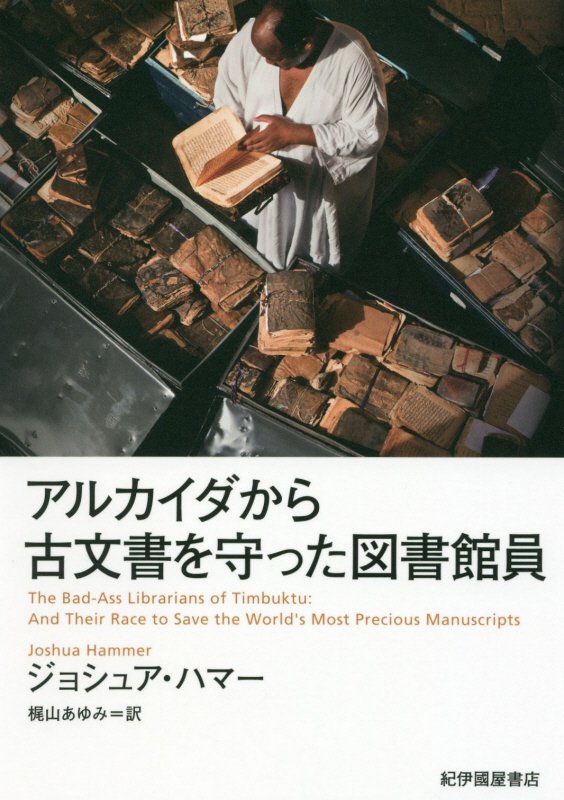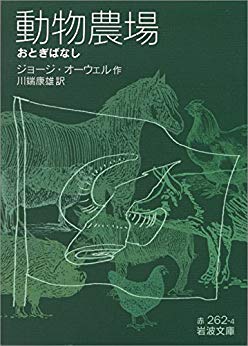文学部 4年生 Nさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
青春は誰にでも訪れるものである。だが、過ぎてしまった青春は二度と取り返すことができない。しかし、小説を読むことで思い出すことができることもある。そこで、これから大学生活が始まるという人にも、もうすぐ社会人になるという人にも、当に青春が過ぎてしまった人にも味わってほしい青春小説として『宝島』をあげたい。
舞台は、アメリカ施政下の沖縄。「英雄」と呼ばれていたオンちゃん、その弟のレイ、親友のグスク、恋人のヤマコ。彼らは米軍基地から物資をかっさらう「戦果アギヤー」と呼ばれる少年少女である。彼らは、オンちゃんを中心に固い絆で結ばれていた。だが、嘉手納空軍基地への侵入に失敗。オンちゃんは行方不明となり、その代わりに基地からは「予定外の戦果」が持ち出された。時は流れ、大人になった3人はそれぞれの道を歩み始める。琉球警察に勤めながら米軍情報部と繋がりを持ったグスク。本格的なアウトローとなったレイ。教師となり沖縄返還活動に励むヤマコ。だが、彼らはいつまでもオンちゃんの面影を忘れることができずにいた。基地から持ち出された「予定外の戦果」とは一体何なのか?また、消えたオンちゃんの行方は?奪われた沖縄を取り戻すため、少年少女は立ち上がる――。
本著は、直木賞、山田風太郎賞を2冠達成し、まさに骨太な傑作と言えるのだが、オススメする理由はそれだけではない。1つは、独特な語り口で沖縄が今現在も抱える社会問題を軽快なテイストで描きあげる作者の表現力の高さ。2つは、「予定外の戦果とは何か」「オンちゃんの行方はどうなったのか」というミステリー的要素も踏まえてあり、読者を飽きさせないこと。3つは、困難や人との付き合いに悩み苦しみながらもひたすらに前を向き続けるグスク、レイ、ヤマコの3人から青春小説の面白さを堪能できる。これらの理由から、本書をぜひ一読して頂きたい。