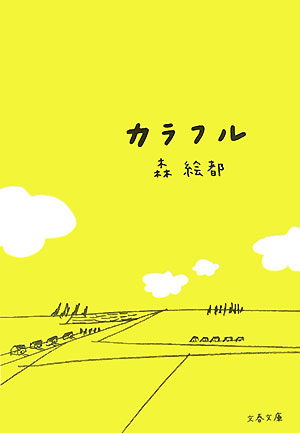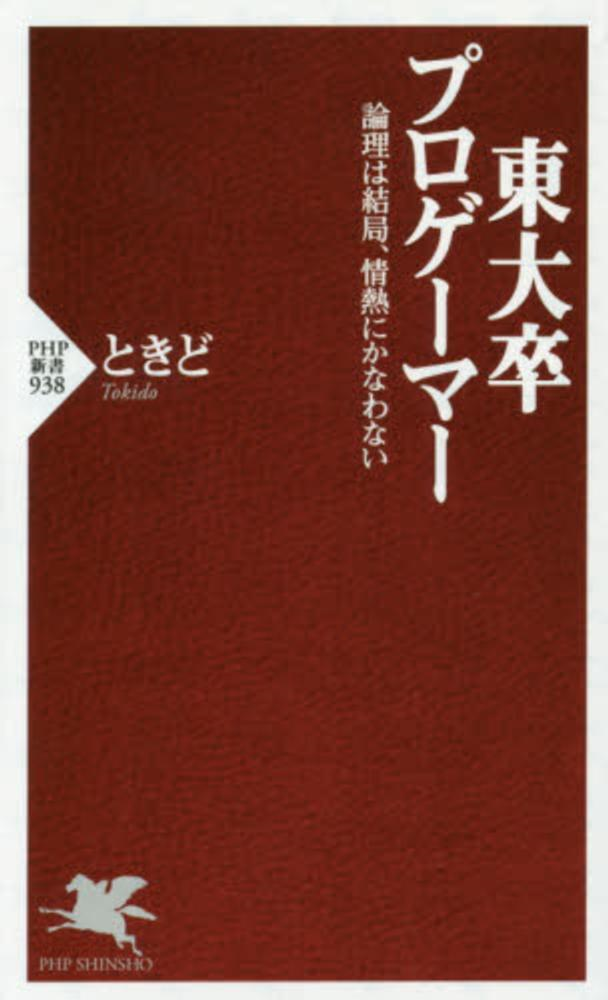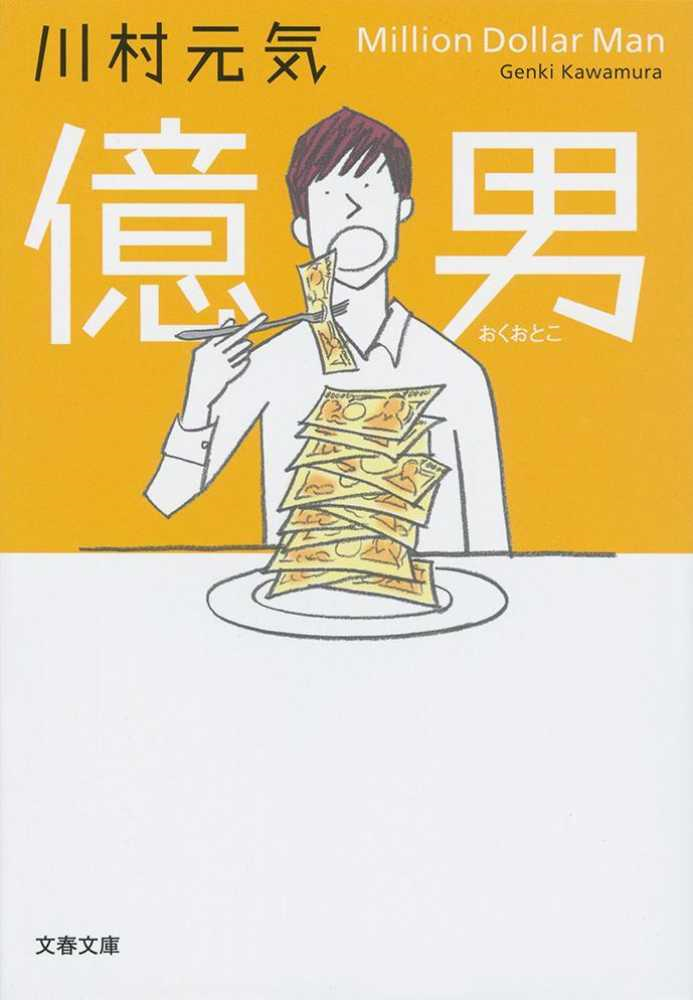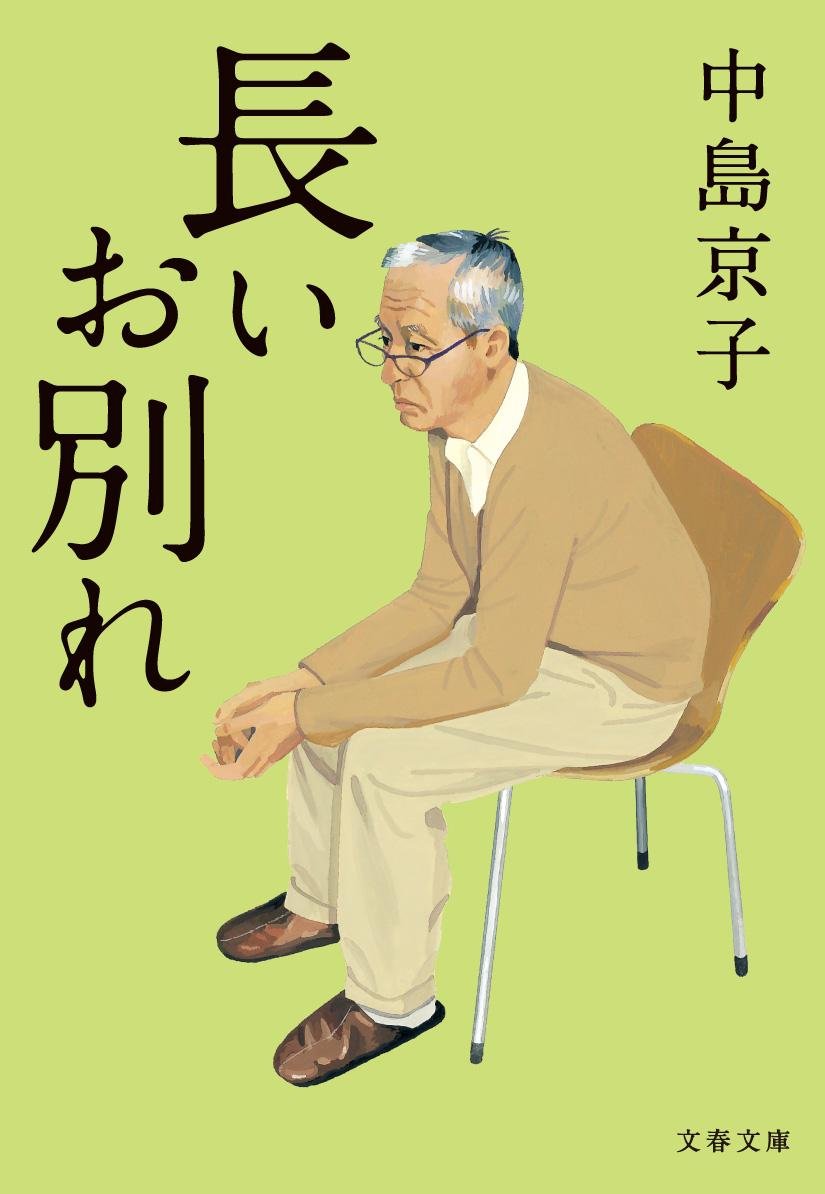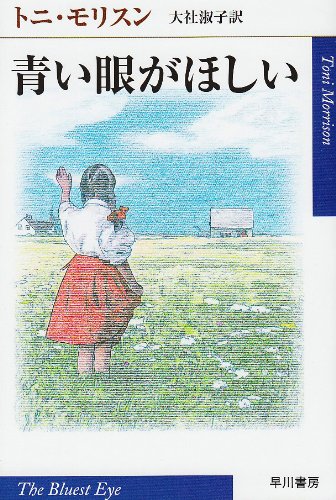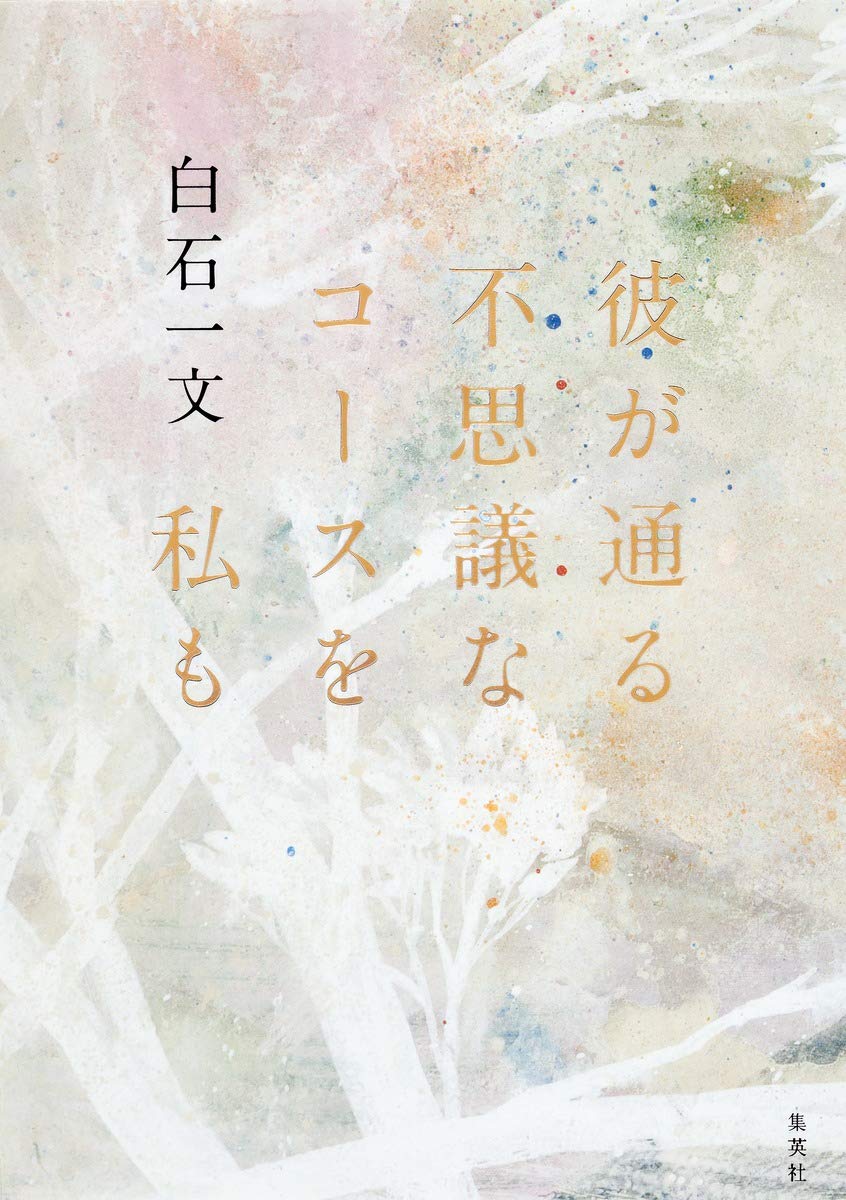文学部 3年生 Tさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : カラフル
著者 : 森 絵都
出版社:文藝春秋
出版年:2007年
本学で所蔵している本はこちら⇨ 森 絵都著 『カラフル』講談社 , 2011年
自分で初めて買った小説を思い出せるだろうか。私にとって「カラフル」はそんな一冊である。
死んだはずの自分の魂が抽選に当選したことにより、本来なら生まれ変われるものの生前の過ちのせいで輪廻のサイクルから外れた「ぼく」が、自殺を図った中学生である小林真の体を借りることで、天使と共に、生前に自分が犯した過ちを探るという物語である。
まるで児童文学のようなファンタジーである物語には、リアルな社会問題を抱えた登場人物たちが描かれている。ユーモアある在り得ない設定により、それが優しく描かれているため、そのバランスこそが幅広い年代の人々に親しまれ続けている理由ではないだろうか。
主人公である「ぼく」には記憶が無く、そんな状態で突然知らない環境の中へ放り込まれるわけだから、その手探りで人間関係を図りながら宿主である小林真という人物像を探そうとする姿は、楽しみながら気軽に読み進めることができる。あまりにもどうしようもない人間であった小林真を変えるために奮闘する姿も、その初々しい努力にはどこか惹きつけられるような魅力を感じるだろう。そんな中、立て続けに辛い出来事が「ぼく」を襲う。そして、10代という多感な時期に生きる登場人物たちは、その不安定な気持ちを吐露し合っていくのである。そこからは、薄暗くもどこか共感できるような感情が描かれており、言葉の一つ一つが鮮明かつ印象的に心に残るのではないだろうか。
そして、「ぼく」は本来の目的である生前の過ちを思い出すのである。
読了後余韻として残るのは、「カラフル」というタイトルの意味と、数々の名言である。
当たり前に生きる日常が、少し違った見え方をするようになるかもしれない。
まだ読んだことのない方にはぜひ一度手に取って頂きたい名作である。