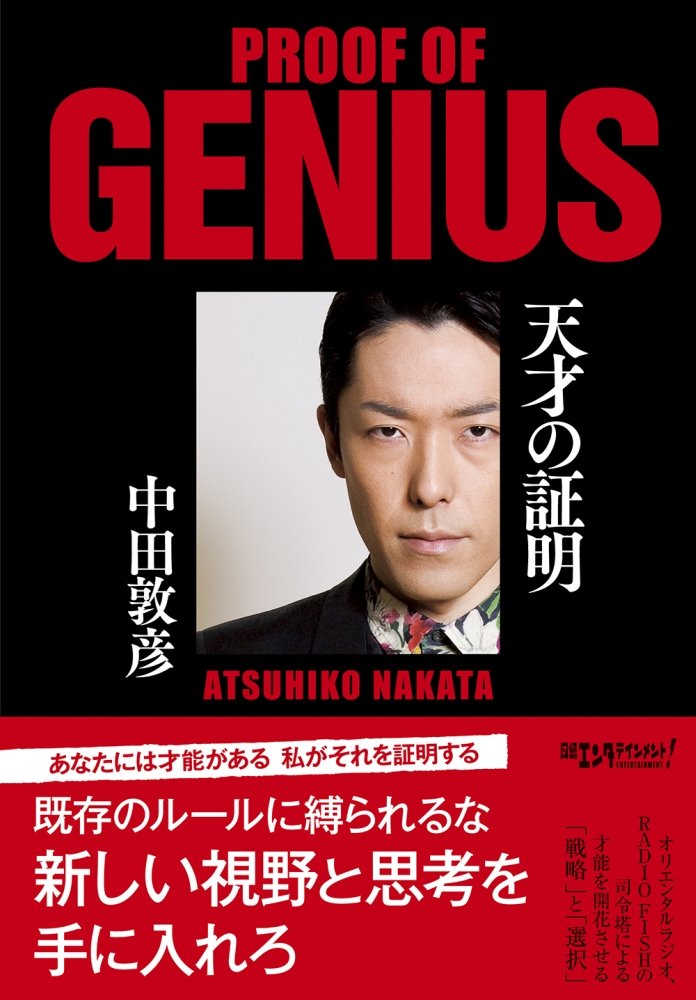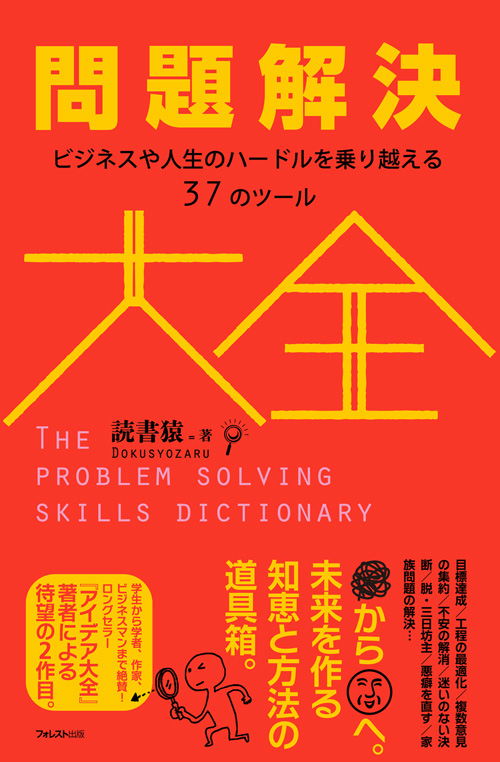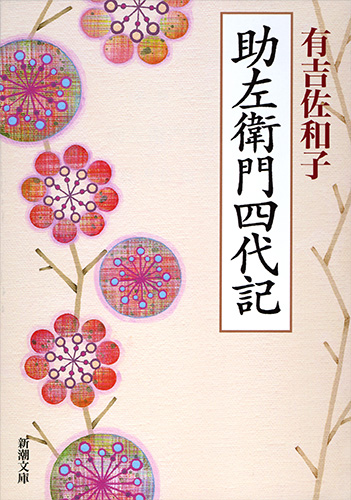文学部 2年生 匿名希望さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名: 夏の海の色
著者: 辻 邦生
出版社:中央公論社
出版年:1977年
あなたにとって、思い浮かぶような夏の思い出は何だろうか。夏はきっと思い出くらいがちょうどよいと思う。私にとってこの作品を手に取るきっかけとなったのは、高校三年生の頃に解いた国語の問題で、本文として表題である短編の「夏の海の色」を読み、惹かれたからである。
それくらい、美しい文章だった。改めて読み返してもそう思えるように、この中には夏の憧憬が広がっている。この本は辻邦生による「ある生涯の七つの場所」という連作短編集の二作目に当たり、フランス人女性と私の緩やかな愛の生活と、少年や青年とその周りに描かれる魅力的な人々との関係や恋愛についての合計14の物語が交互に描かれている。これは、一作目である「霧の聖マリ」から引き続き「黄いろい場所からの挿話」と「赤い場所からの挿話」が交互に語られている。これは、七冊からなる物語が平行に描かれているためであるが、この作品だけでも読み味わうことができるようになっている。
古い城下町である。城跡、石垣、夏の昼下がり、濃く影を落とす公園に、木陰で昼寝をする行商人。表題作で描かれるのは、そんな景色が広がる夏の物語だ。第三希望の中学校に進学が決まった少年は、叔母の妹である咲耶の紹介で、彼女の住む街で過ごす夏の日々の中、地元の中学校の剣道部の練習に参加することになる。海辺の街で行われる合宿に参加することになった際、咲耶は「私」に、絶対に海で泳がないようにと約束させるのであった。わけも説明しない彼女との約束を合宿が終わるまで守り続けた「私」は、二人で船に乗り沖合の赤いブイの近くにたどり着いたとき、その悲しい理由を知ることになる。
咲耶に抱く少年の淡い恋心と、彼女の抱える秘密が、美しい城下町の描写と夏の匂いに溶け込んで、少年の一夏の思い出と心の成長が淡くシリアスに紡がれている。
この本の中では、このような夏の物語が他にも収録されている。自分の中にある夏の思い出を思い返すように、少し感傷的な心で読み進めて欲しい。もうすぐ秋になる、そんな夏の終わりや初秋に浸って欲しい。あなたの夏の海の色に向けて。