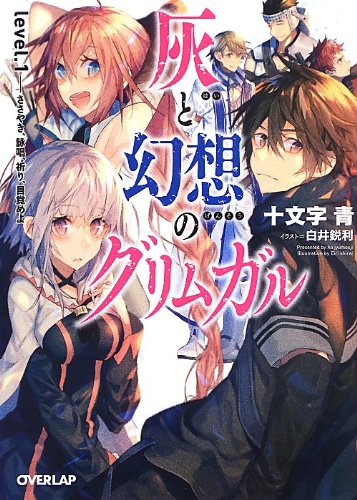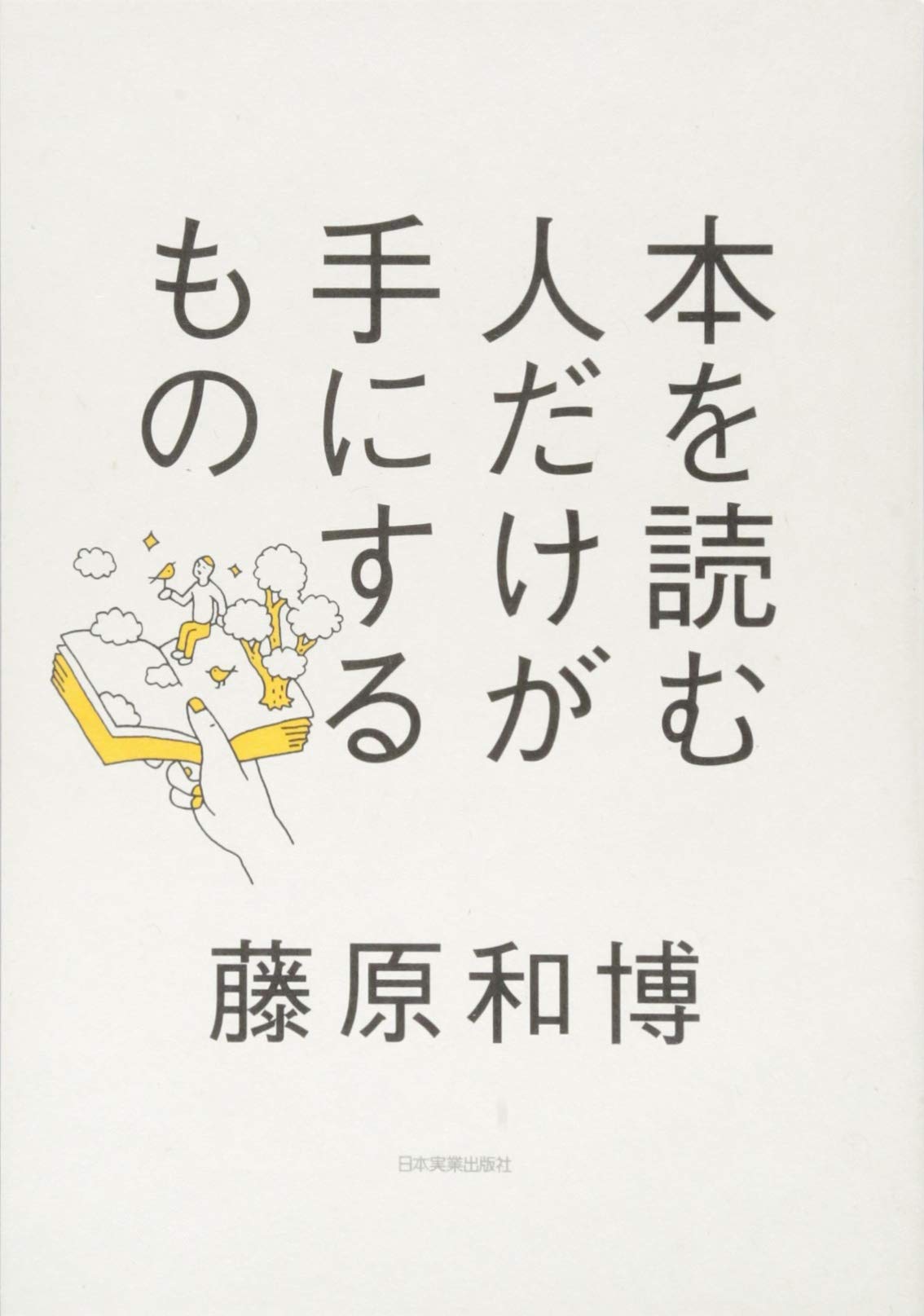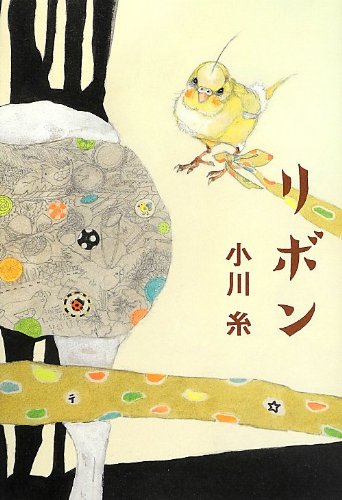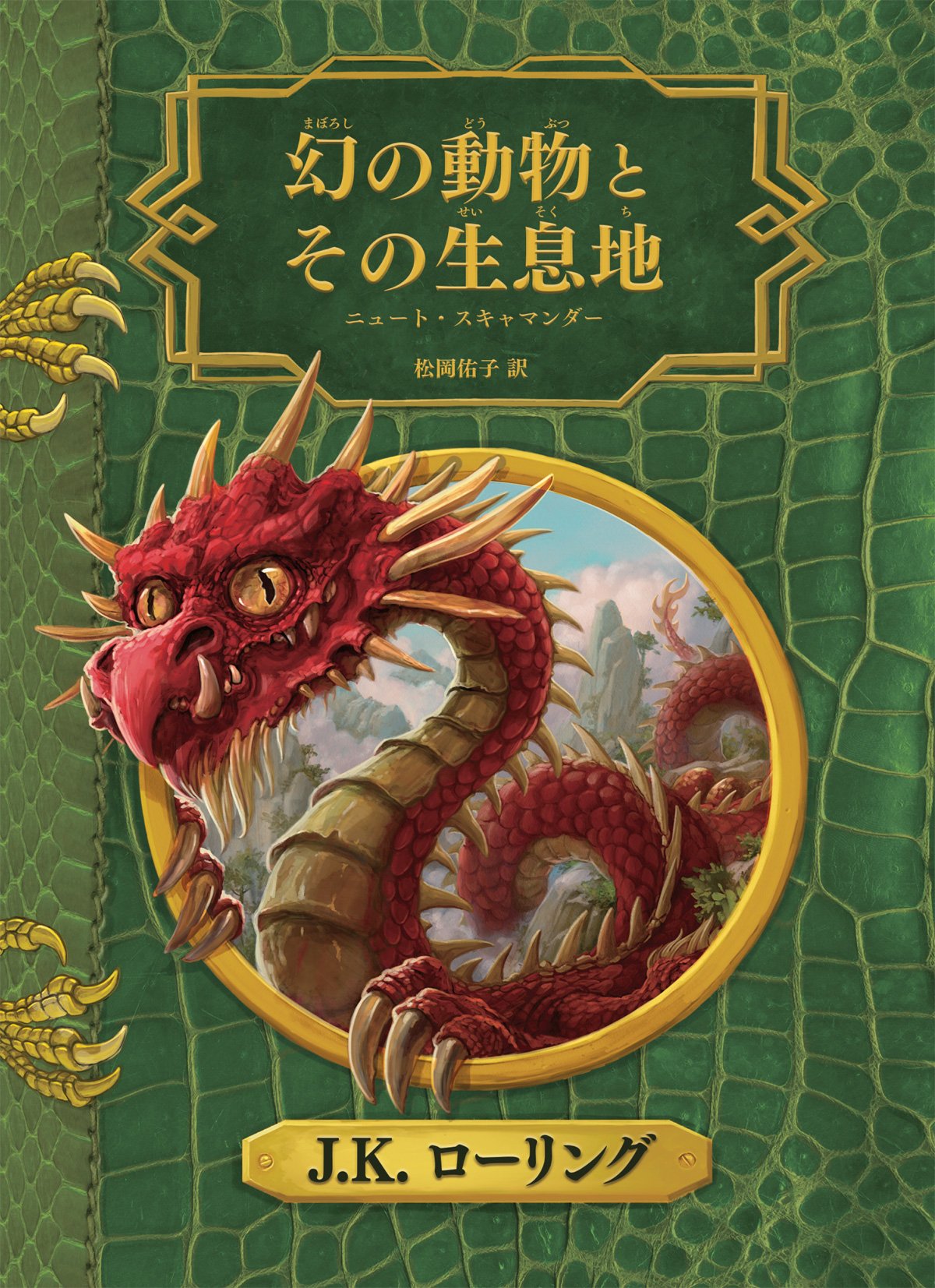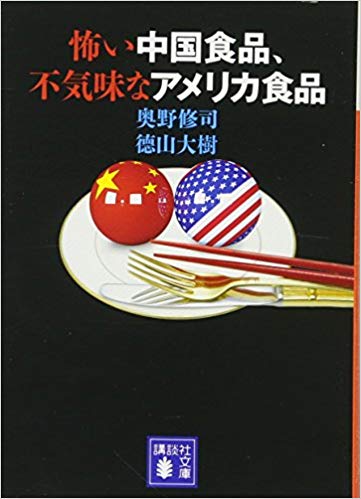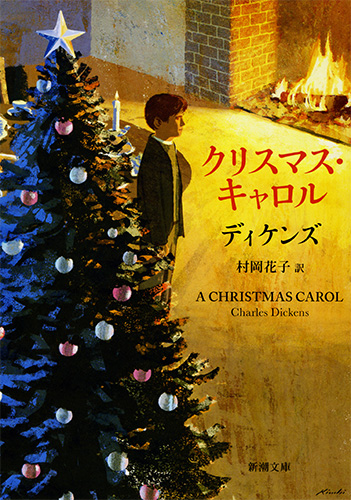 文学部 3年生 匿名希望さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
文学部 3年生 匿名希望さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名: クリスマス・キャロル
著者: チャールズ・ディケンズ 村岡花子訳
出版社:新潮社
出版年:2011年
皆さん、『クリスマス・キャロル』を読んだことがありますか?おそらく、読んだことのある方は少ないのではないかと思います。しかし、読んでいないという方、特に文学部の方は危機感をもってほしいと思います。なぜなら、この本は人生の中で読んでいて当然といえる程、子供の頃持っていた大切な思いが込められている本だからです。
物語は、ケチで意地悪なスクイージ老人が、クリスマスの夜に亡き仕事仲間・マーレイの幽霊と対面するところから始まります。マーレイの亡霊は、翌日から第一・第二・第三の幽霊がおまえの前に現れる、と話し姿を消します。すると、その言葉通りに幽霊が次々にスクイージの前にやってきます。そして、幽霊たちがスクイージに見せたものは、過去・現在・未来における彼の悲しい過去、見たくない現実、そして希望のない未来と現実でした。それらを見た後、スクイージはどう行動するのか?注目してもらいたいと思います。
この書評を読んでくださっている方の多くは、学生の方が多いのではないかと思います。学生というのはもうじき社会人となって立派に自立していく時であります。それはつまり、子どもの頃の心と記憶を忘れ、大人になっていくということでもあります。そんな時だからこそ、『クリスマス・キャロル』を読んでほしいと思います。もう、今の時点ですでに本作を読んで感動することやワクワクすることは難しいでしょう。しかし、今読んでおくことで幼かったころの自分、そしてクリスマスが近づくにつれワクワクしていたころの自分を思い出せるはずです。そのため、ぜひ一度、本作を読んでみてくれればと思います。きっと子供の頃の思い出に浸れるはずです。