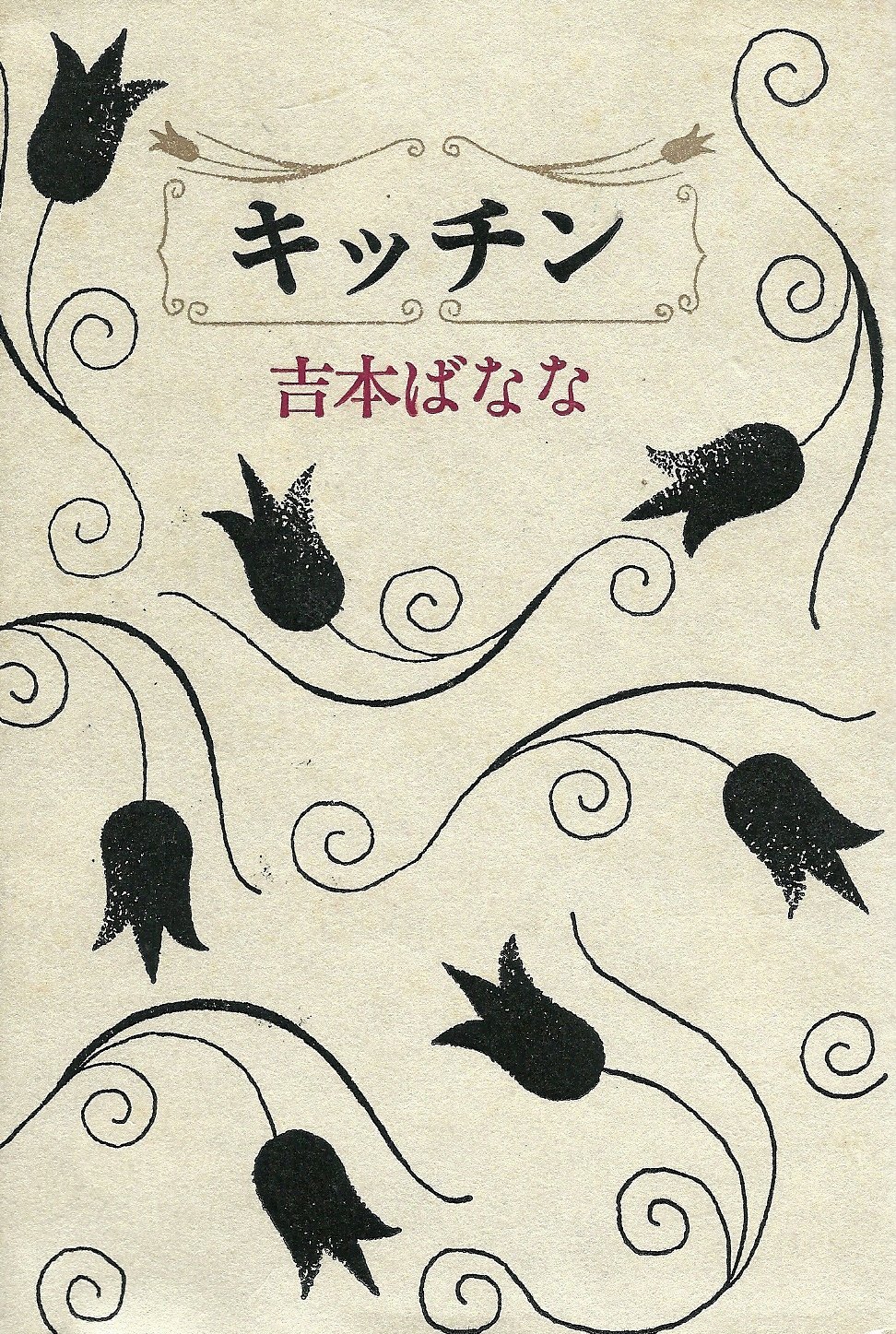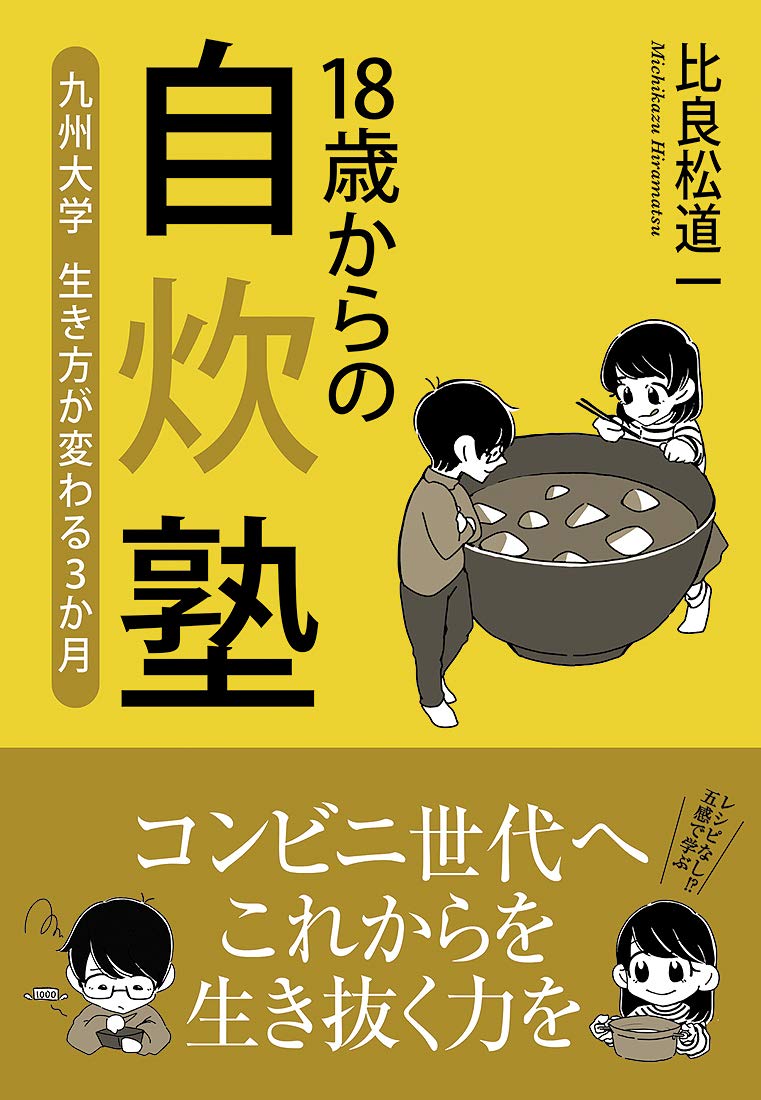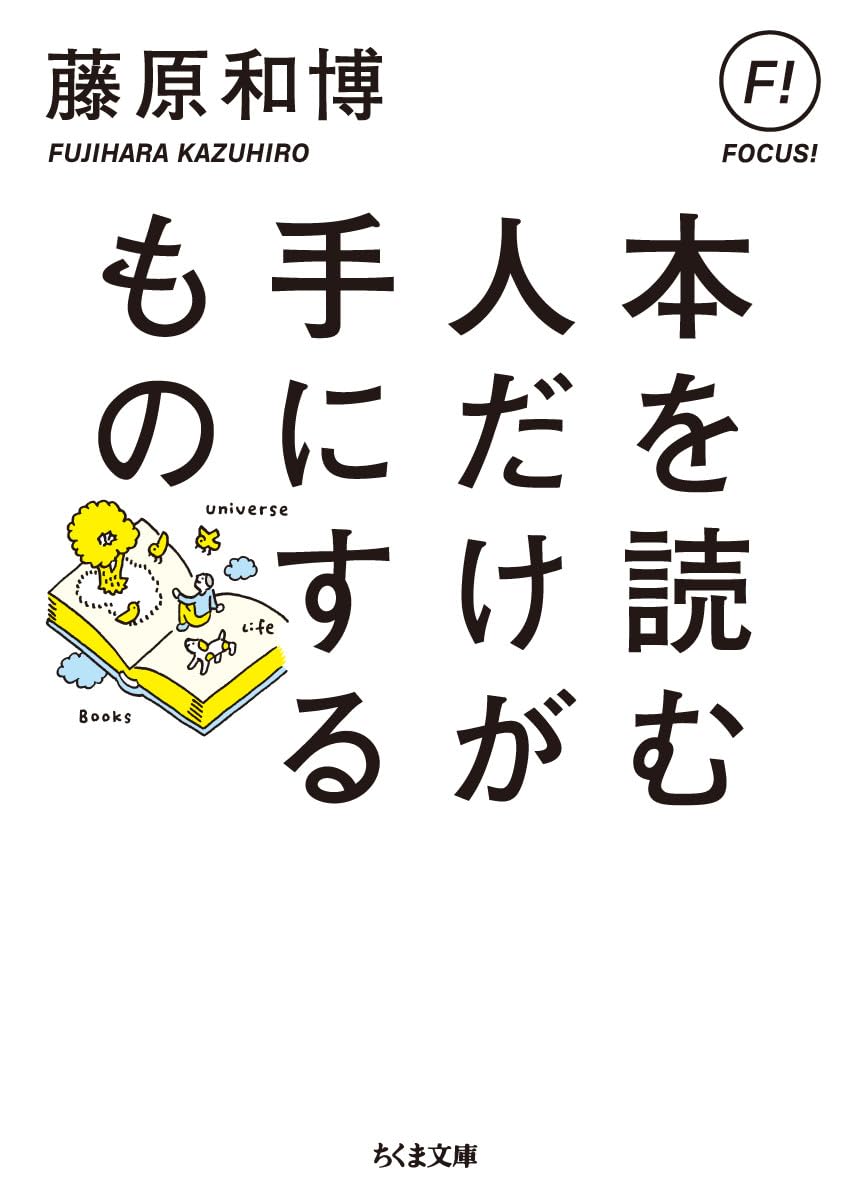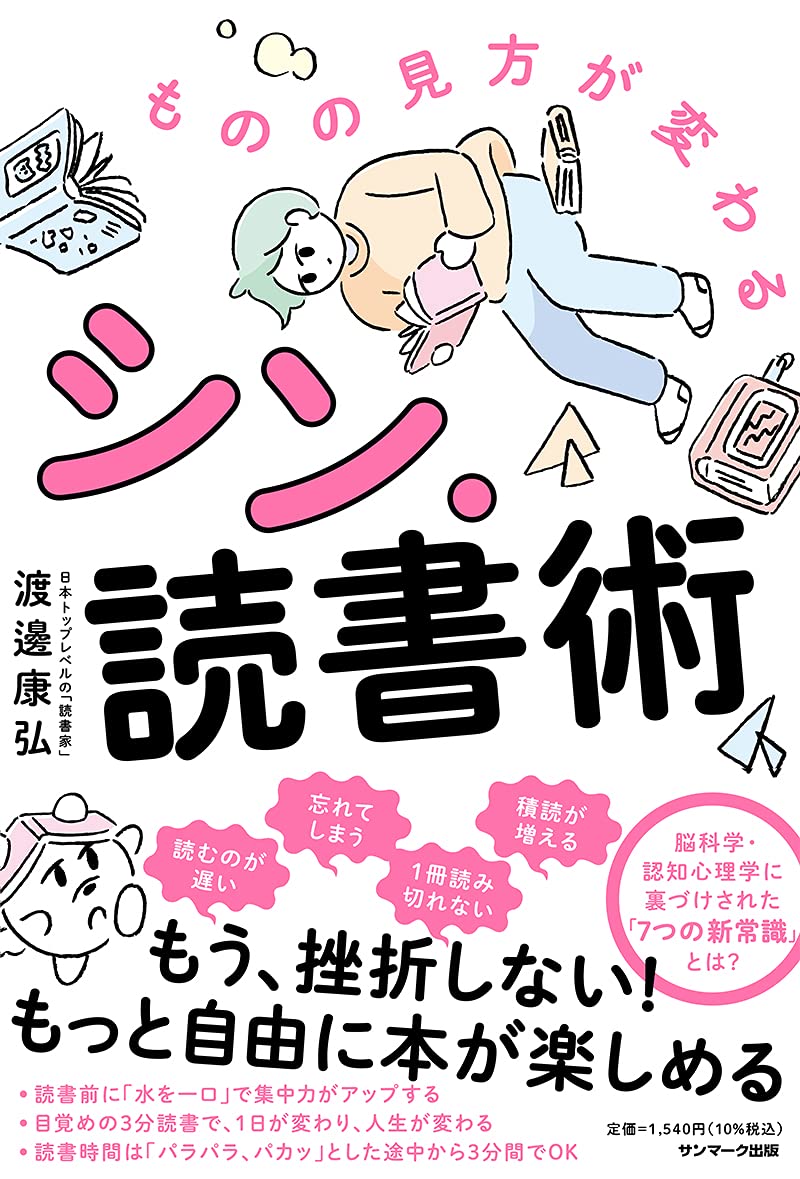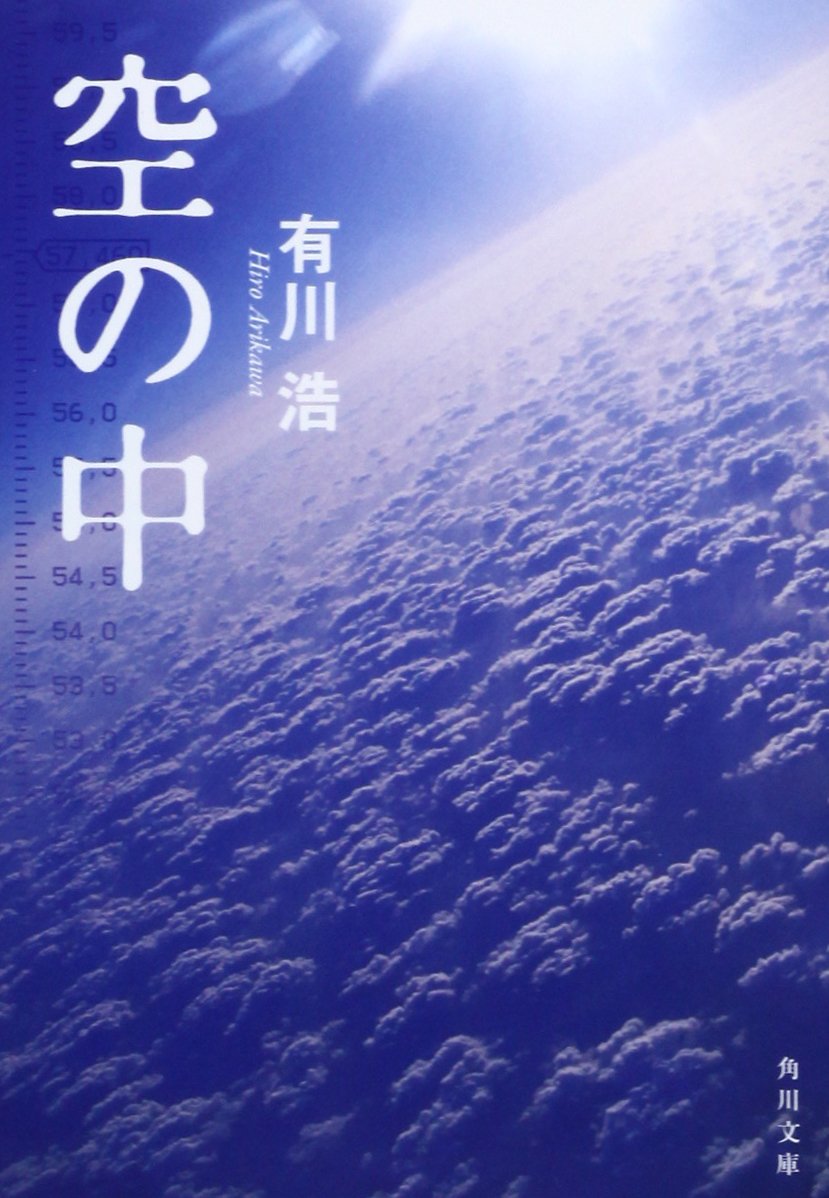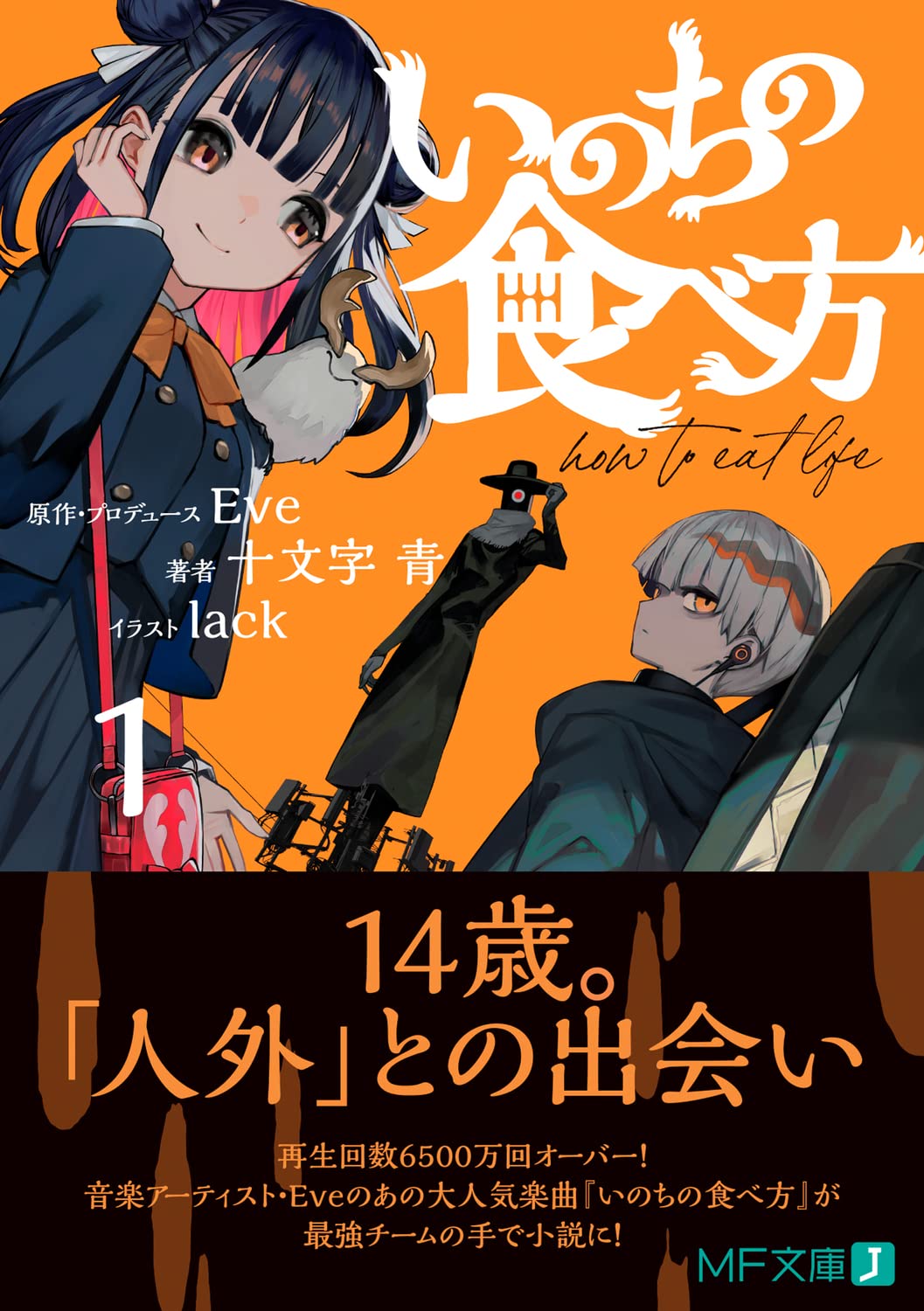10月26日(木)に開催された第7回 甲南大学書評対決(主催:甲南大学生活協同組合)で紹介された本です。
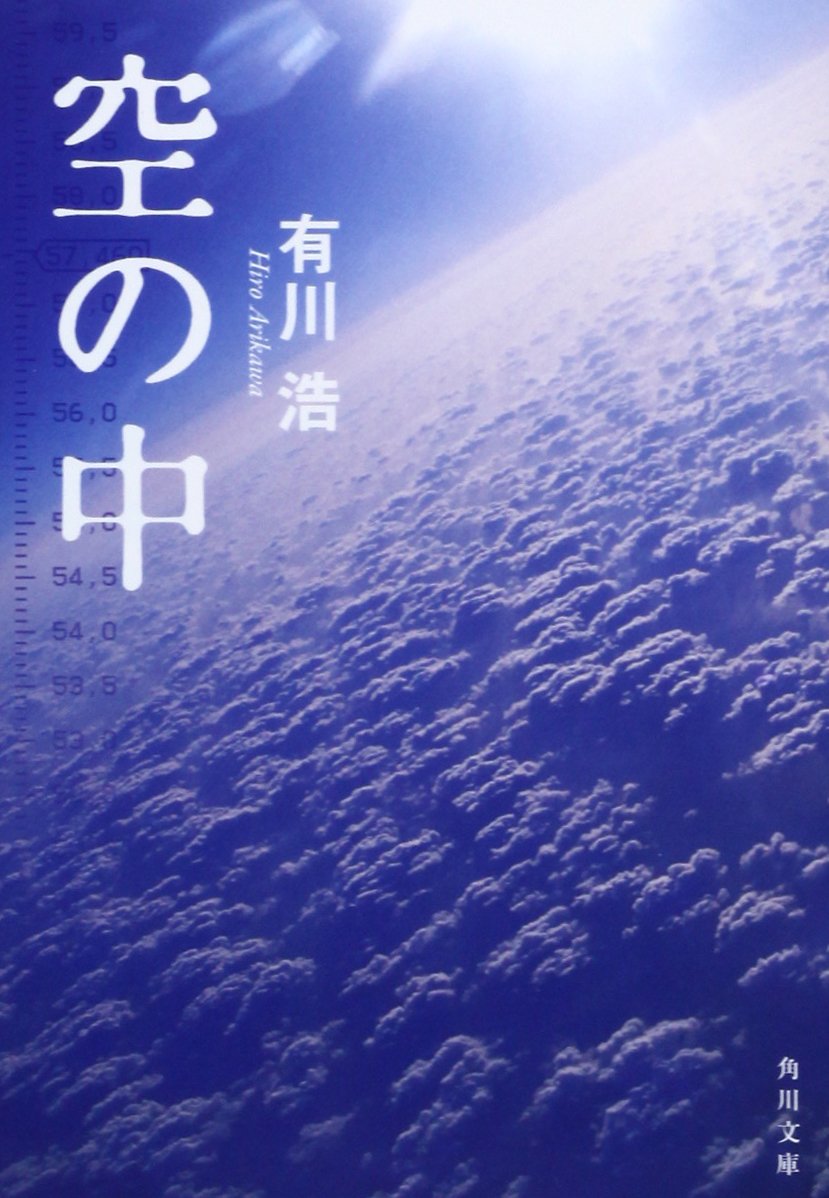
書道部甲墨会チーム 文学部2年 田中 杏佳さんからのおすすめ本です。
書名 :空の中
著者 : 有川浩
出版社: 角川文庫
出版年:2008年
田中さんの紹介してくれた本は、有川浩さんの『空の中』。大人と子ども、二人の主人公が自分の中に折り合いをつける物語です。
以下、田中さんからの書評です。
高度2万メートルの上空で、飛行機が爆発する不可解な事故が相次いだ200X年。ある日、高校生の瞬は海で不思議な生き物を拾いました。家に帰ると、とても仲の良かった航空自衛隊パイロットの父が亡くなったと知らされます。一人になった瞬は、感情を吐き出せないまま、着信履歴に残った父の番号に電話をかけてみます。呼び出し音が何十回にもなったとき、突然通話が繋がり、やがて雑音まじりの声が聞こえました。それは拾った生き物が、電波をジャックして発した言葉でした。父の死は頭の隅に追いやられ、瞬は謎の生き物にのめり込んでいきます。
一方、事故の調査のため、メーカーの担当者と、事故から生還した自衛隊パイロットは再び高度2万メートルの高さへ飛びました。事故に共通するその空域で、二人は都市を覆えるほどの「何か」と出会います。その「何か」と瞬に拾われた生き物は、元は同一個体であったことがわかり・・・
二組のカップルが織り成すスペクタクルエンタテイメントです!
第7回 甲南大学書評対決、生協書籍部で実施中! | 甲南大学図書館ブログ (konan-u.ac.jp)も合わせてご覧ください!