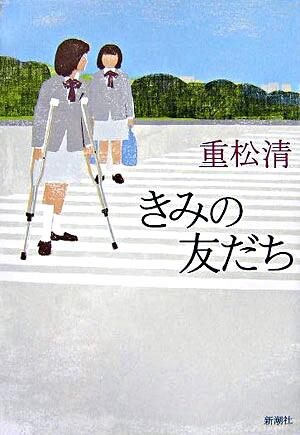
知能情報学部 4年生 団野 和貴さんからのおすすめ本です。
書名 : きみの友だち
著者 : 重松 清著
出版社:新潮社
出版年:2005年
「友達100人出来るかな」春になるとよく耳にする童謡である.小さい頃に私も,友達がたくさん出来ることを願って口ずさんでいたように思う,本当に100人も作れるだろうか.100人も友達が必要だろうか.
この小説で言う「きみの友だち」とは,交通事故に遭い松葉杖生活を余儀なくされ,周りに当たり散らし孤立していった恵美,病気がちで入退院を繰り返していた大人しい由香.彼女達を取り巻くクラスメートの事である.
友達は100人必要か.離れていても心の中で一生忘れない友達が本当の友達,だという人は100人も必要ない.しかし,みんなを敵に回したくない,同化していたいと思う人は,友達が100人必要になってくる.どちらが正解という訳ではなく,どちらも正解と言えるだろう.
この本を読んで,「友だち」の定義,存在について,ぜひ考えてほしい.私は,「いなくても寂しく感じないのが友達」だと思う.私は,友だちとは,お互いに気心が知れていつも一緒にいるから,いないと寂しいものだと思っていた.しかし,それだと単に群がっているだけで,大切な時間を共有しているわけでもなく,それぞれがバラバラなのだと感じた.だから,友だちは100人も作る必要はないと感じる.

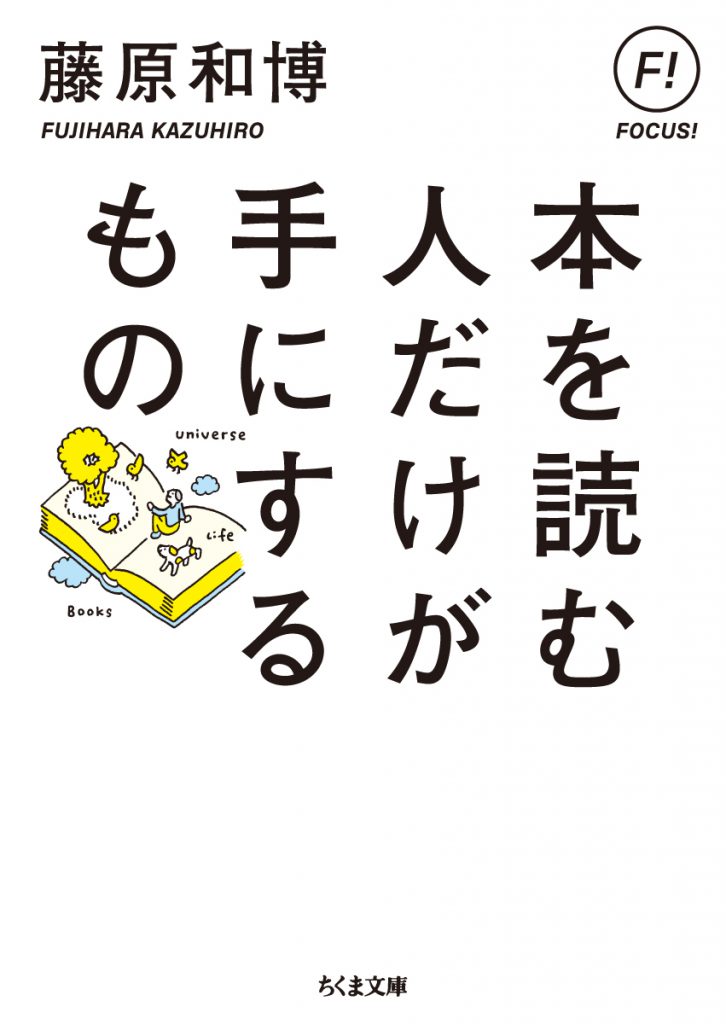
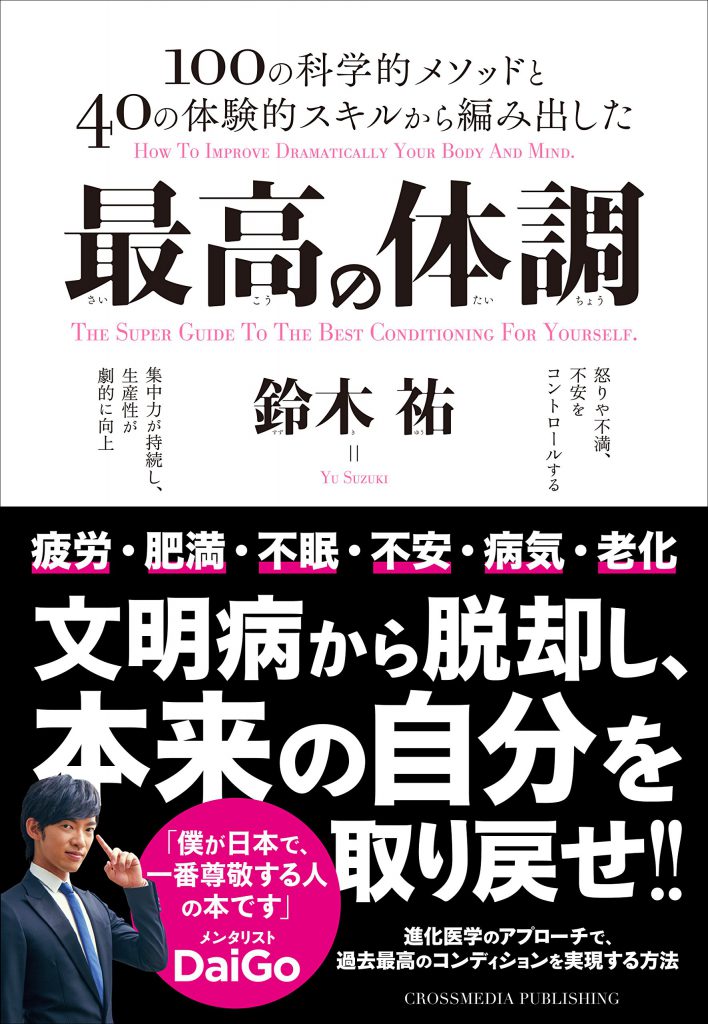
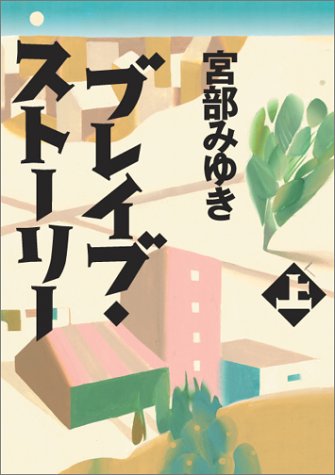
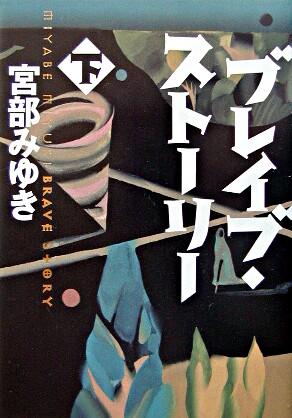

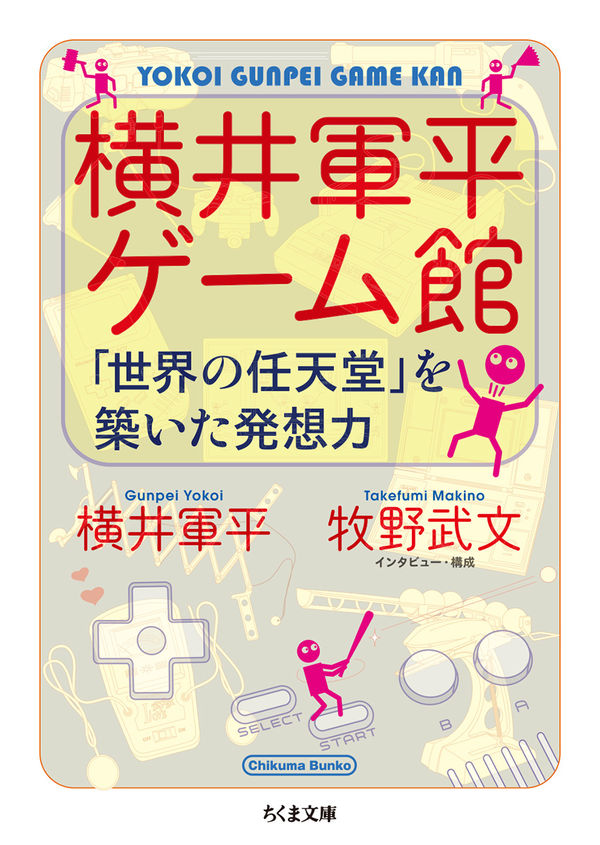 知能情報学部 4年生 Hさんからのおすすめ本です。
知能情報学部 4年生 Hさんからのおすすめ本です。