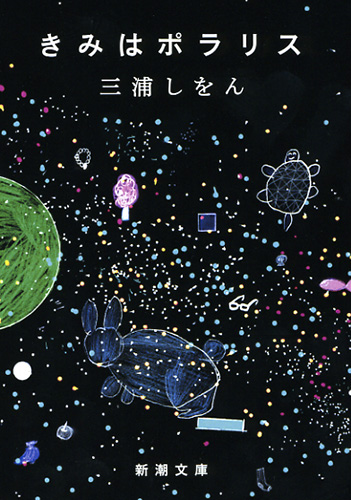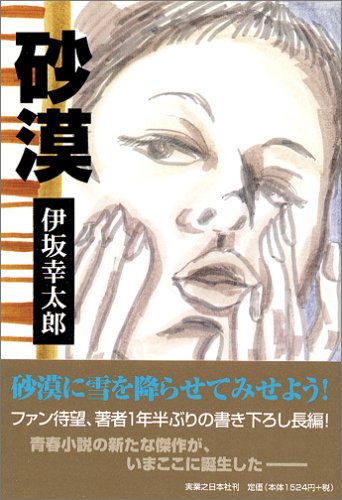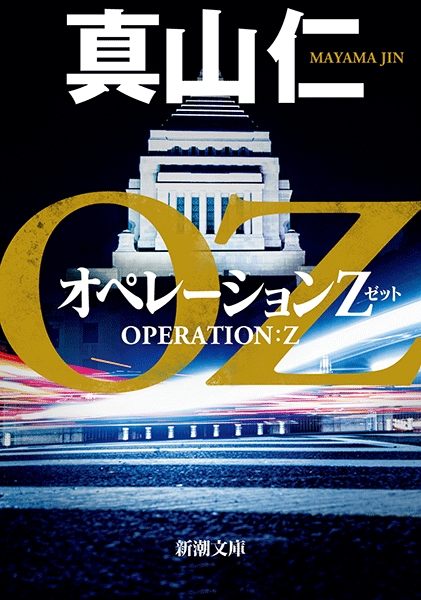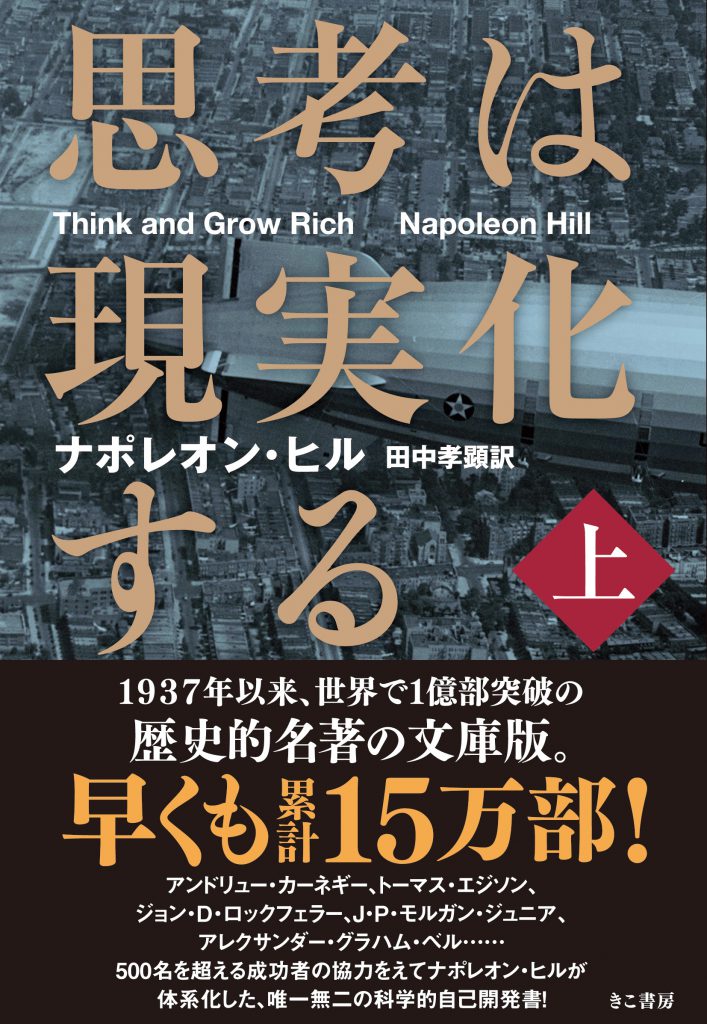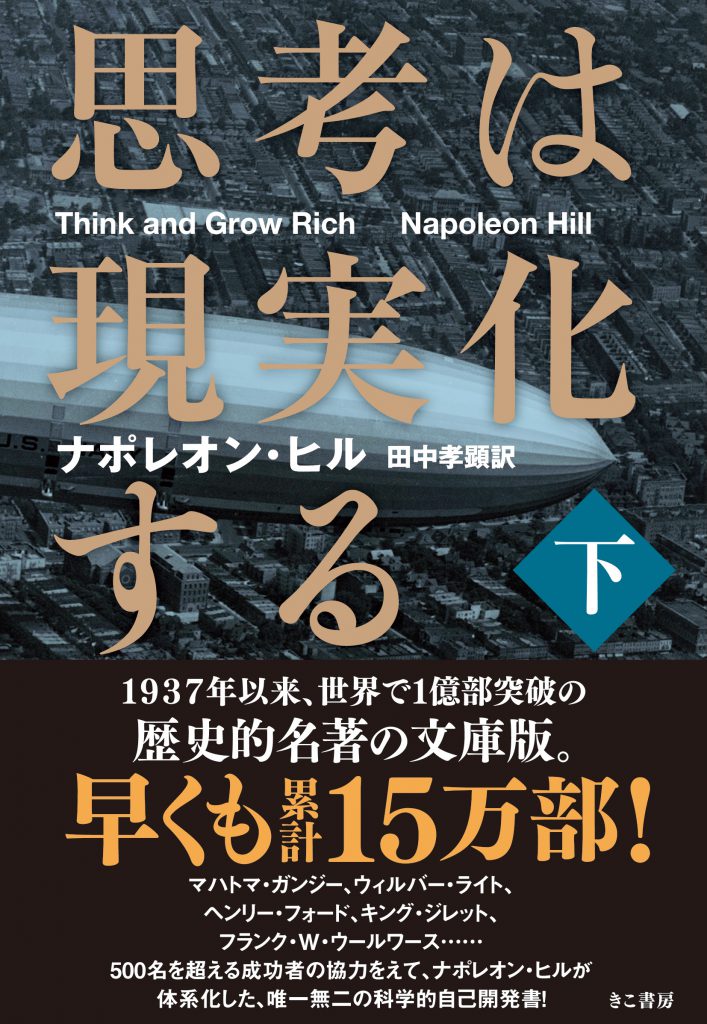マネジメント創造学部 1年生 塩谷 瑠緋さんからのおすすめ本です。
書名 : ドルフィンデイズ!
著者 : 旭 晴人著
出版社:KADOKAWA
出版年:2018年
フリーダイビングが好きな少年、潮蒼井は、就職先がなかなか決まらず、フリーターとニートのハーフ状態を続けていた。そんな時、父親が紹介してくれた求人、それがドルフィントレーナーだった。採用試験当日、蒼井は生まれ持った視力の良さで、事前審査を通過し、実技試験も途中までは難なくこなした。しかし最後、イルカとのコンビネーション演技で、蒼井は最難度の演技、イルカロケットを成功させたにも関わらず、採用試験に落ちてしまう。納得がいかず、蒼井はずっと不合格の原因を考えていた。その時に思い出したのは、コンビネーション演技で一緒に演技したイルカ“ビビ”の存在だった。蒼井はイルカロケットを成功させることができた喜びのあまり、一緒に演技をしたビビのことを考えていなかったのだ。それに気づいた蒼井は会場に戻り、ビビに自分の過ちを謝罪し、それを見ていた試験監督、海原は周りの従業員と相談して蒼井を合格にする。
晴れてドルフィントレーナーになった蒼井は、蒼井の相棒になったビビと共にショーデビューを目指して働き始める。しかしその矢先、イルカには致命的な異変がビビに見つかる。
私は、この本を読んで、どうして落ちてしまったのかを考え、原因に気づき、関係者以外立ち入り禁止のバックヤードにわざわざ出向き、海原や周りの従業員に、ビビに謝らせてほしいと頼み込む蒼井の行動にとても驚かされた。私が考えるに、普通の人なら、落ちた原因も考えず、原因に気づいたとしても、ビビに謝りたいと考える人はあまりいないと思う。落ちてしまった以上、いくらイルカに謝っても意味がないからだ。しかし、蒼井はそうではなく、落ちたことによる憤りは感じていたものの、一緒に演技を成功させたビビを一人プールの中に置いてきぼりにしてしまったことに気づき、すぐに試験会場に引き返し、海原たちにビビに謝らせてほしいと一生懸命頼み込んでいた。この姿を見て私は、蒼井はとても心優しい青年なのだなと思った。この本を読んで、私は、生き物へ愛情を注ぐ大切さを学ぶことができた。