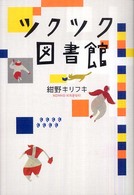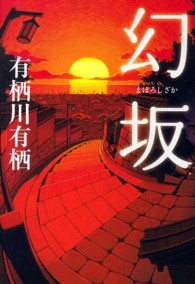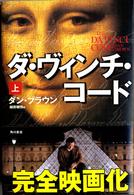知能情報学部 3年生 匿名さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名:7つの習慣ティーンズ【リニューアル版】
著者:ショーン・コヴィー
出版社:キングベアー出版
出版年:2014年
先生から「読んでおきなさい」と言われ、この本を渡されたのがこの本だ。題名からしてとっつきにくい本だと最初は感じたが、いざこの本を読むと意外と読みやすいといった印象を受けた。この本は題名にある通り、人生をよりよくする『7つの習慣』について、その習慣が大切な理由、並びにその習慣を身に着けるにあたっての注意や心がけ、行動について書かれている。また、『7つの習慣』について説明する際、著者は自身が言った言葉や著者へ送られたメッセージや有名人や偉人の言葉、他作品で出てきた言葉を引用することによって、著者の伝えたいメッセージに説得力があり、尚且つよく分かるようになっている。そのため題名に『ティーンズ』とあるように、10代の人が読んでも内容が充分理解できる。また、この本には他のこの手の本にはあまり見かけない「俗語」をよく見かける。この俗語も10代の人が読んでも内容を理解しやすくする工夫としてとらえることが出来る。無論、10代の人以外が読んでもこの本の内容は役に立つ。
この本の文章中には、「主体的」と「信用口座」という単語をよく見かける。前者の「主体的」は価値観による行動のことを指し、『第一の習慣』の中に深く関わっている。本の文章中では、「主体的」の反対としてその場の衝動で動くことを「反応的」という単語で表し、「反応的」に行動することによるデメリット、「主体的」に行動することによるメリットを。
後者の「信用口座」には二種類ある。自身に向けて作られる「信用口座」と他者に向けて作られる「信用口座」だ。「信用口座」は、信用の預金・引き出しを行い、「信用口座」にある残高が、その人をどれほど信用しているか、という指標となる。この「信用口座」という考え方はこの本では『7つの習慣』の中でも重要な要素となっている。
この本の題名には「ティーンズ」とあるが、無論10代ではない人が読んでもこの本の内容は読んだ本人のためになる。今の自分に納得していない人、自分の可能性を諦めている人にはこの本を勧める。