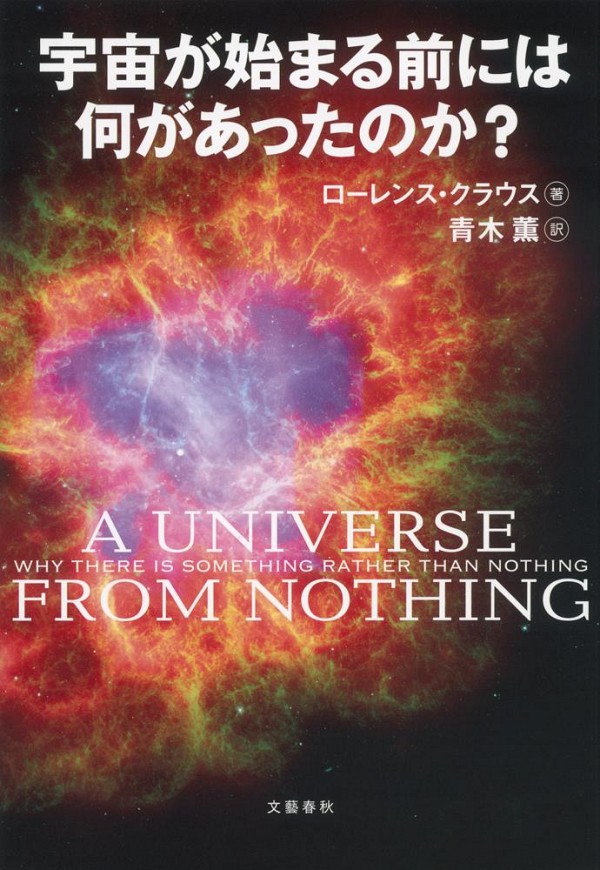まだまだコロナ禍が落ち着かないなか、例年夏に実施しているブックハンティングツアー(学生店頭選書)も中止せざるをえない状況です。
そこで、KONANライブラリサーティフィケイトのエントリー学生を対象に、学生が読みたいと思う本を自由に選んでメールで申請してもらうオンライン選書を実施しました。
学生たちも慣れないオンライン授業で大変なところ、何名かの学生が参加してくださいました。ご協力ありがとうございます!
すでに所蔵している本などを調査し、最終的に発注したのは26冊となりました。10月上旬には図書館に配架される予定です。
また実施することもあるかと思いますが、次回はもっとたくさんの人に参加してもらえるよう図書館も工夫したいと思います。
学生の皆さんの積極的な活動を図書館も支援していきますので、これからもお互いコロナに負けず頑張りましょう!
国際言語文化センター 要木 佳美先生へのインタビュー
文学部 3年生 友江 輝人さんが、国際言語文化センター 要木 佳美先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
Q . 本を読むのは好きですか。
A . 好きです。
Q . どんな本を読まれることが多いですか。
A . 中国関係の本が多いです。
Q . どういった時に本を読まれますか。
A . いろいろなテーマで研究するときに読みます。
Q .中国語に興味を持ったきっかけを教えて下さい。中国・中国語の魅力について。
A . 中国を研究するために必要だからです。自分の知らない世界を知りたい。
中国は広大で、歴史も長く、スケールが大きい。中国語は文法がシンプルで学びやすい。
Q . 中国語を学ぶにあたっておすすめの本はありますか。
A . 『why ? にこたえるはじめての中国語の文法書』 (相原茂ほか・同学社)
Q . 好きな作家や作品について教えて下さい。
A . 中国古典文学では、杜甫、李白。中国古典小説では、『紅楼夢』(曹雪芹)、『聊斎志異』『三国志』『水滸伝』『西遊記』。中国近代文学では、『子夜』(茅盾)、『阿Q正伝』(魯迅)、『家』『寒夜』(巴金)、『駱駝の祥子』『四世同堂』(老舎)。近代西洋文学では、『谷間の百合』『従妹ベッド』(バルザック)、『桜の園』『三人姉妹』『ワーニャ伯父さん』(チェーホフ)、『ボバリー夫人』(フローベル)、『月と六ペンス』『人間の絆』(モーム)、『変身』『城』(カフカ)、『アンナカレーニナ』(トルストイ)、日本古典文学では、『源氏物語』(紫式部)。おすすめの一冊は、『戦争と平和』(トルストイ)です。
Q . 先生の考える読書について。
A . 実際の人生で体験することのできない時代や国の事を教えてくれます。
読書は想像力を育て、社会に出た後の人生の力になります。
─インタビューを終えて。
お忙しい中、優しく丁寧に対応して頂きました。
好きな作家や作品についてお伺いした所、こんなにも沢山紹介して下さったことから、先生の読書が好きな人柄が目に浮かびます。
好きな本を楽しんでたくさん読んでほしいと、そう述べる先生から「きっと人生の宝物になると思います。」という言葉を頂きました。
今回のインタビューで学んだことをこれからに生かしていきながら、楽しく読書に触れることを続けていきたいと思います。
<要木 佳美先生おすすめの本>
トルストイ 著 藤沼 貴(翻訳) 『戦争と平和』岩波書店 , 2006年
(インタビュアー:文学部 3年 友江 輝人 )
[藤棚ONLINE]経済学部・森 剛志先生推薦『革命前夜』
図書館報『藤棚ONLINE』
経済学部・森 剛志先生 推薦
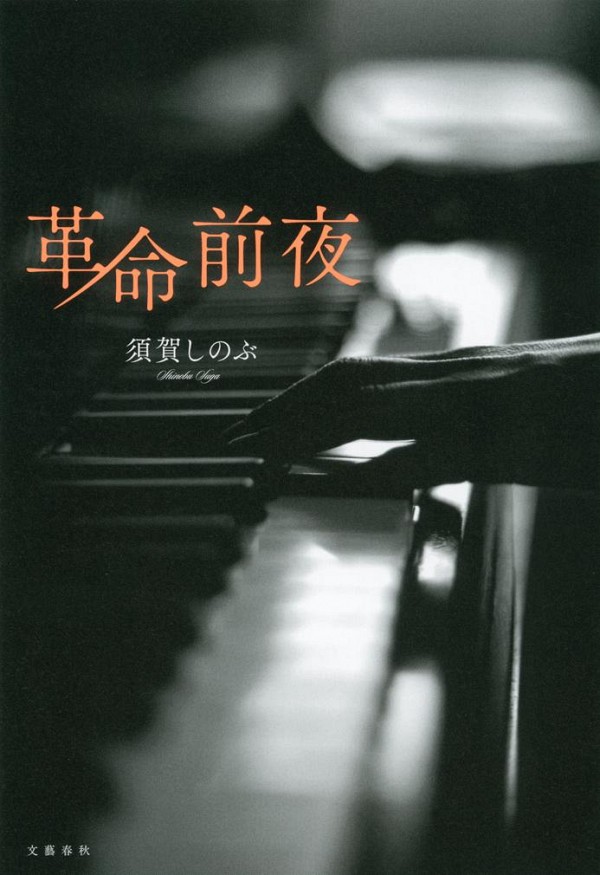
書名:革命前夜
著者:須賀しのぶ
出版社:文藝春秋
出版年:2015年
監視国家での人間関係は2つ:密告するか、しないか
こんな小説があったのか。可憐にして重厚、しかもエンタメ感十分の内容の文章が体内に脈打ち流れてくる。読み終わってしばらくぼっと放心状態だ。昭和が終わったその年(1989年)、ピアニストを目指して1人の日本人青年眞山柊史(マヤマ・シュウジ)が東ベルリンに到着する。冷戦末期の東ドイツの雰囲気は、母国日本とは大違いだ。人が人を監視する社会。なぜ、一介の日本人留学生に最初から外務省職員が同伴するのか読み進めるうちにわかってくる。ここは監視社会なのだ。しかし、シュウジが志すピアニストの世界は、才能と人生をかけて世界中から集まった天才・鬼才ぞろいだ。息の詰まるような熾烈なピアニストの世界を堪能したかと思うと、時代は大きく音をたてて動き出す。自由を奪われた東ドイツの若者たちが抗議活動を起こしだす。その中には、圧倒的な美貌と美しい演奏を奏でるクリスタもいる。シュウジも否が応でも、この時代のうねりの中に巻き込まれていく。そして、ついにその時がくる。ベルリンの壁崩壊。決して過去の出来事ではない。いま、なぜ香港の若者が熱くなっているのか。日本にいながらでも、今の時とその時を重ね合わせながら読み進めることができる青春エンタテイメントだ。
[藤棚ONLINE]理工学部・須佐 元 先生推薦『A Universe from Nothing』
図書館報『藤棚ONLINE』
理工学部・須佐 元先生 推薦
新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。皆さんはこれまでも沢山の本を読んで来られたと思いますが、これからの四年間は、たっぷりと読書の時間が取れる人生の中でとても貴重な時間です。読書はまずは楽しみであり、同時に知識を得るための一つの方法です。ジャンルにこだわらず読みたい本をできるだけ沢山読んでください。そこで得た知識は糧となり、また身についた読書習慣は今後の長い人生に、人工的ではない美しい色合いと深みを与えてくれるはずです。みなさんの選書の助けとなるかどうかわかりませんが、私が最近気に入った本を紹介しておきます。
「A Universe from Nothing (邦題:宇宙が始まる前に何があったのか?)」文藝春秋
ローレンス・クラウス著 青木薫訳
本書は素粒子論から宇宙論の研究に進んだ著者が、宇宙に対する現在の理解の先端までを独特の語り口で述べたものです。なかなか難解な部分もありますが、前半は観測的・理論的にかなりの程度確立されてきたビッグバン宇宙論についての記述が中心です。後半では理論的に「ユニバース」ではなく「マルチバース」ではないかと考えられている先端の宇宙観について紙面が割かれています。全編通して著者は科学的思考法とはなにかについてしつこく語りかけてきます。無からの宇宙創生の物語はしばしば宗教的・哲学的論争を引き起こすので、著者はそのような見方を徹底的に排除する立場に立って論を進めて行きます。一方的に著者の主張を受け入れる必要はありませんが、物事を考えるときの真摯な科学的思考法から多くを学ぶことができると思います。われこそはと思う人は手にとって見てください。
以上推薦しましたが、とにかくそれぞれがそれぞれの興味の赴くままに本を読んで下さい。
ウィリアム・ギブスン著, 黒丸尚訳『ニューロマンサー』
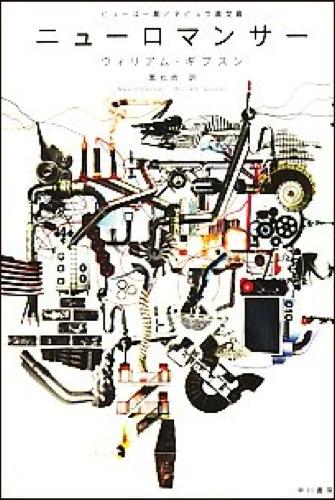
書名:ニューロマンサー
著者:ウィリアム・ギブスン著, 黒丸尚訳
出版社:早川書房
出版年:1986年
法学部1年 和田颯太朗さん(「基礎演習(濱谷)」リサーチペーパーより)
まず、作者のウィリアムギブスンは1948年にアメリカに生まれたSF作家である。幼少期に引っ越しを繰り返したことによりSF小説をよく読む内気な性格へと成長し、1984年にビブリオバトルで紹介したニューロマンサ―で小説家デビューする。作中でも日本が舞台となっているように日本への関心も深い。脳とコンピューターの融合や、サイバースペースという概念は彼が生み出したと言われている。彼の描くSFはサイバーパンクというジャンルに属するが、このサイバーパンクというジャンルも彼が生み出したジャンルである。
第二に、ニューロマンサーが与えた影響については、後のサイバーパンクと名のつく作品すべてに影響を与えていると言ってもいい。「攻殻機動隊」や「マトリックス」などは特に影響を受けている。ニューロマンサーが与えた影響は作品だけではなく、現在開発されているVRなどのデザインのモデルになるなどテクノロジー自体への影響も大きい。影響とは言えないが、作中で登場しているものが既に実現しているものはいくつかある。高度な知能を持つAIや、体を一部機械にかえる義体化技術などニューロマンサーが出版された1984年には誰も想像していなかったようなことが次々と実現している。
第三に、あらすじ及び世界観についてである。サイバネティックス技術が進歩した世界でと電脳ネットワークが地球を覆い尽くしており、宇宙でも月などのコロニーで生活している人間もいる。財閥とヤクザとよばれる多国籍企業が経済を管理している社会で、戦争も頻発していおり、社会は荒廃している。AIもかなり発達しており、人格を有するAIが存在し、AIが完璧な存在となり人間を超えないように管理するチューリング機関がある。あらすじについては非常に登場人物が多く、長くなってしまうのでかなり省略して説明する。まず、主人公のケイスはハッカーとして仕事をしていたが、とある失敗により、二度と電脳ネットワークに接続できない体にされてしまう。そこに謎のアーミテジという男に強引に仕事を依頼され、サイボーグのモリィと共にアーミテジからの仕事をこなしていく。しかし、実際はアーミテジという男は存在せず、人格を失った男をウインターミュートというAIが操っているだけである。仕事の目的も宇宙に居る高度なAIとウインターミュートが融合するためのもので、ケイスなどを雇っていた理由は先述したチューリング機関に捕まらないようにAIと融合するためであった。最後には融合を果たしたウインターミュートが遠い宇宙から「同族」の信号を受信し、宇宙に旅立つというシーンで終わる。
ニューロマンサーの最も重要な部分はただテクノロジーが進化した世界を描いている訳ではないということである。世界は電脳ネットワークに覆われているが、この技術を使うことのできない人と使うことのできる人の格差は拡大し、経済は「財閥」「ヤクザ」とよばれる多国籍企業に管理されている。こういった問題は現実となり始めている。アメリカと中国の巨大企業が競争を繰り返し、インターネットを使える人と使えない人との差は拡大する一方である。進化するテクノロジーという点についても、人格を有するAIと人間をどう区別するのか、AIの進化をどこまで許すのかという問題がある。作中でもチューリング機関というAIの進化を管理する機関が存在するが現実でもそういった機関又は規則が設立されるのは時間の問題であると考える。作中ではほとんどの人間が脳とコンピューターを融合させているが、脳をコンピューターに置き換えたとき、意識はどこに有るのか、ロボットに人間の区別はどうつけるのか、生と死の境はどこに有るのかといった課題もある。実際に死後脳を取り出し、完全な脳のコピーをつくり新しい体とつなげ生き返らせるという研究が行われている。生き返った後意識は脳のコピーに宿るとされているが、それが本当に生前の自分であるのかといったことは実際にやってみなくてはわからない。こうした近い将来実現するであろう問題を考えることができるということが、ニューロマンサーを含むサイバーパンク作品の面白いところであると考える。
朝霧カフカ原作, 春河35漫画『文豪ストレイドッグス』
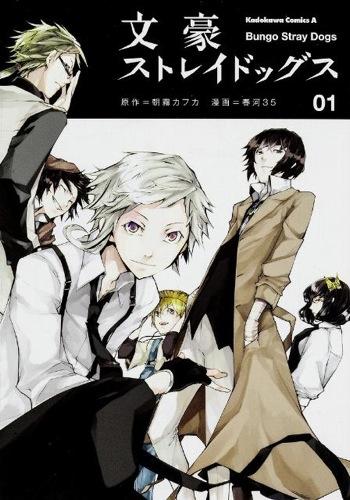
書名:文豪ストレイドッグス
著者:朝霧カフカ原作, 春河35漫画
出版社:角川書店
出版年:2013年~
法学部1年 吉川史華さん(「基礎演習(濱谷)」リサーチペーパーより)
まず、文豪ストレイドッグスという作品について紹介する。
文豪ストレイドッグスとは、現代横浜を舞台に、中島敦、太宰治、芥川龍之介など様々な文豪たちがキャラクター化され、それぞれの文豪にちなんだ作品の名前を冠した「異能力」という超常能力を駆使して活躍するアクションバトル漫画である。原作の漫画本編は、孤児院を追い出された中島敦が、入水自殺を図って川に流されていた自殺愛好家の太宰治を助ける場面から始まる。そのあとに起こるある事件をきっかけに中島敦は「武装探偵社」という異能力集団に入社し、横浜の港を縄張りとする兇悪な闇組織「ポートマフィア」や、北米を拠点とする異能力者集団「組合(ギルド)」、「魔人」ドストエフスキーと対峙するなど、次々と難事件に直面しては解決していく。作品内での重要な要素である「異能力」とは、例えば中島敦の「月下獣」は巨大で凶暴な白虎に変身する能力で、実在する文豪中島敦の「山月記」をモデルとしている。他にも、全ての異能を無効化する太宰治の「人間失格」、自身の外套を不定形かつ何でも喰らう「黒獣」に変化させ操る芥川龍之介の「羅生門」など、登場人物によって多種多様な異能力が存在する。漫画、小説、アニメ、実写化など多岐に渡り展開されるこの作品は「文スト」と呼ばれ、主に若い女性を中心に親しまれている。
文ストは原作を朝霧カフカさんが、作画を春河35さんがそれぞれ担当している。朝霧さんは文ストの小説版の大半も自らが執筆を担当しており、他にも「汐ノ宮綾音は間違えない。」や「水瀬陽夢と本当は怖いクトゥルフ神話」の漫画原作なども手掛けている。この作品が生まれたきっかけについて、朝霧さんは「文豪がイケメン化して能力バトルしたら絵になるんじゃないかと編集と盛り上がったから」と述べている。また、舞台が横浜になったのは春河さんが横浜出身であるからである。文ストは、このように存外軽い気持ちで生み出された作品なのだ。
現在、日本では活字離れの深刻化が騒がれている。確かに、10代、20代の若者で、好んで活字を読む人は決して多くはないと思う。特に大正・昭和期の文豪の作品となると、現代文の教科書や夏の読書感想文で、多くても両手で足りるほどの冊数を読んだことがある程度の人が大半だろう。そうした中で、「文豪ストレイドッグス」という作品に出合ってから、それらの本を手に取ってみたり、あるいは電子書籍などで読んでみたという人は実際かなり多い。角川文庫と文ストのコラボカバーの書籍も多く発売されているので、そちらを購入した人も多いだろう。私も、文ストを知ってから文豪の作品に興味が湧き、電子辞書に入っているものを読み漁ったり、コラボカバーの「人間失格」を購入したりして読むようになった。他にも、若者の文学離れを背景に来館者が伸び悩む全国各地の文学館が、文ストを扱ったイベントを開催して来館者を増やしているという記事もある。同記事には、「出版社や文学館は『若者が文学に関心を持つ入り口になれば』と期待してる」とも書かれている。
ある意味軽い気持ちで生み出されたひとつの作品が、漫画やアニメという枠を大きく超えてこれほどまでに多大な影響を与えることはそうそうないのではないかと私は思う。