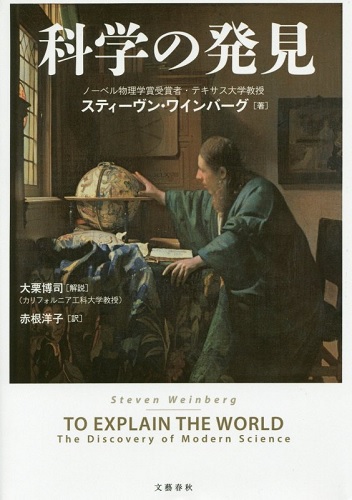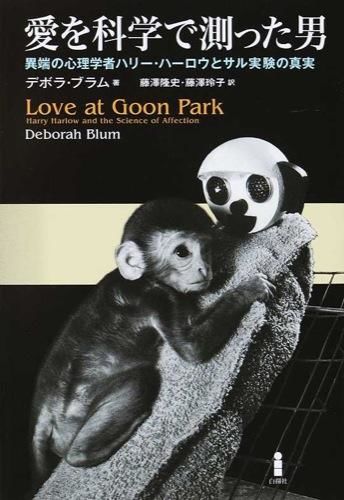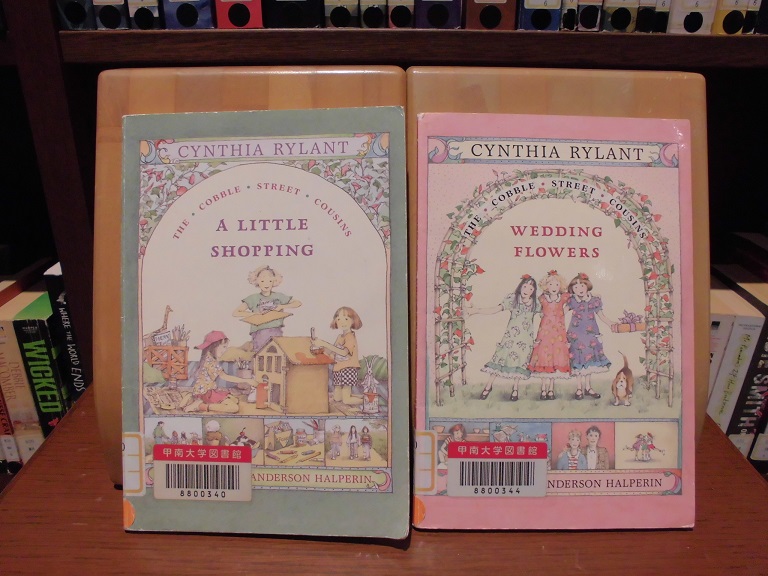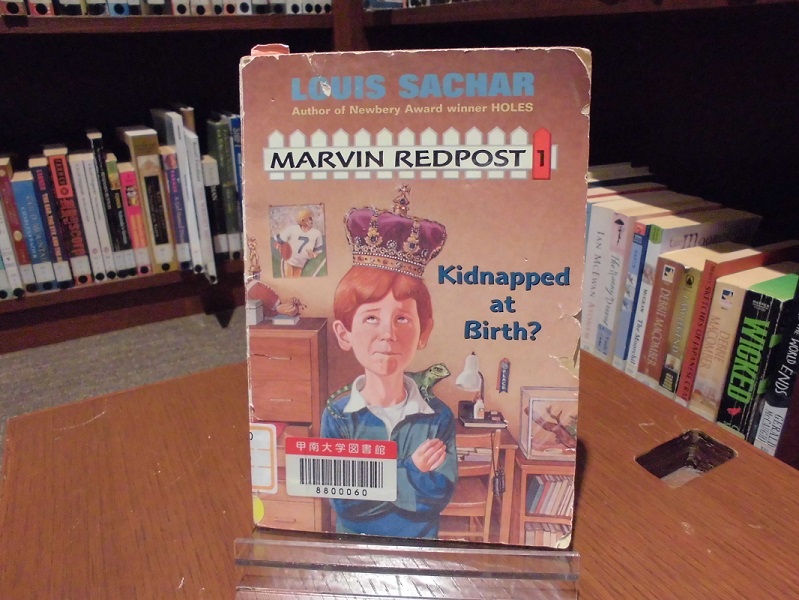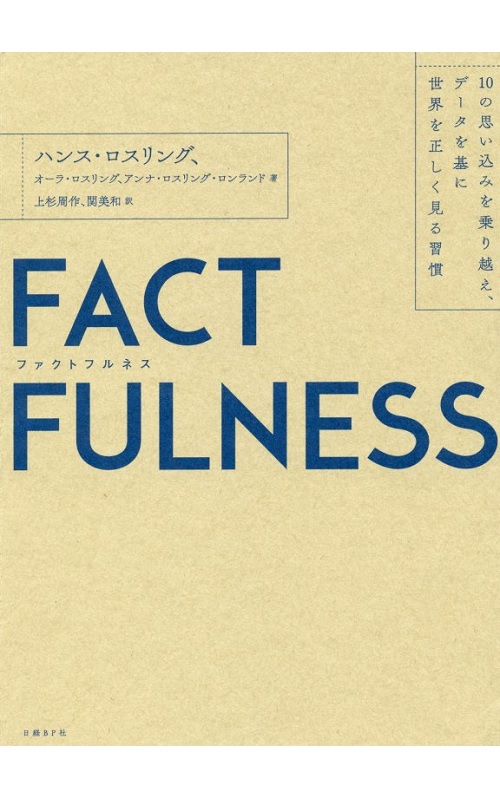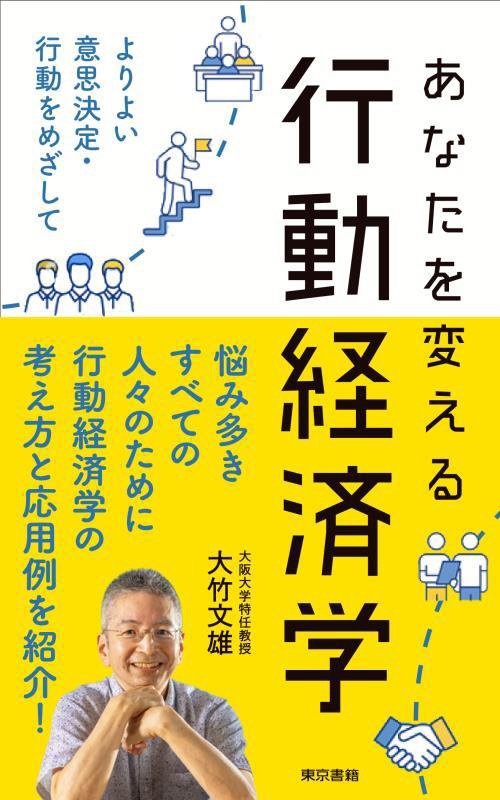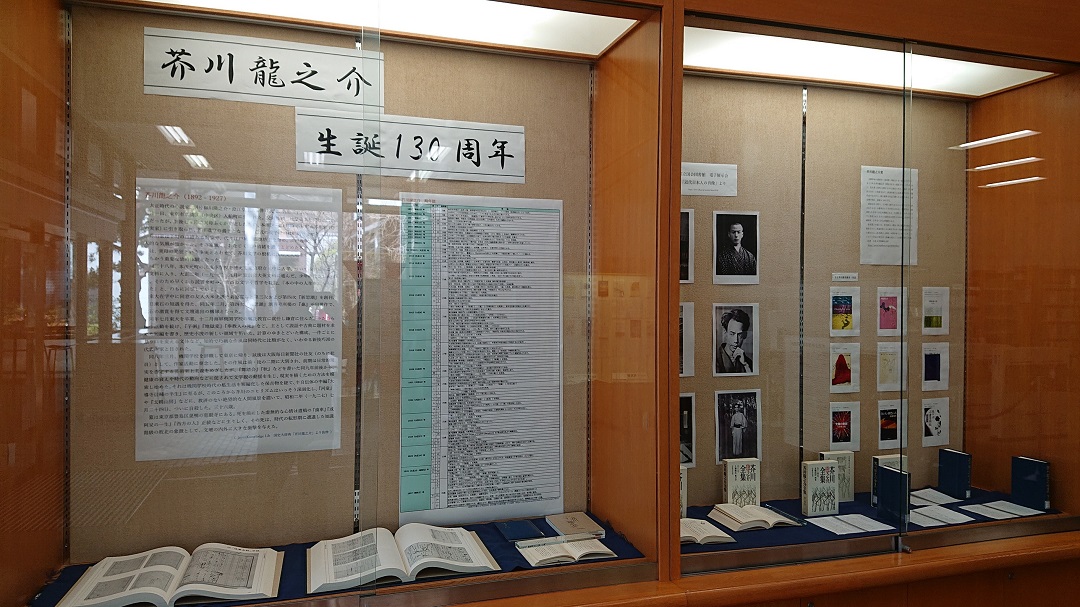図書館報『藤棚ONLINE』
理工学部・須佐 元 先生 推薦
『科学の発見』
本書は、昨年残念ながら他界されたノーベル物理学者のスティーブン・ワインバーグ氏による科学史に関する本です。
20世紀を代表する理論物理学者のうちの一人である著者が、古代ギリシャから現在までの、物理学・天文学を中心とした科学の歩みを講義してくれます。既に多くの書評があって、過去の科学者にダメ出ししているかなり激しい側面を多く取り上げています。確かに過去の科学者たちの考え方がいかに現在の科学的価値観と隔たったものであったかを、厳密に取り上げています。しかしながら著者も述べている通り、これによって「科学」それ自身が数千年にわたって紆余曲折を経ながら進化してきたこと、その過程で多くの科学者が苦闘し、それによって形作られてきた現在の科学の価値および未来への教訓を伝えようとしているのだと思います。
途中やや専門的で難しいところもありますが、サイエンスに携わる・志す人々一般にとって、手にとってみる価値はある本であると思います。