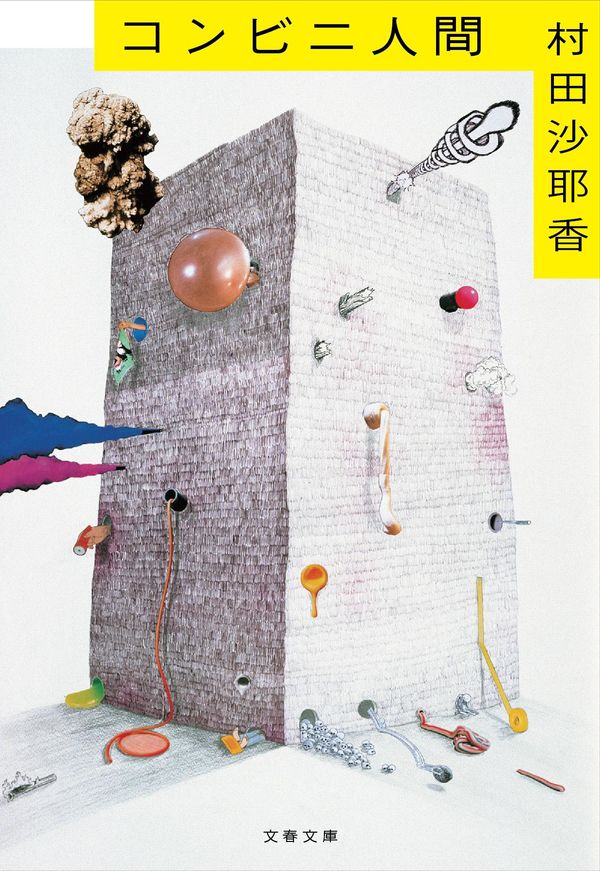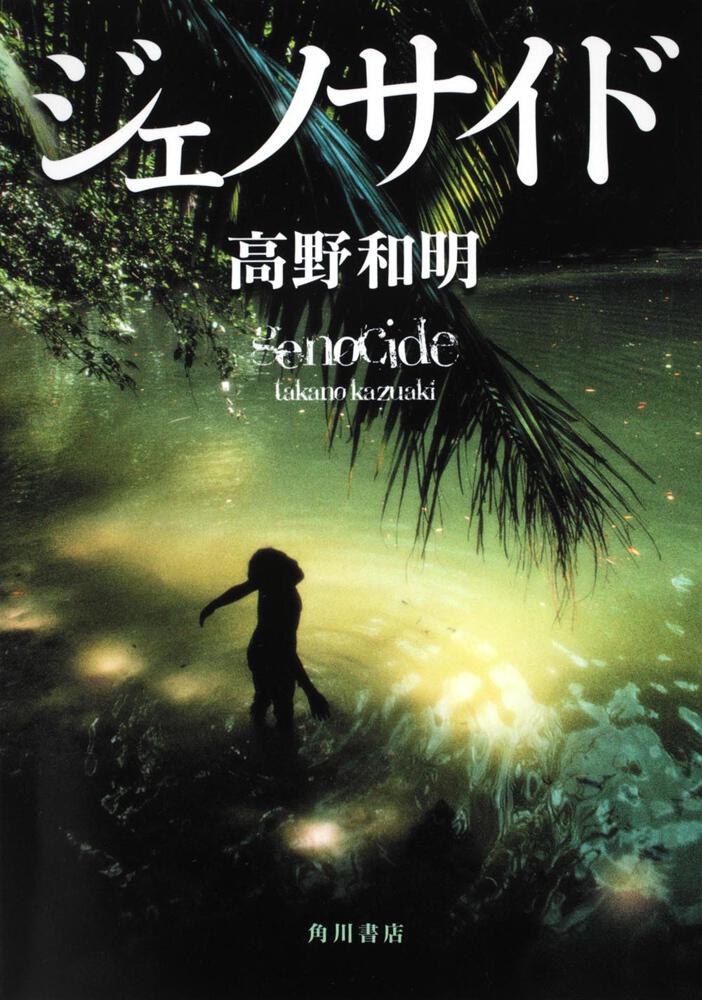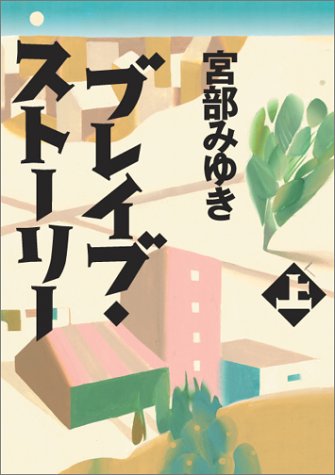
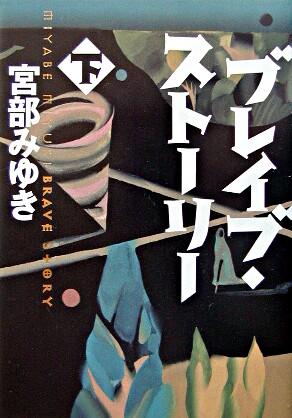
知能情報学部 4年生 団野 和貴さんからのおすすめ本です。
書名 : ブレイブ・スト-リ-
著者 : 宮部 みゆき著
出版社:角川書店
出版年:2003年
主人公のワタルは,小学5年生.父と母と3人で暮らす,ありふれた普通の人生.友だちと遊んだり喋ったりする,普通の人生.しかし,そんな人生に危機が訪れる.多感な時期に,両親の離婚危機や同級生との喧嘩.踏んだり蹴ったりのワタルは,ある日,異世界「幻界(ビジョン)」に通じる扉を発見し,女神のもとへ辿り着けたら自分の運命を変えられることを知り,旅に出る.そこで,仲間たちと出会い,剣も振ることができなかったワタルが,どんどん成長していく.
以上があらすじであるが,RPGのような世界観を感じるだろう.旅立つまでに時間がかかるが,一気にこの世界に引き込まれワタルと冒険している気分になる.本作は,物理的な強さよりも,精神的な強さに重きを置いている.子供はもちろん,大人も十分楽しめる.
「運命を変える」とはどういうことなのか.この物語を読めば,それが分かるだろう.人生は思いがけないこと,未知の要素で展開されていることが多い.では,「運命を変えたい」と願うとき,何を願うことなのだろうか.そして,「運命を変える」ことが何を手に入れることができるのだろうか.この本を読んだ後に,ぜひ考えてほしい.ワタルと読んだ後の自分を重ねることで,ワタルと一緒の強さを手に入れることができるだろう.答えは,人の数だけある。
ワタルと一緒に己と世界を見つめ直す長い旅をして,その答えを手に入れてほしい.


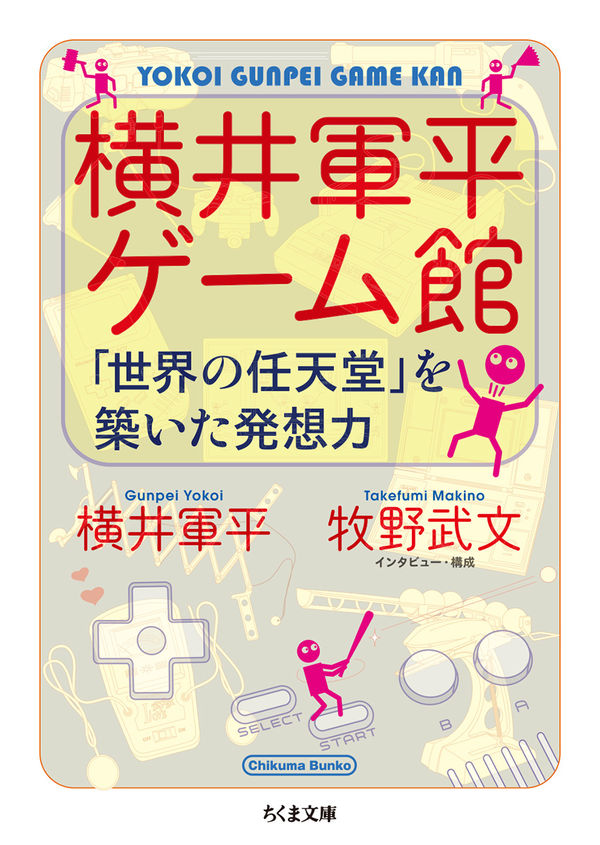 知能情報学部 4年生 Hさんからのおすすめ本です。
知能情報学部 4年生 Hさんからのおすすめ本です。