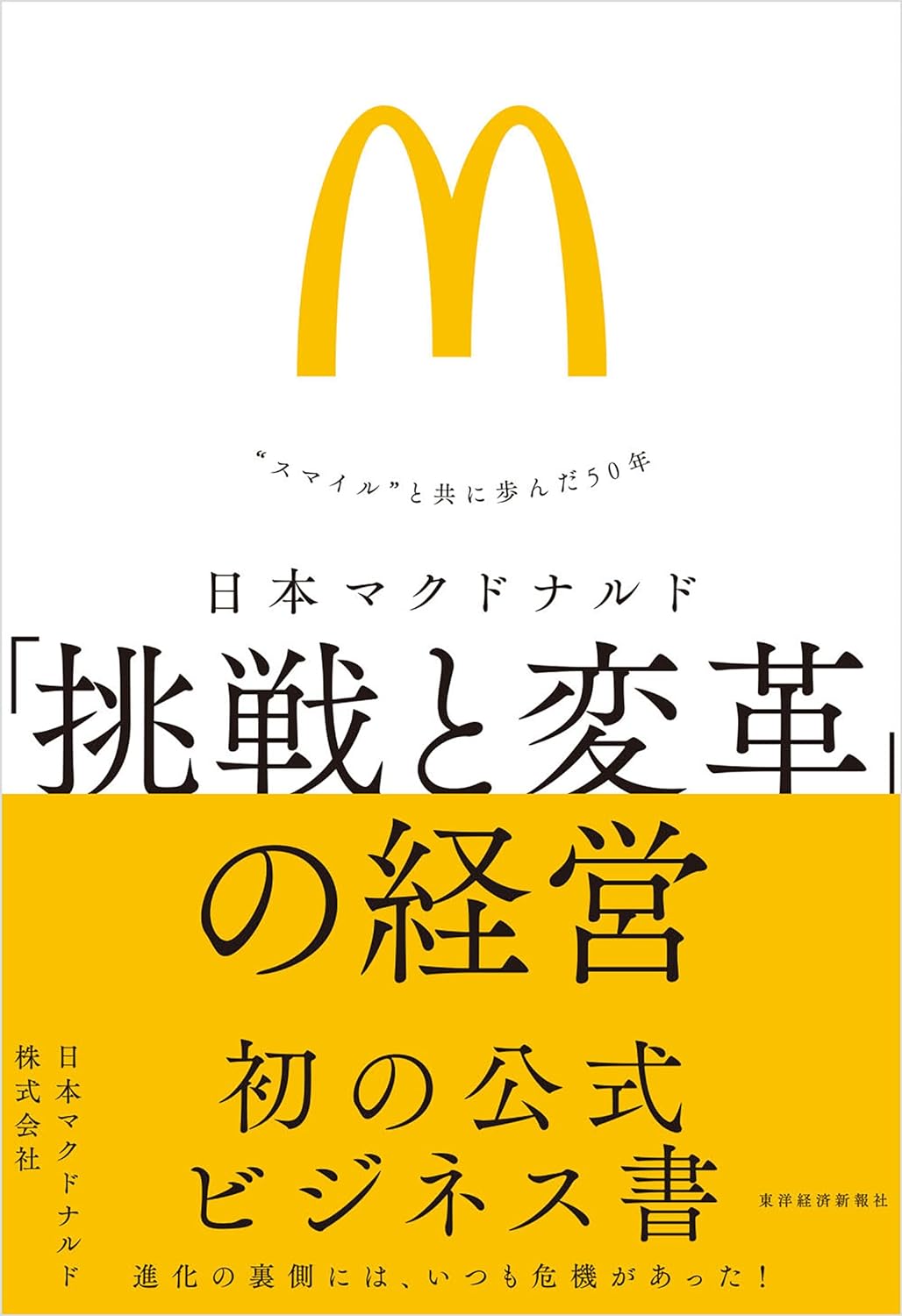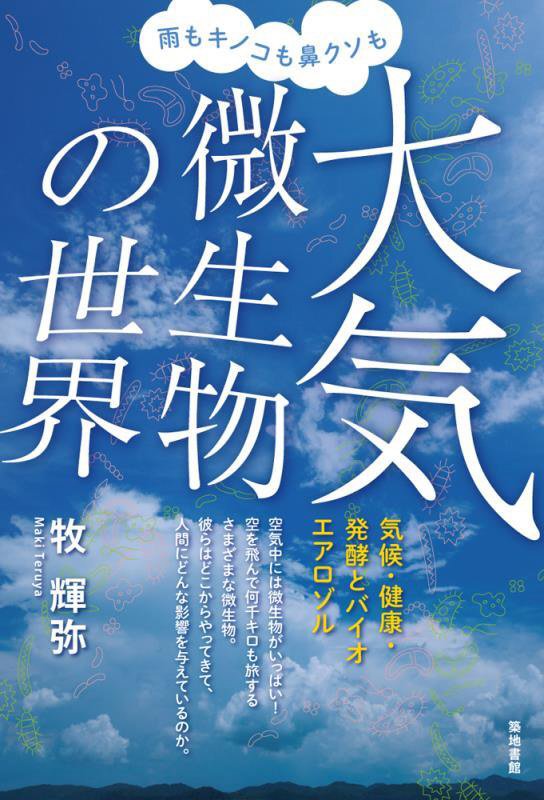文学部4年生 Kさんが、全学共通教育センター 本田 勝裕先生にインタビューを行いました。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
Q. 面白い本について
(1番目は)読んでいくうちに早く次読みたいって思うほど本に集中できる本。いい本って、匂いがする、声が聞こえる。読んでいると色々なことが本の中から立体になって現実のように読める本。
2番目が空想の世界に入っちゃう本。
Q. 印象に残っている本について(★…学生におすすめの本)
【大学以前】
C・S ルイス著『ナルニア国物語』
マーク・トウェイン著『トム・ソーヤーの冒険』
【大学時代】
F・スコット・フィッツジェラルド著『グレート・ギャツビー』
★司馬 遼太郎著『竜馬がゆく』
…未知の世界を知ることが面白く、また自由に生きる竜馬に憧れ、何度も読み返した。
★宮本 輝著『青が散る』
…大学を舞台として友情と恋愛が交錯する小説。世代を問わずに楽しめる。
Q. 行動と読書について
僕の思考と行動と、著者の考えや作中の人の行動が一致していると、自分と書物の関係が生まれる。
応援団になってもらえるというか共感できるというか。一人で頑張ってても不安だし、しょうがないし、だから読書によってそういう力をもらっているかな。
(自身の行動と矛盾する考えの本は)矛盾が面白いねん。(自身と著者の考えの)往復を読書を通じてやっているところはあるかな。
Q. 学生におすすめの本について
乱読をしてほしいかな。(海外文学には)日本にないものが書かれてるわけやんか、めっちゃ面白かった。そんな世界あんのって。知らない世界を知れるってのが大事。どこの国のどの作家が面白いかは読んでみないとわからないよね、就活と同じやな。
本を読むと扉が開いていくんよね。そうするとその先に行ってみたいと思う。行ってつまらなかったら、知識の世界と経験が違うっていうのがわかる。失うものがないから、コスパ、タイパを超えた世界がそこから始まることはあるよね。
Q. 読書の活かし方について
- 同じ本を数年後に再度読む
面白いのが、1回目には気づかなかったところに2回目面白いと思うところがある。なぜかっていうと僕が成長し変化してるから、本は変わっていない。
- SNSでの書評公開
読んですぐ書くこと。できれば24時間以内に。稚拙でいいねん。自分が感じたことやもん。
【効果】
(書評が)他の人に読まれることで、共感を生む、反感を生む、そしたら仲間ができたりするっていうのが1点。
もう一つ。表現力が上がってゆく。
- 本の舞台や作家に会いに行く
実際に現場に行ってみたりすると、またそこで人との出会いや景色との出会いがあったりしていくから面白いかなぁ。出かけてみないとわからないよね、それが読書の先にあるものかな。
【感想】
面白さと学びのあるお話を聞くことができ、とても充実した2時間でした。本の中の自由な竜馬に憧れたお話や、「挑戦しなければ失敗もない」ことを学んだ本の著者に会いに行かれたお話から、本田先生のエネルギッシュさには、本の影響もあるように思いました。編集者時代のお話も興味深く、面白いことを伝えていく楽しさが、現在のお仕事と共通しているというお話がとくに印象的でした。
ご紹介いただいた本はすべて、読んでいて立体になる本だそうです。そのような読書体験をしたことがないので、読んでみたいです。
(インタビュアー: 文学部4年生 Kさん)