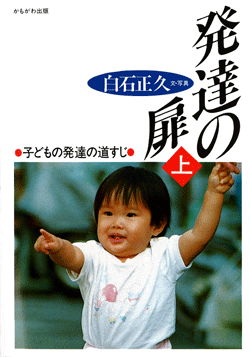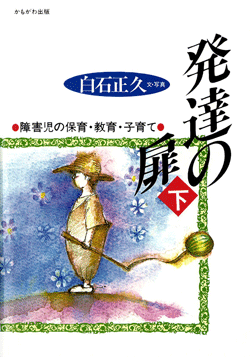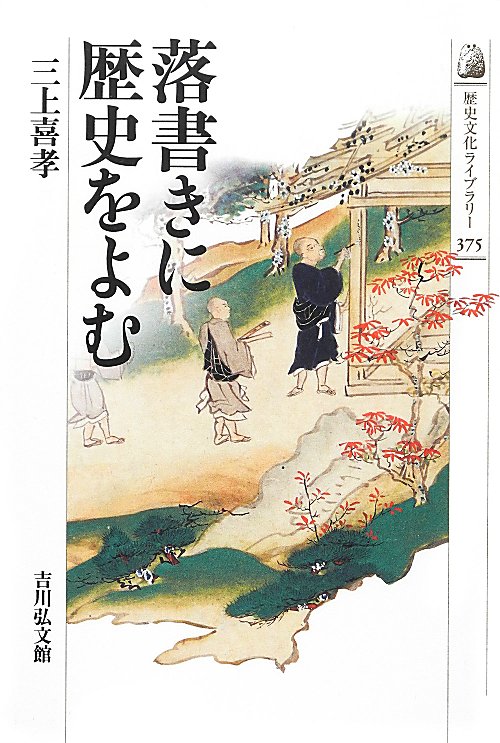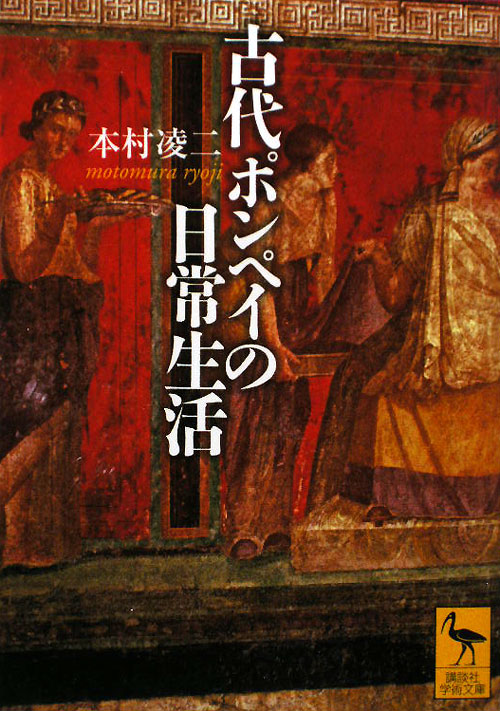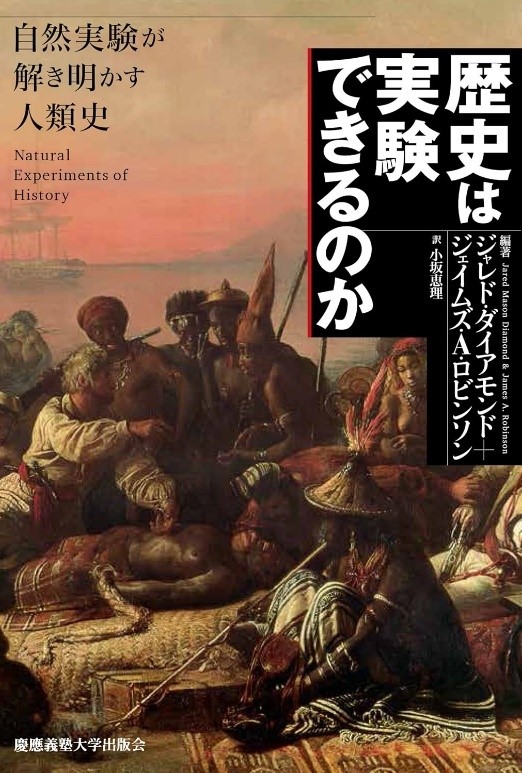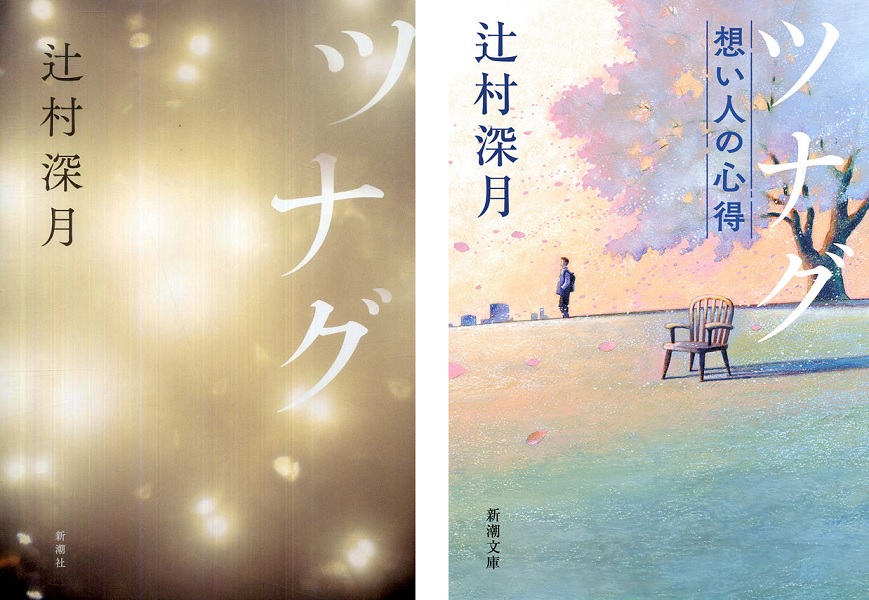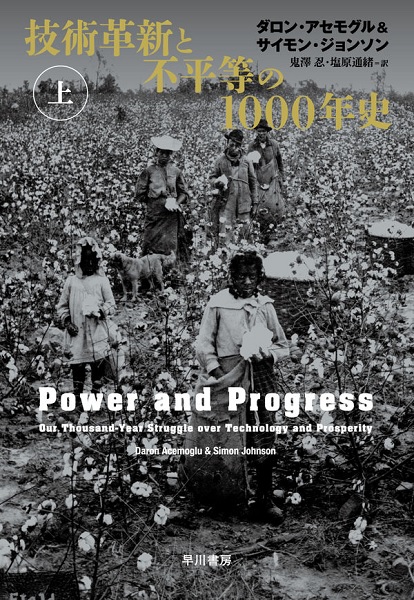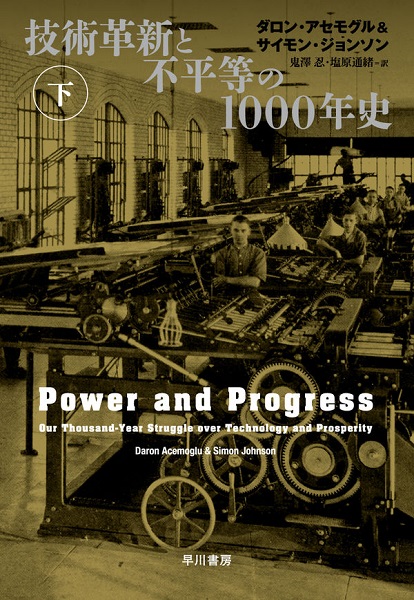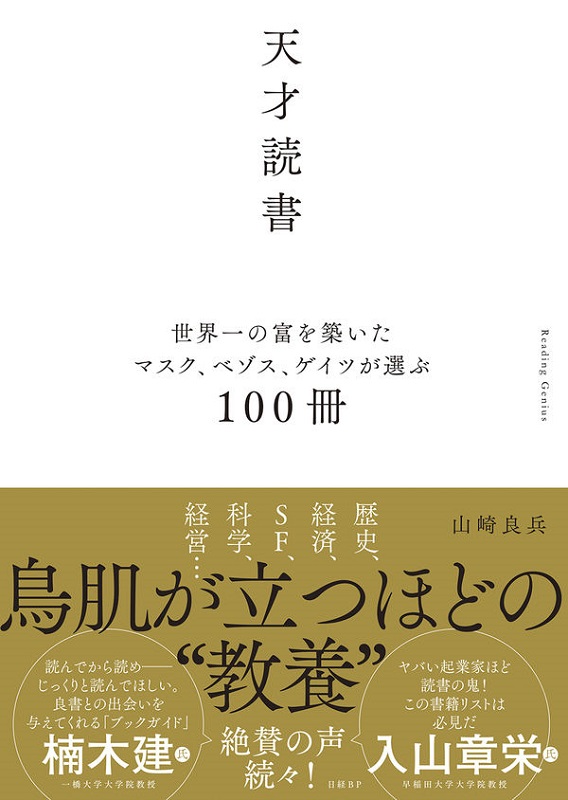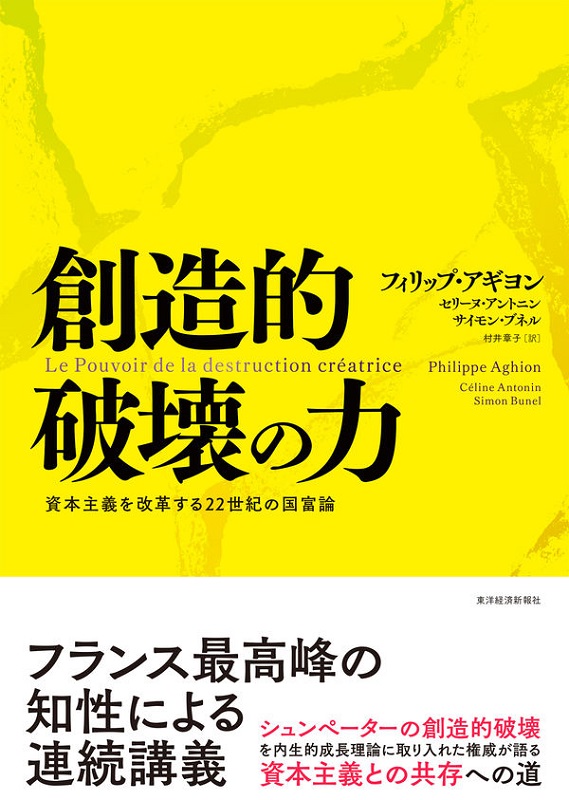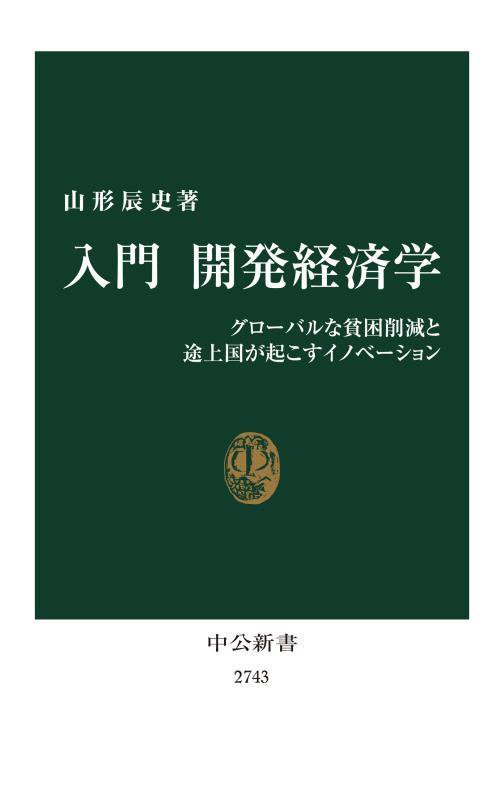在校生のみなさん、2025年、新しいスタートを切られているでしょうか。
私は今学期、西宮キャンパスで開発経済学を教えています。どうすれば経済は成長するのか、どうすれば発展途上国で生活する貧しい方々の生活を豊かにできるのか。こうしたことを、既存研究から得た理論を学び、実際のデータを確認することで、理解していこうとしています。日本を筆頭に、先進国にも貧しかった時代はあり、ここまで成長できたのだから、政府が実施した政策と、人や企業が行ったことのなかに、成長を促す要因があったはず。この講義は、経済成長という側面から、歴史を形作る要因を探る旅をしているようなものかもしれません。
そこで、私がおすすめしたい本を紹介します。
歴史は実験できるのか:自然実験が解き明かす人類史 ここでいう自然実験とは、社会制度や歴史的に偶然起こった出来事をあたかも原因であるかのようにとらえ、その後の社会をどう変えたのか、データを用いて因果関係を明らかにすることです。フランス革命軍とナポレオンがドイツに侵攻したことは、その後のドイツの都市化と経済にどう影響を与えたのか?イギリスが植民地インドの統治時代に採用した制度は、現在に至るインドのインフラや教育水準を上げたのか?この本では、各章の著者が上述のような異なるテーマで自然実験の手法を用いており、読み応えのあるものです。
さらに驚くべきは、先ほどのフランス革命のテーマが2024年ノーベル経済学賞を受賞した3名の教授(Daron Acemoglu & Simon Johnson* (Massachusetts Institute of Technology) James A. Robinson (University of Chicago))による執筆であり、インドのテーマが2019年ノーベル経済学賞を受賞した3名の教授のうちのひとり(Abhijit Banerjee (Massachusetts Institute of Technology))であることです。授賞理由は、国家の繁栄に影響を与える制度の役割(2024年)やフィールド実験を用いた途上国における貧困解消に向けた効果的な政策(2019年)を検証したことにあります。いずれも開発経済学の主要テーマであり、「人々の選択こそが世の中を変える」ことを示しています。
フランス革命という偶然によって既存の制度が崩壊し、侵攻先のドイツにもこの波が押し寄せてきている状況は、外圧に悩む現在の多くの国にも起こりうることを示唆しています。さらに、こうした制度変更を柔軟に受け止め対応した地域こそが、同時期に来ていた産業革命の波をもうまく乗りこなし競争力を高めうるとの視点は、国の選択が長期的な我々の暮らしの行方を決めうるのだと教えてくれます。歴史から学ぶことは、歴史学者だけの仕事ではないのだと、経済学を専攻する私にも多くの刺激を与えてくれました。
本書「プロローグ」最後の段落には、こうした最高峰の経済学者が、編者から依頼された修正にも常に協力的だったこと、自然実験にもろ手をあげて賛成ではないはずの伝統的歴史学者にも目を通してもらったことが綴られています。圧倒的な知性と驚きのアイデアをもつ先生方が、謙虚さをもって、専攻する学問分野が違う研究者に真摯な姿勢で向き合っているとは!本書の意図とは全く関係ありませんが、私の一番の感激どころ、だったのでした。
世の中が混沌としていても、打開できるのは我々の意志と選択。よりよい選択をするために、みなさん、図書館で様々な本に触れ、いい出会いをしてください。
* ご興味があればDaron Acemoglu & Simon Johnsonの近著は、前回の藤棚ONLINE(https://www.konan-u.ac.jp/lib/blog/archives/6560 )でご確認ください。
**
KONAN-PLANETに昨年末掲載された記事を読まれましたか?
「甲南大学の読書王に聞く!今年読んだおすすめの本 ベスト3(2024)」
マネジメント創造学部にはプロジェクト科目という実践的な学びが得られる授業があり、グループワークやプレゼンテーションを積極的に行っています。今学期私が担当する「開発経済‐アフリカ各国の経済成長−」プロジェクトに参加し、頑張っている学生さんの推薦本、『偶然屋』(七尾与史著)を読んでみました。
「偶然は偶然のまま、自然のままに日常を楽しむ余裕をもちたい」という意見は、ほかの学生さんの意見をしっかりと(穏やかに)聞いて、建設的な意見を追加できないか考えている、真摯な人柄から出る言葉だなと思いました。みなさんも、ご家族、お友達、先生、自分の気になる方が、何を読み、どう感じたのかを聞いて、思いもしなかった新たな本と出会ってみませんか?
今年も、心に残る本との出会いがありますように。