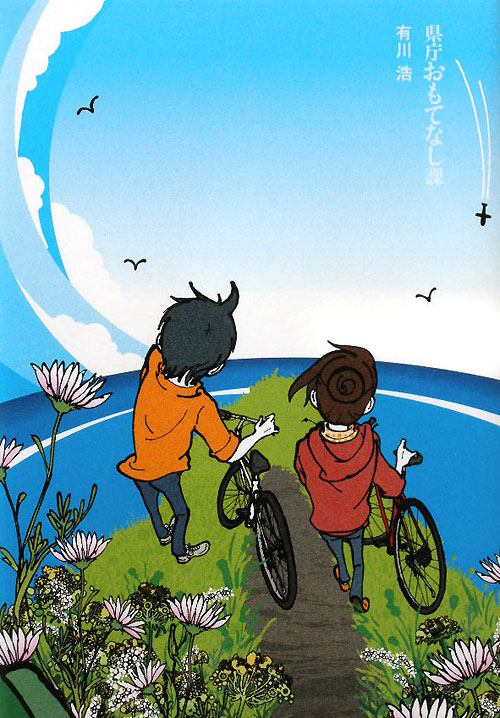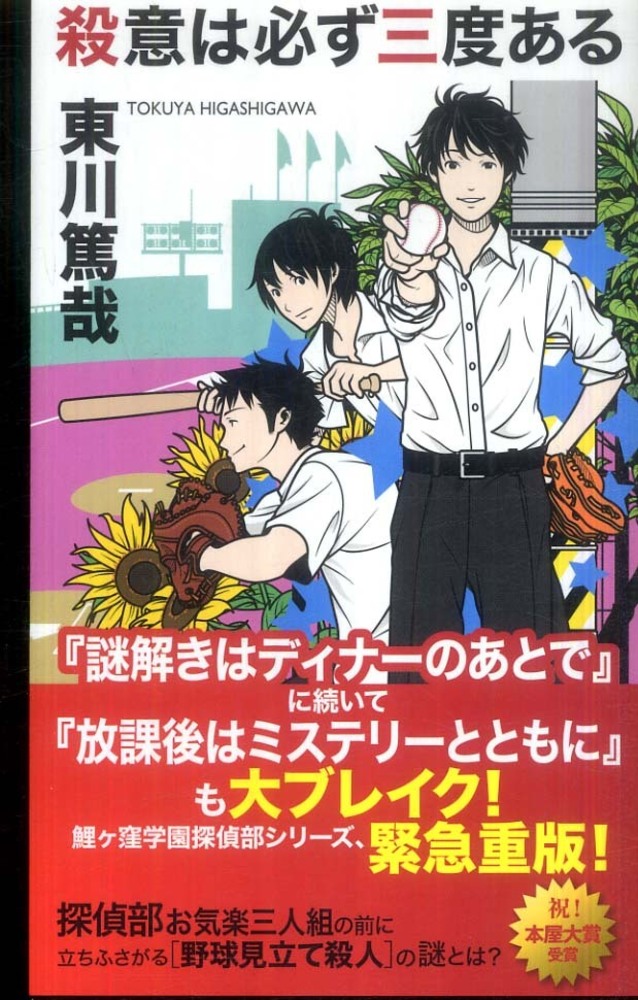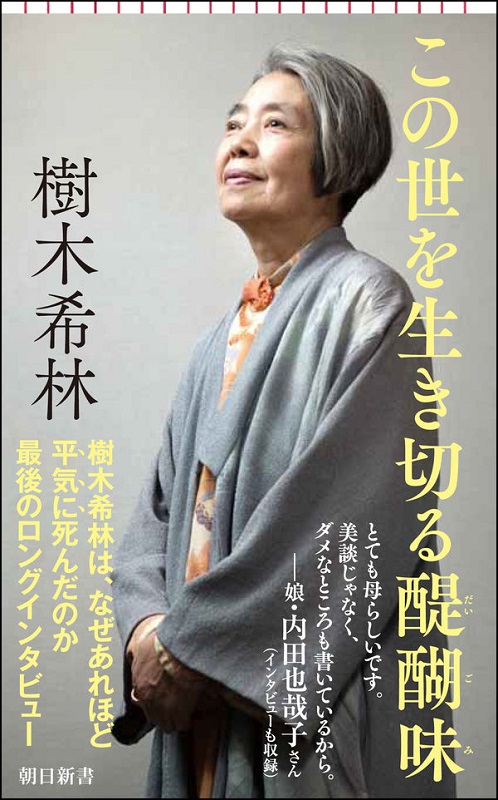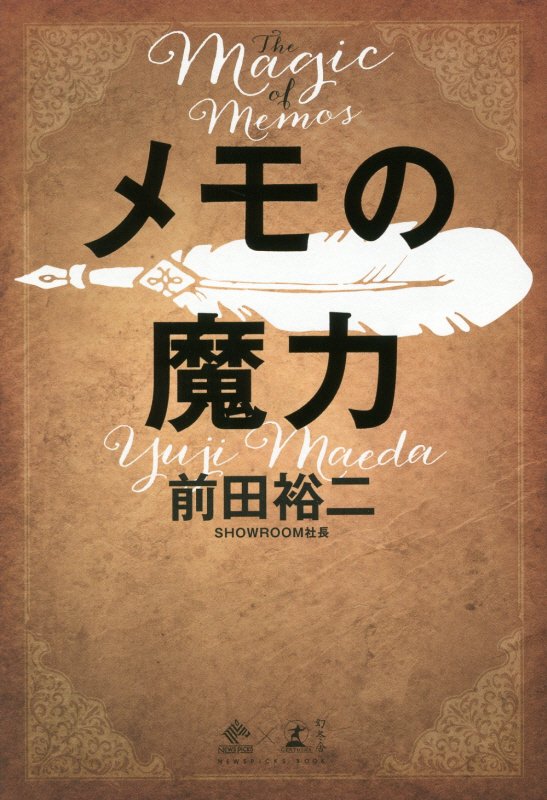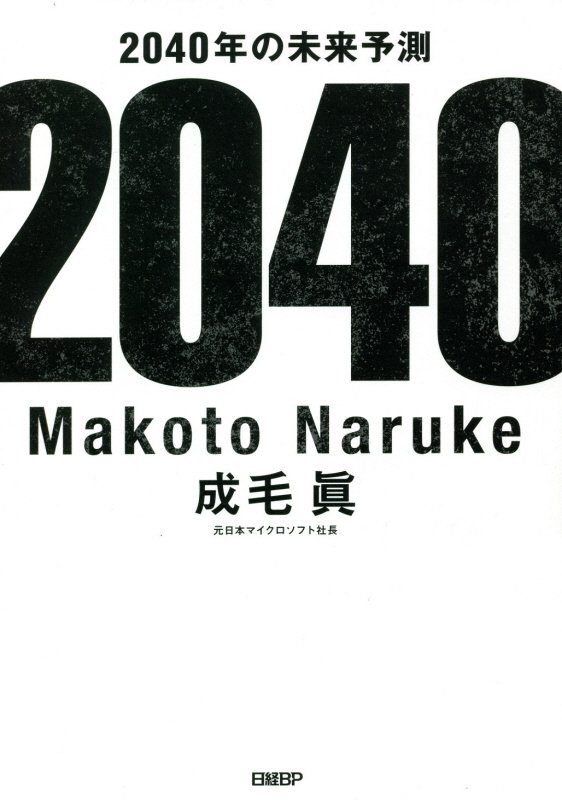図書館報『藤棚ONLINE』
全学共通教育センター・山本貴揚先生コラム
僕は、法律学という、現実社会を対象とした学問をやっていますが、10年ほど前のことだったでしょうか、懇意にしている洋品店で立ち話をしていた相手(他の客)から、「あなたはあの世とこの世の間にいる人です」と言われたことがあります。もちろんその時は、「何を言っているんだ、この人」と思いましたが、その言葉の影響でしょうか、今となっては、文字どおり“夢か現か”という感覚がつねに傍にある、という感じで生きています。
昨年、知人から、僕たちの住むこの三次元世界は、宇宙の彼方の二次元平面に元データがあって、そのデータが投影されたホログラムに過ぎない、というような世界(宇宙)の捉え方があることを教わりました(理系の方にはずいぶん不正確な理解だとお叱りを受けそうですが、そこは文系人間がそんな感じで理解に努めている、ということで、どうぞお許しください。よい入門書をご紹介いただけますと幸いです)。イーロン・マスクも、この世は仮想現実と考えてほぼ間違いない、という趣旨のことを言っていますが、いずれの考え方も、この世界は僕たちが考えているような実体としてそこに存在するわけではない、と捉える点では同じような考え方なのだと思います。こういった捉え方を否定する主張も存在するようですが、“夢か現か”の僕にはわりと自然に受け入れることのできる観念で、こういう話を聞くにつけ、僕の感覚は“現”よりも“夢”に近づいてしまうのです(ちょっと他人の話に影響され過ぎでしょうか・・・苦笑)。
さて、こういった世界観では、人の意識も作られている、ということまで言われているようなのですが、これにはさすがの僕も抗いたい気持ちがあります。自分はいるのかいないのか、という考えがよぎって怖くなった時には、そっと法律の本を開いて、“現実”への引き戻しをお願いする次第です。
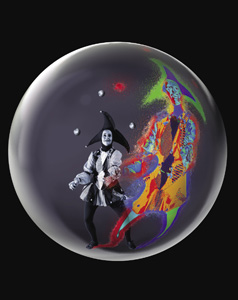
※図書館よりあわせて読みたい記事をご紹介!
「時間と空間の起源」(Nature ダイジェスト Vol.10 No.11 ※オープンアクセス)
「重力は幻なのか? ホログラフィック理論が語る宇宙」(日経サイエンス, 2006/2号, P.20〜28)
「ホログラフィック宇宙 時空の本質に迫った四半世紀」(日経サイエンス, 2023/11号, P.70〜74)
※『Natureダイジェスト』や『日経サイエンス』は、学内ネットワークに接続した端末より閲覧できます。学外から利用する場合はVPN接続をご利用ください。学外アクセスの詳細はこちら。
※甲南大学図書館HPでは電子図書館を公開しています。特に雑誌コーナーは学生向けの電子ジャーナルをすぐに閲覧できるようにピックアップしていますので、ぜひ楽しんで読んでみてください!