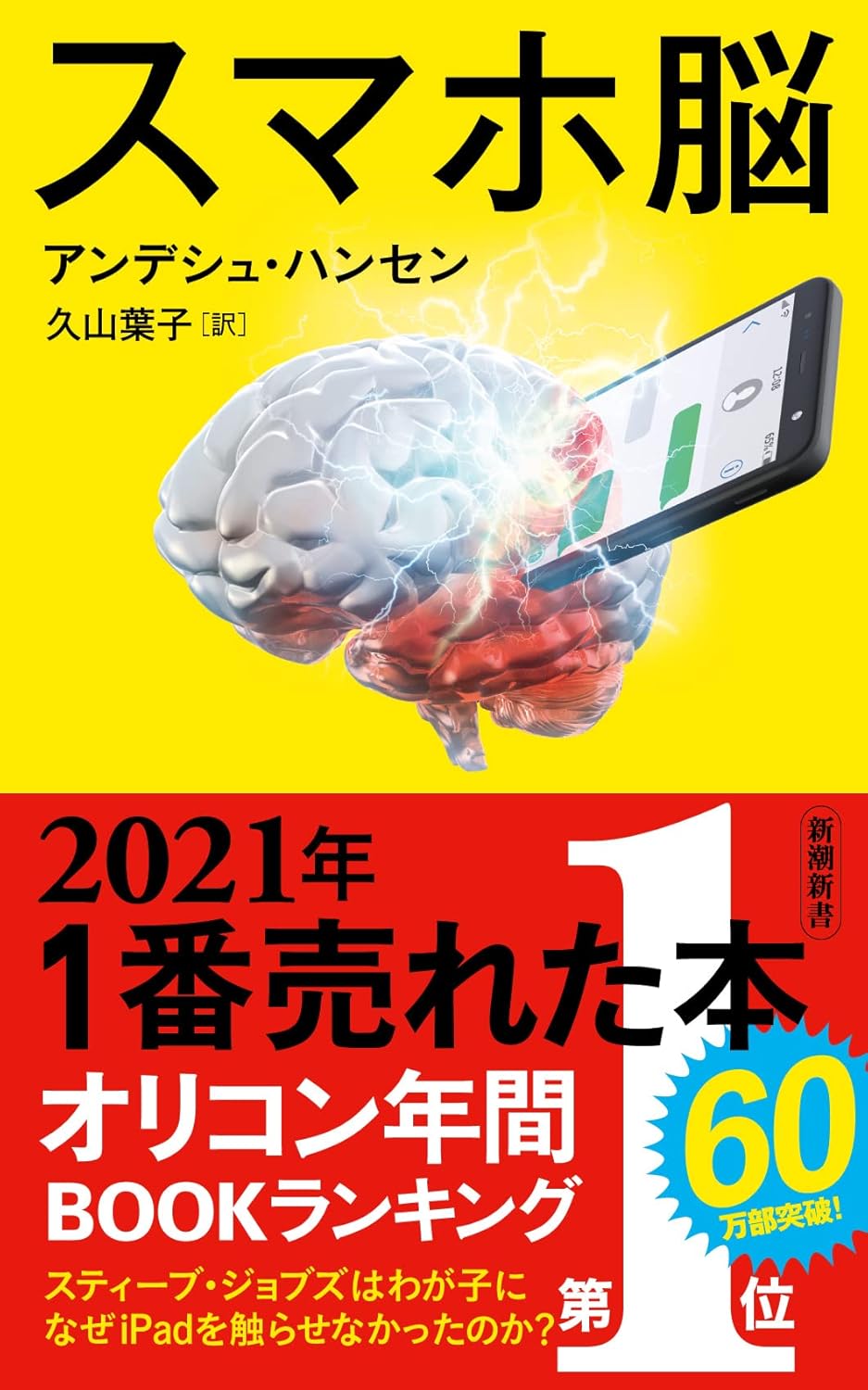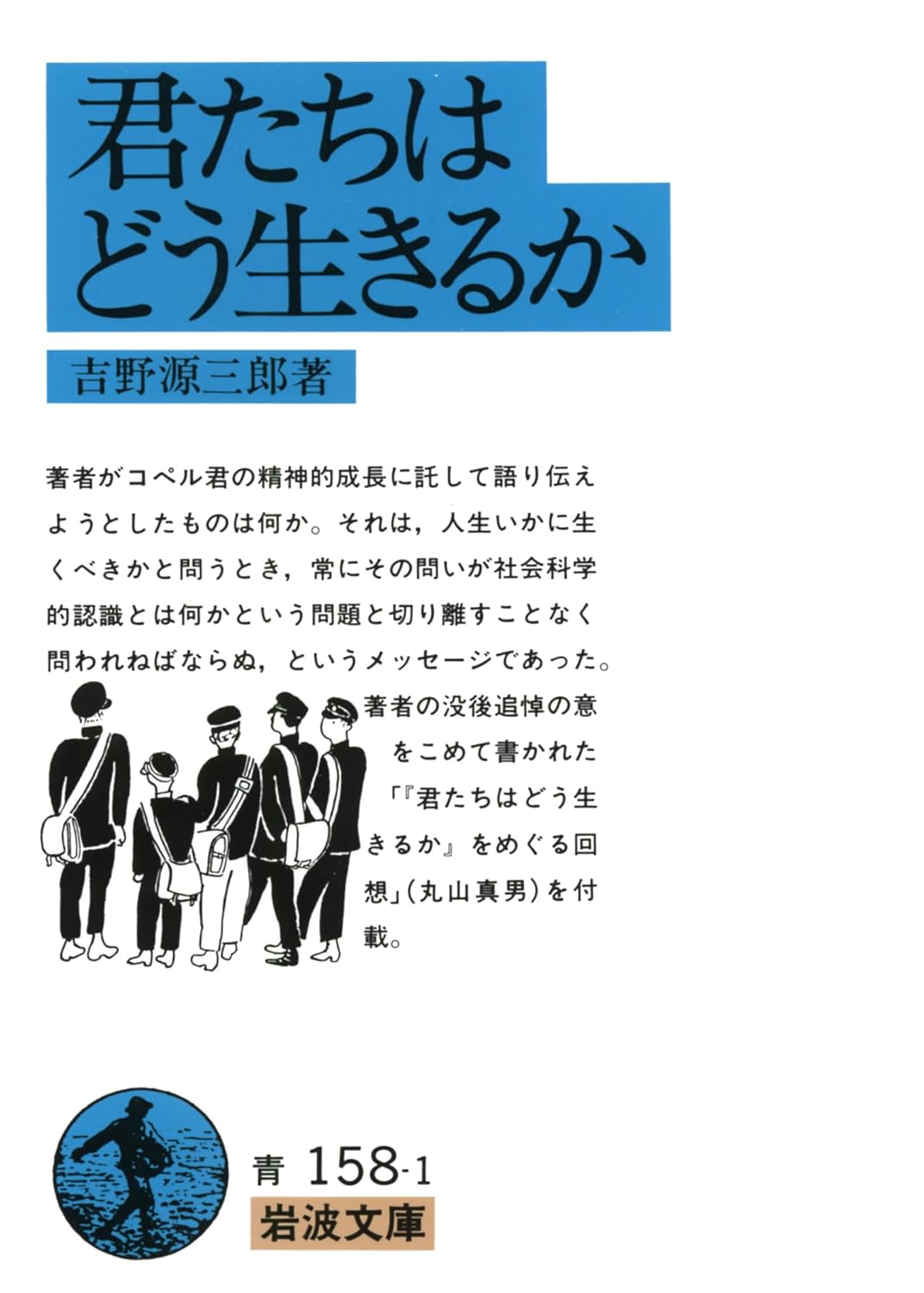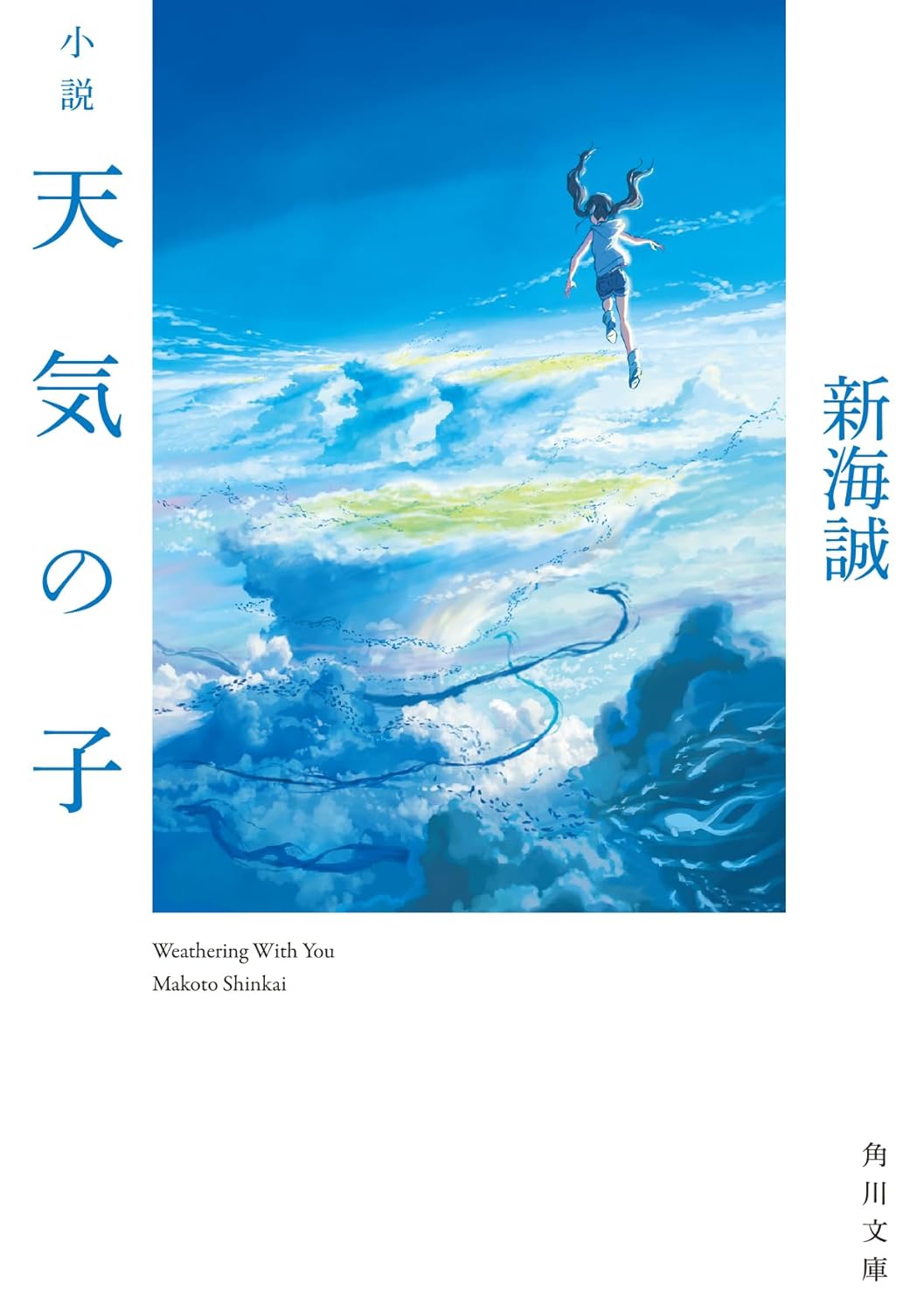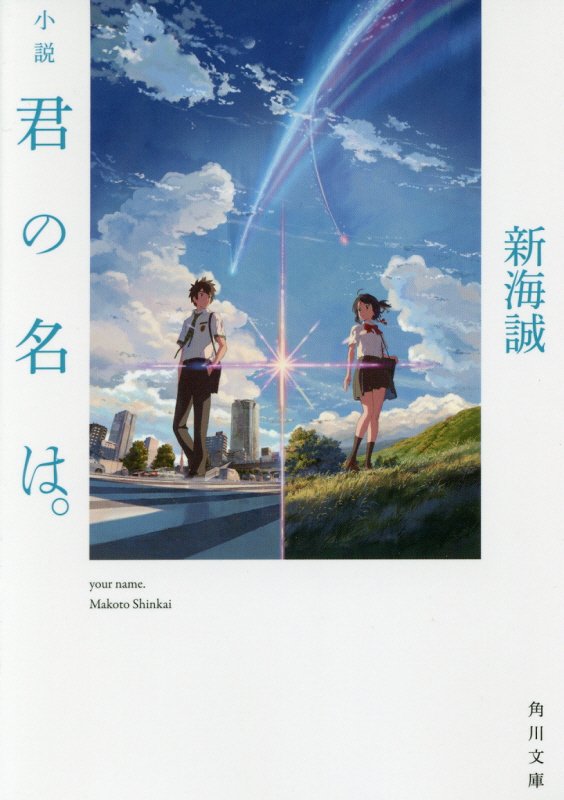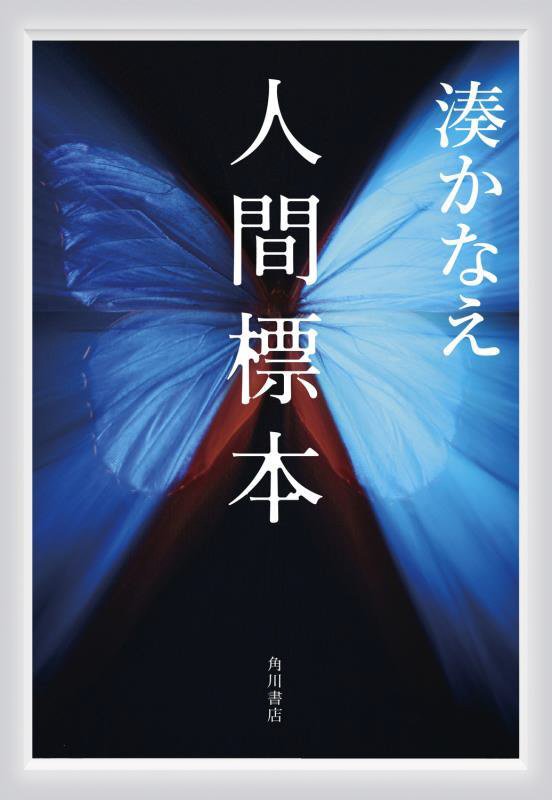知能情報学部 4年生 本田 昇太郎さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : ノルウェイの森
著者 : 村上春樹著
出版社:講談社
出版年:1987年
しばしば青春小説や恋愛小説として語られるが、読み進めるほどにそれらの枠には収まらない作品だと感じる。物語の中心にあるのは恋愛の成就でも成長の達成でもなく、「人は喪失とともにどのように生き続けてしまうのか」という、答えの出ない問いである。
物語は、ワタナベがキズキの死を回想するところから始まる。この死は、理由も説明も与えられないまま物語に置かれている。だがそれは不親切というより、現実に即した描き方だ。実際の喪失もまた、納得できる理由や意味を伴わないことがほとんどで、人は理解できないまま時間の流れに取り残される。ワタナベの淡々とした語り口は冷たさではなく、感情をどう扱えばいいのか分からない人間の誠実さを感じさせる。
直子は、その喪失を誰よりも深く抱え込んだ存在として描かれる。彼女の壊れやすさは痛々しいが、決して怠惰や弱さとして裁かれてはいない。むしろ、心が壊れてしまうことも人間の一つの現実なのだという、突き放しでも美化でもない視線がある。直子の選択は悲劇的だが、そこには「正しく生きられなかった人」への断罪はない。
一方で緑は、現実的で生命力にあふれた人物として登場する。彼女の明るさや率直さは物語に風通しの良さを与えるが、それは無条件の強さではない。彼女もまた孤独を抱え、必死に生にしがみついている存在だ。直子と緑は単なる対照ではなく、どちらも「生き方の可能性」であり、優劣をつけられるものではない。
ワタナベ自身は優しく、誠実であろうとするが、誰かを救えるほど強い人間ではない。その曖昧さや中途半端さは批判されがちだが、他者の人生を完全に引き受けられないという点で、極めて現実的な存在だと思う。彼は選び続けるが、選んだ結果に確信を持つことはできない。その姿は、読者自身の姿とも重なって見える。
『ノルウェイの森』は、喪失を乗り越える物語ではない。喪失を抱えたまま、それでも生きてしまう人間の姿を描いた物語だ。だからこそ読む年齢や状況によって受け取る印象が変わり、人生の節目ごとに思い出される。読み終えたあとに残るのは救いではなく、静かな余韻と、言葉にできない感情の重さである。その不完全さこそが、この作品が長く読み継がれてきた理由なのだと思う。