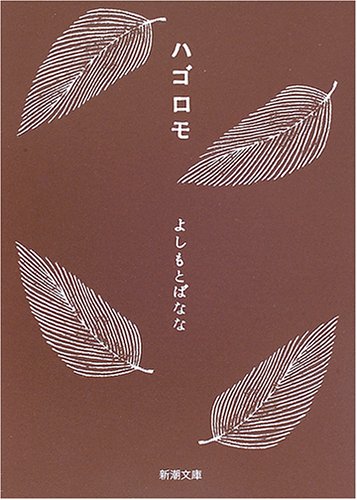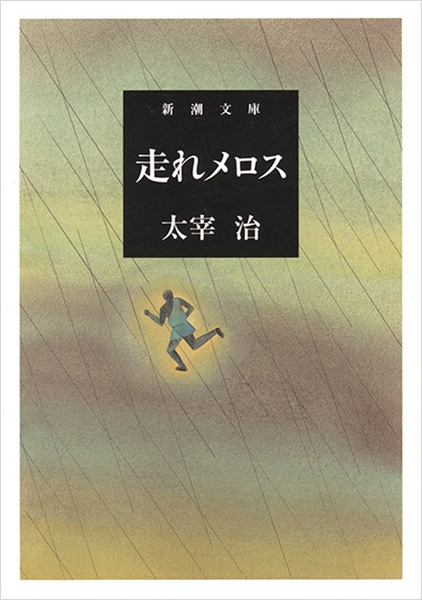知能情報学部 4年生 Yさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : わかりやすさの罠 : 池上流「知る力」の鍛え方
著者 : 池上彰
出版社:集英社
出版年:2019年
『わかりやすさの罠』は、「わかりやすく伝えること」は本当に常に善なのか、という問いを真正面から投げかける一冊である。私たちは説明や発表、文章作成の場面で「わかりやすくしなければならない」と強く求められる。しかし本書は、その姿勢が思考を浅くし、重要なものを切り捨ててしまう危険性をはらんでいることを指摘する。
著者は、わかりやすさとは情報を単純化し、整理し、即座に理解できる形に変換する行為だと述べる。一見すると親切だが、その過程で本来の複雑さや曖昧さ、考える余地が失われてしまう。特に、答えが一つではない問題や、時間をかけて考える価値のあるテーマほど、「わかりやすさ」を優先することで誤解や思考停止を招きやすい。
印象的なのは、「わからなさ」には意味があるという主張である。すぐに理解できないからこそ人は考え、問いを立て、他者と議論する。本書は、わからなさを排除するのではなく、耐え、向き合うことが知的成長につながると教えてくれる。この視点は、効率や即答が重視される現代社会への強いアンチテーゼとなっている。
一方で本書は、わかりやすさそのものを否定しているわけではない。問題は、目的や文脈を無視して「わかりやすさ」だけを絶対視する態度にある。伝える側も受け取る側も、簡単に理解できたという満足感に安住せず、その裏で何が省かれているのかを意識する必要がある。
『わかりやすさの罠』は、情報が溢れる時代において、考える力を取り戻すための重要な示唆を与えてくれる一冊であり、学ぶ立場にある人だけでなく、教える・伝える立場の人にも強く薦めたい。