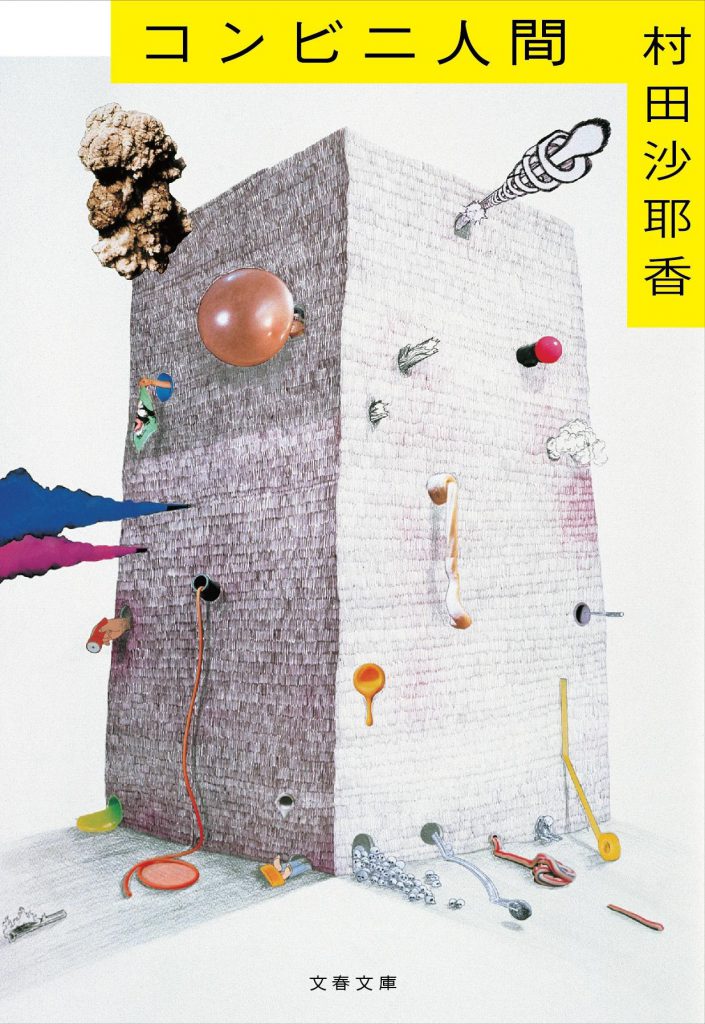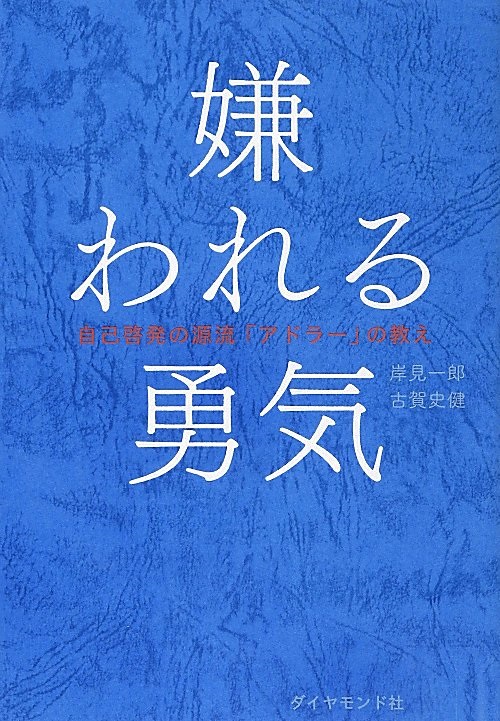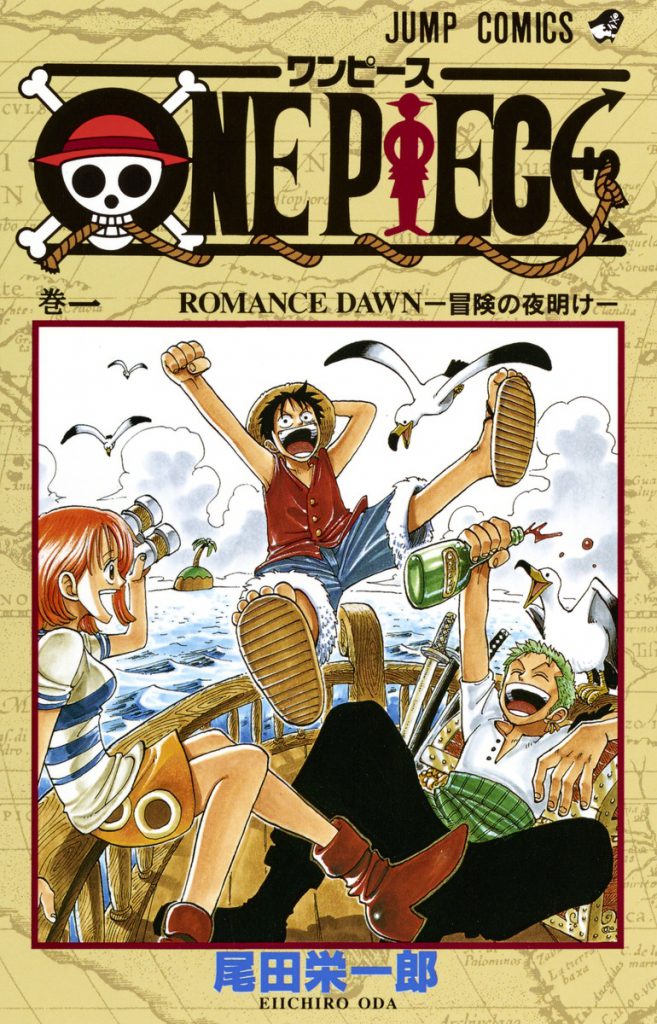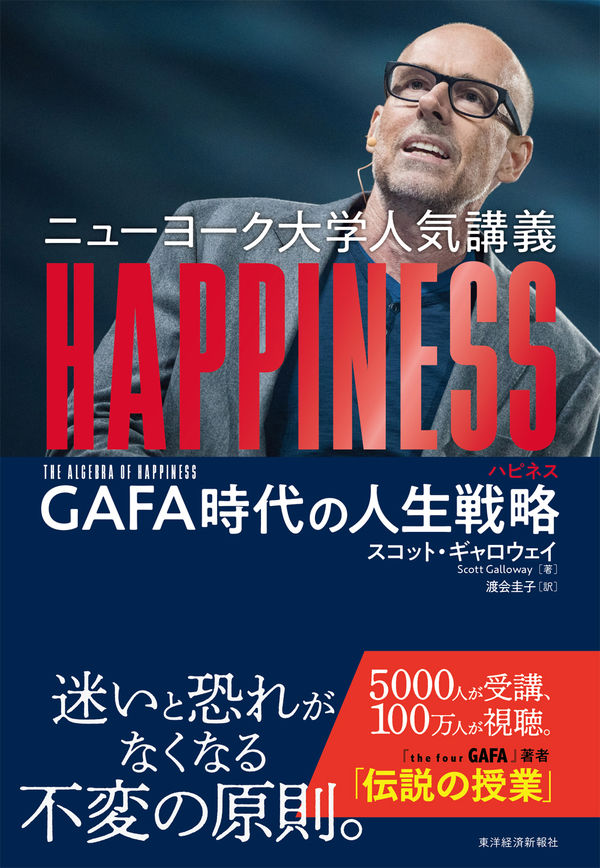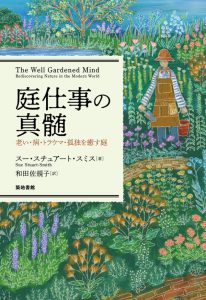10月27日(木)に開催された第5回 甲南大学書評対決(主催:甲南大学生活協同組合)で紹介された本です。
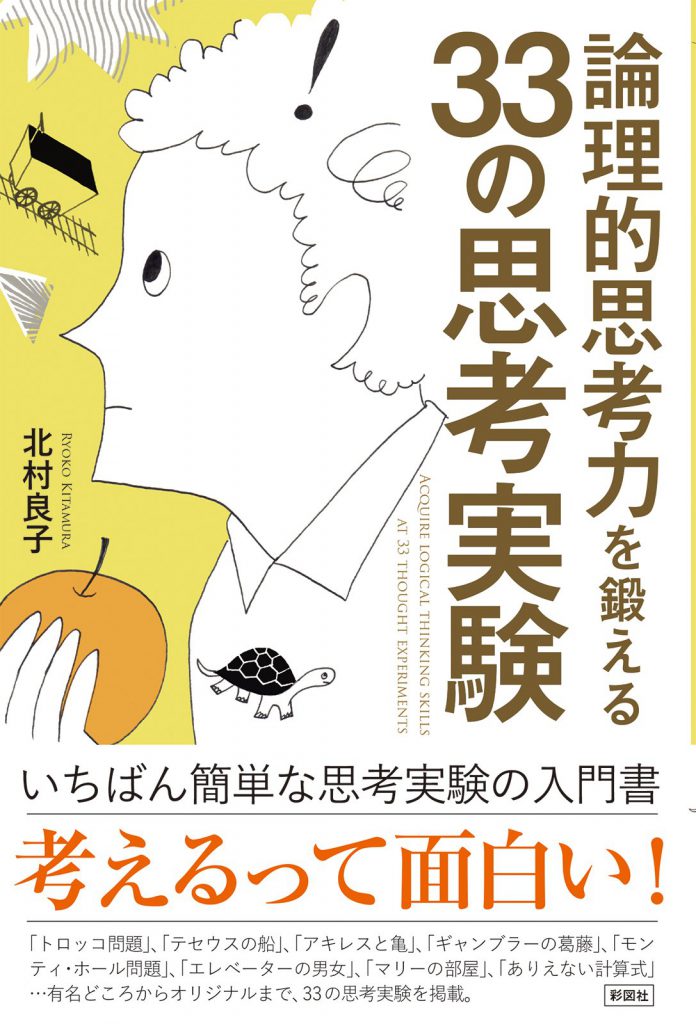
ラーニングアシスタントチーム 経営学部3年 地引 愛里子さんからのおすすめ本です。
書名 : 論理的思考力を鍛える33の思考実験
著者 : 北村 良子
出版社: 彩図社
出版年:2017年
論理的思考 (ロジカルシンキング)とは、物事を筋が通るように考え整理し、矛盾などがないように結論を導き出すことです。 この本ではそんな論理的思考力が鍛えられるような実験が簡単なイラストと共に掲載されており、読めばきっとあなたも考えることの楽しさに目覚めるはず!
ご存じの方も多いであろうトロッコ問題をはじめとする33の実験は4つのカテゴリー「倫理観を揺さぶる思考実験」「矛盾が絡みつくパラドックス」「数字と現実の不一致を味わう思考実験」「不条理な世の中を生き抜くための思考実験」に分けられています。どの実験でも自分が今までに得た知識や集中力が試されるので、脳を鍛えながらも改めて自分を見つめるきっかけにもなるかもしれません。
私はこの本を父から譲り受けました。親子喧嘩中の父の意見はいつでも筋が通っていて、私が反論しても全て論破されるのがとても悔しかったです。そんな時何も言わずに父からこの本を差し出され読み進めていくと、自分がいかに結論以外見ていない隙だらけの思考をしていたかに気付かされました。自信家だった私には結構大きなショックです。 その後何度もこの本を読み、今ではようやく父と同じ土俵で戦うことができるようになりました。他にも、論理的思考はゼミでの研究やレポートを書くときに必ず役立つし、説得力が加わることで意見や文章の質がぐっと上がると思います。良い子の皆さんはこの本で鍛えられる論理的思考力を親への口答えに使わず、これから先のビジネスシーンなどでぜひ役立ててください。