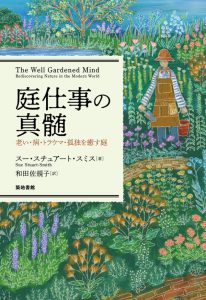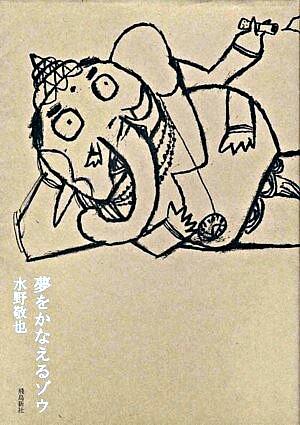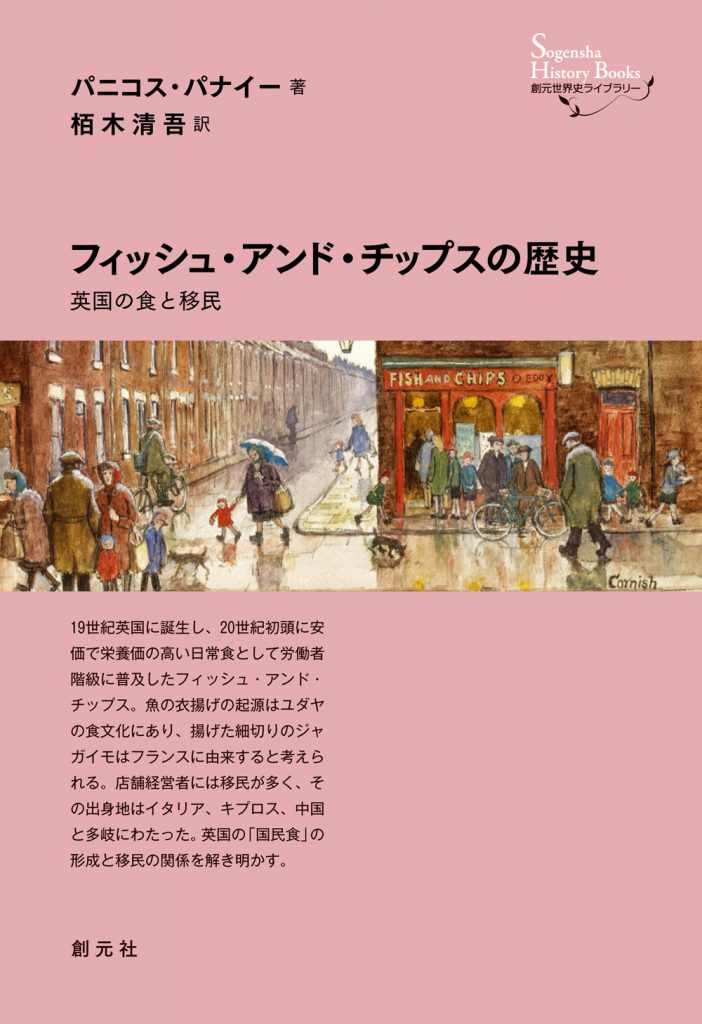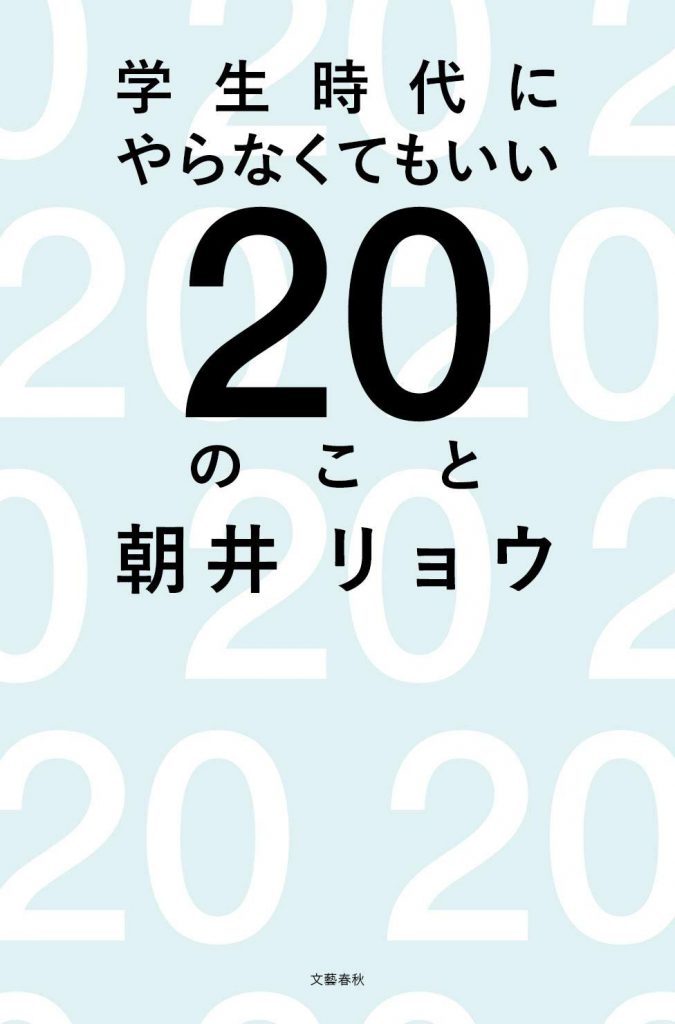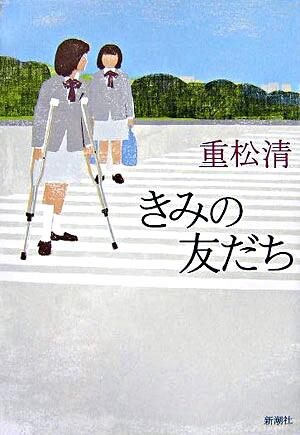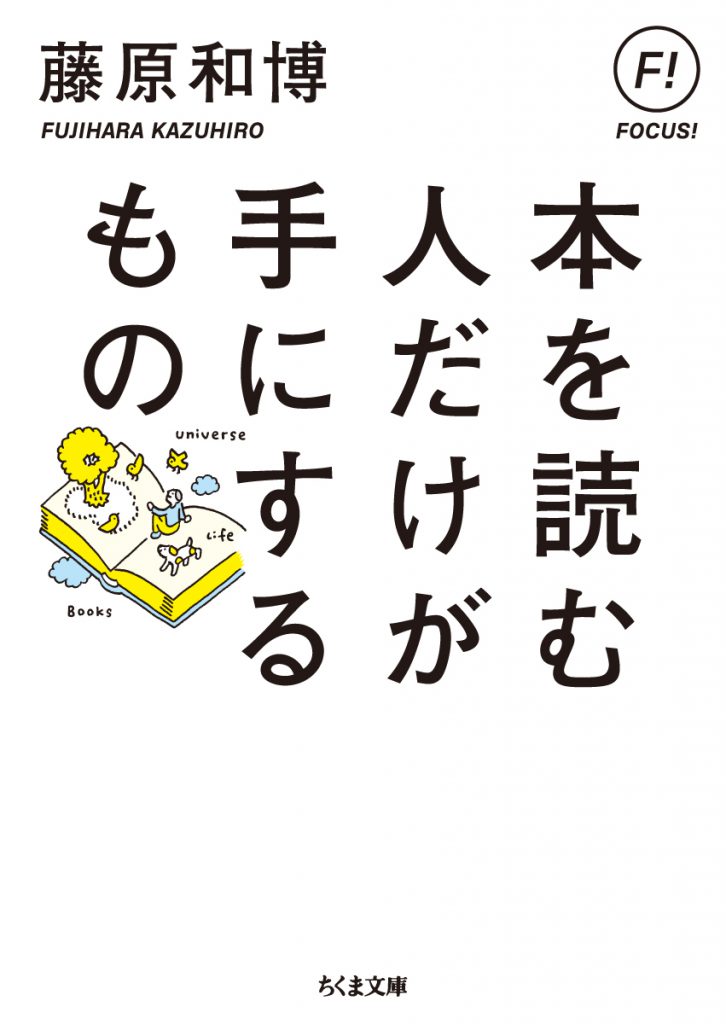文学部 4年生 Iさんからのおすすめ本です。
書名 : 庭仕事の真髄 : 老い・病・トラウマ・孤独を癒す庭
著者 : スー・スチュアート・スミス著 和田佐規子訳
出版社:築地書館
出版年:2021年
皆さんは、最近自然と触れ合うことはあるだろうか。
本書は、ガーデニングを通して自分の気持ちや心を癒していく人々の姿を描いた物語である。イギリスでは、「サンデータイムズ」ベストセラーや、タイムズ紙、オブザーバー紙の「今年読むべき1冊2020年」に選出された1冊である。
戦争で負った心の傷をガーデニングで癒したという祖父や、ガーデンデザイナーである夫から影響を受け、著者は精神科医でありながらガーデニングに熱中する。そこから、自然やガーデニングを用いた治療法を試していく。患者は、心の病気を患う人や、虐待を受けた経験がある人、罪を犯した人、復員兵士など様々なバックグラウンドを持つ人々である。彼らは野菜や花を育て、それらを手入れする過程で、自分自身と向き合い、感情をコントロールしていく。本書からは、自然が持つ治癒力のすごさを学ぶことが出来る。
本書では、現代人が、生活で自然や人と触れ合う機会が少ないことについても触れている。実際、コロナ禍で、デジタル化がより進み、オンライン授業やテレワークなど、外に出ることや、直接人と触れ合うことがなくても成り立つことが増えている。私たちはその便利さと引き換えに、大切な何かを失ってはいないだろうか。スマートフォンやパソコンといった無機質なものに囲まれ、現実を見失ってはいないだろうか。
本書は、現代人が、野菜や花、木などの生命と直接触れ合うことが大切だと記している。植物が育ち、枯れ、また成長していく姿からは、生命の大切さを感じることが出来るからだ。そして、自分自身も自然の一部だということに気付き、自分自身の生命や感情、思いも大切にできるようになると述べている。
ガーデニングは時間が経つのを忘れさせてくれると本書で書かれているように、約300ページある本書も時間を忘れて読むことが出来る。デジタル化が進んだ今、自然と触れ合う大切さを気付かせてくれる一冊である。