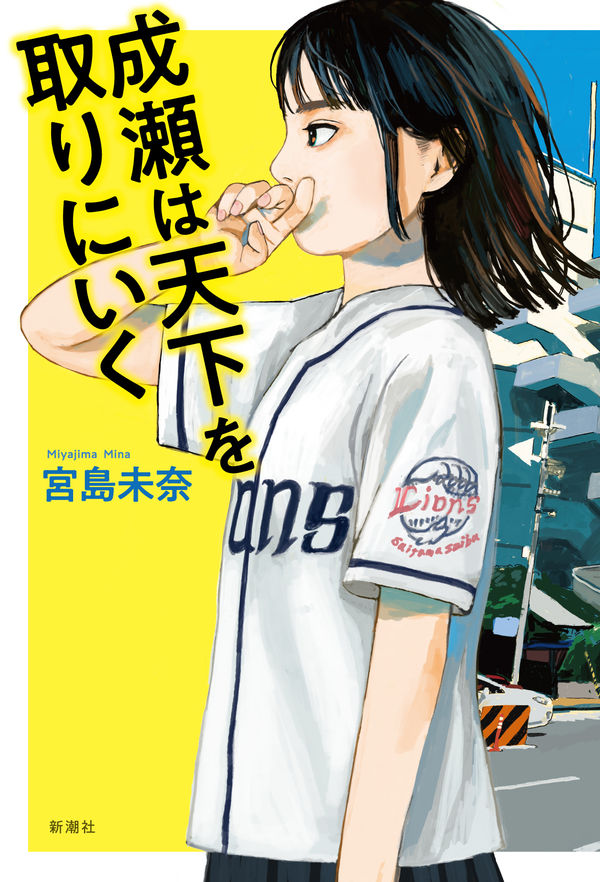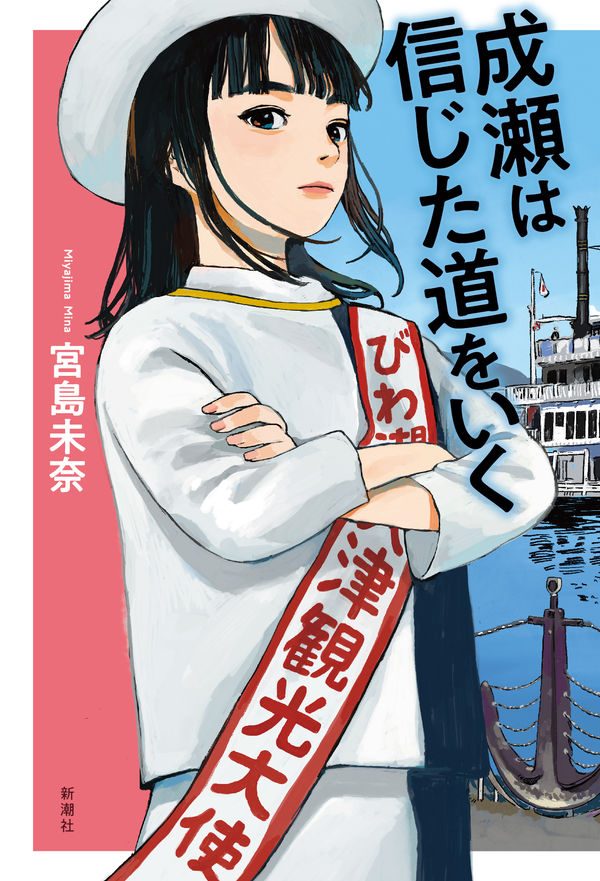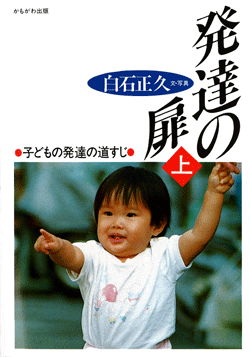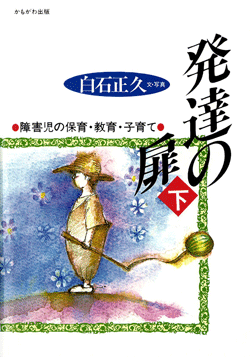図書館報『藤棚ONLINE』
甲南大学法学部教授(商法) 山本真知子先生より
*オランダの人文主義者、デシデリウス・エラスムス(1469年-1536年)が「あなたの図書館はあなたの楽園である。」(“Your library is your paradise.”)と言ったとされています。
【325 商法. 商事法】
325は、商法研究者が生涯で何度となく見る数字です。日本の図書館の本は、「日本十進分類法」(にほんじっしんぶんるいほう)に従って、分野ごとにまとめられていて、商法(会社法)は325に分類されているからです。
「日本十進分類法」とは、日本の図書館で使われている分類法です。英語名(Nippon Decimal Classification)の頭文字をとって「NDC」と呼ばれることもあります。森清(1906年-1990年)が考案し、1929年に刊行されました。100年近くにわたって使われていますが、時代の変化に合わせて、日本図書館協会分類委員会によるアップデートもされています。現在(2025年)は、新訂10版(2014年12月刊行)が最新版です。「十進法」を使って0から9までの10の数字を基本とし、10倍しながら桁数を増やしていき、0~9のそれぞれを1~9と0に区分すると、00~99の100に区分でき、さらにそれぞれをまた1~9と0に区分すると、000~999の1000に区分することができます。必要に応じてさらに細かく分類することもあります。
実際に、10の第1次区分(類目)、0、1、2、3、4、5、6、7、8、9があり、その1つである3が社会科学となっています。3は10の第2次区分(綱目)に分けられ、その1つが32法律です。32がさらに10の第3次区分(細目)に分類されていて、その1つの325に商法(会社法)があるということになります。
冊子体のものが入学前後のガイダンスなどで配られたり、図書館にも置いてあったりする、甲南大学図書館「情報探索ガイド2025年度版」にも「NDC日本十進分類法」についての記載があります。図書館の1階に000から599までの本があり、2階に600から999までの本があります。学生の皆さんも、学部・学科等によってそれぞれ親しみのある番号があるのではないでしょうか。
【0 総記】
「日本十進分類法」では、第1区分の0に全体にかかわる総合的な本を分類することになっていて、「総記」と呼ばれています。0にも、03(百科事典. 用語索引)や08(叢書. 全集. 選集)などの第2区分、さらに第3区分等があります。司書教諭(学校図書館法5条)のある人が、この「総記」の0の存在が素晴らしいという趣旨のことを言っていました。これにより、各分野の分類が整うというのです。
【図書館は「楽園」か?】
図書館には、様々な分野の書籍が所蔵されています。専門の番号の書籍を読み進めるとともに、100から999の数字のなかの普段は手に取らない分野の書籍も読んでみると、世界が多面的に見えてくるかもしれません。その際にも、「総記」の「0」にある百科事典などは有益です。読む本に迷ったら、同じく0の「02図書.書誌学」の中に「本を紹介する本」があります。他の図書館を訪ねてみたければ、日本の図書館、世界の図書館を紹介する本など、図書館についての本も0の中の「01 図書館. 図書館情報学」でみつけることができます。
0をガイドに、様々な番号への知的な旅を可能にする場所が「図書館」であり、誰かにとっては「楽園」であるのかもしれません。
*しかし、実際には、エラスムスからジョン・フィッシャー(ロチェスター司教)宛ての書簡の中に「あなたがどれだけ際限なくその図書館にいようとも、私にとって全く不思議ではない。図書館はあなたにとって楽園である。私自身にとっては、そのような場所に3時間もいたら気分が悪くなってしまうだろう。」(”It is no secret to me how unremitting you are in the library, which for you is Paradise.” ”As for myself, if I stayed three hours in such place, I would be sick.”)との記述があり、少しニュアンスが異なっています。海に近いかの地の気候とそこにある四方をガラス窓に囲まれた図書館(室)がエラスムスの好みではなかったようです。
【甲南大学図書館で借りられる参考文献等】
<NDC・325・0>
・甲南大学図書館「情報探索ガイド2025年度版」
(https://www.konan-u.ac.jp/lib/?page_id=245)
・公益社団法人日本図書館協会「日本十進分類法(NDC)」(https://www.jla.or.jp/ndc/)
・小林康隆編著『NDCの手引き:「日本十進分類法」新訂10版入門』(日本図書協会、2017年)(014.4//2009)
・宮沢厚雄『分類法キイノート:日本十進分類法[新訂10版]対応〔第3版補訂〕』(樹村房 , 2020年)(014.4//2011)
・伊藤靖史ほか『会社法〔第6版〕』(有斐閣、2025年)(325.2//2649)(1階シラバスコーナー)
・神田秀樹『会社法〔第27版〕』(弘文堂、2025年)(325.2//2652)
<日本・世界の「楽園」>
・新藤透編著『写真にみる日本図書館史』(日外アソシエーツ、2025年)(010.21//2040)
・立野井一恵『新しい、美しい日本の図書館』(エクスナレッジ、2024年)(010.21//2037)
・株式会社楽園計画編『図書館が街を創る。:「武雄市図書館」という挑戦』(ネコ・パブリッシング、2013年)(016.219//2001)
・立田慶裕『世界の大学図書館:知の宝庫を訪ねて』(明石書店、2024年)(017.7//2017)
・gestalten編『世界の図書館を巡る:進化する叡智の神殿』ヤナガワ智予訳(マール社、2023年)(010.2//2022)
・アルベルト・マングェル『図書館 愛書家の楽園』野中邦子訳(白水社、2008年(新装版、2025年))(010.2//2024)
・Desiderius Erasmus and Saint John Fisher, Jean Rouschausse, Erasmus and Fisher : Their Correspondence, 1511-1524 (Librairie Philosophique J. Vrin, 1968), 83 (https://www.google.co.jp/books/edition/Erasmus_and_Fisher/o1fI1hcp8okC?hl=ja&gbpv=0)