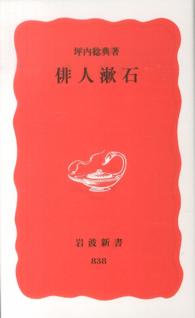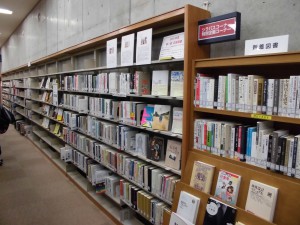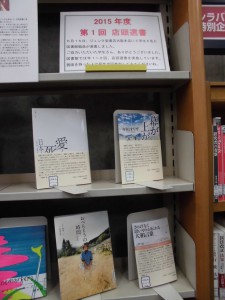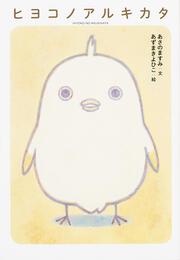文学部 4年生 川嶋健佑さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名:花修 : 曾根毅句集
著者:曾根 毅
出版社:深夜叢書社
出版年:2015年
2015年に出版されて句集のなかでも抜群に読み応えのある句集がこの花修であった。
作者の曾根さんは東日本大震災が起こったまさにその時、仙台港にいたことが付属の栞に記されている。そのこともあってか震災に関係していそうな句が目立つ。以下にその句を上げる。
薄明とセシウムを負い露草よ
桐一葉ここにもマイクロシーベルト
燃え残るプルトニウムと傘の骨
諸葛菜活断層の上にかな
句の質感としては重い。しかし、作者の伝えたいことが句の表層に現れてこないため、その質感は如何様にも解釈ができる。それは漫然と震災句として流される可能性もあるし、曾根さん自身の訴えかけのように受け止められる可能性もある。だが、ひとつとして多くを語った句はない。つまり1句ごとに俳句としての無機質さ、広い意味での客観性を維持しているのだ。それは先に挙げた句以外にも共通する。
以下に挙げる句はこの句集のなかでも個人的に抒情性を感じるものだ。
存在の時を余さず鶴帰る
かかわりのメモの散乱夕立雲
快楽以後紙のコップと死が残り
「存在の時」、「かかわりのメモ」、「快楽以後」、どのことばも抽象度が高い。この抽象度の高さが句に余白を生み、抒情へと繋がっていく気がする。以下に挙げる昭和を代表する俳人の抒情性と曾根さんの抒情性を比べると違いがはっきりする。
炎天の遠き帆やわがこころの帆 山口誓子
玫瑰や今も沖には未来あり 中村草田男
バスを待ち大路の春をうたがはず 石田波郷
これらの抒情的な句は、言い換えれば「青春性」と言ってもよいだろう。それと比べると曾根さんの句はどこか「無機質な抒情」といった感じ。もしかしたら平成の抒情とはこういったものかもしれない。
少し話はズレるが、句集は1頁に2句から4句しか載っていないものが多い。それは1句ごとに立ち止まって読んで欲しいという思いから、その形態にしているそうである。そういった意味ではこの花修は間違いなく1句ごとに立ち止まらないといけない句が並んでいる。