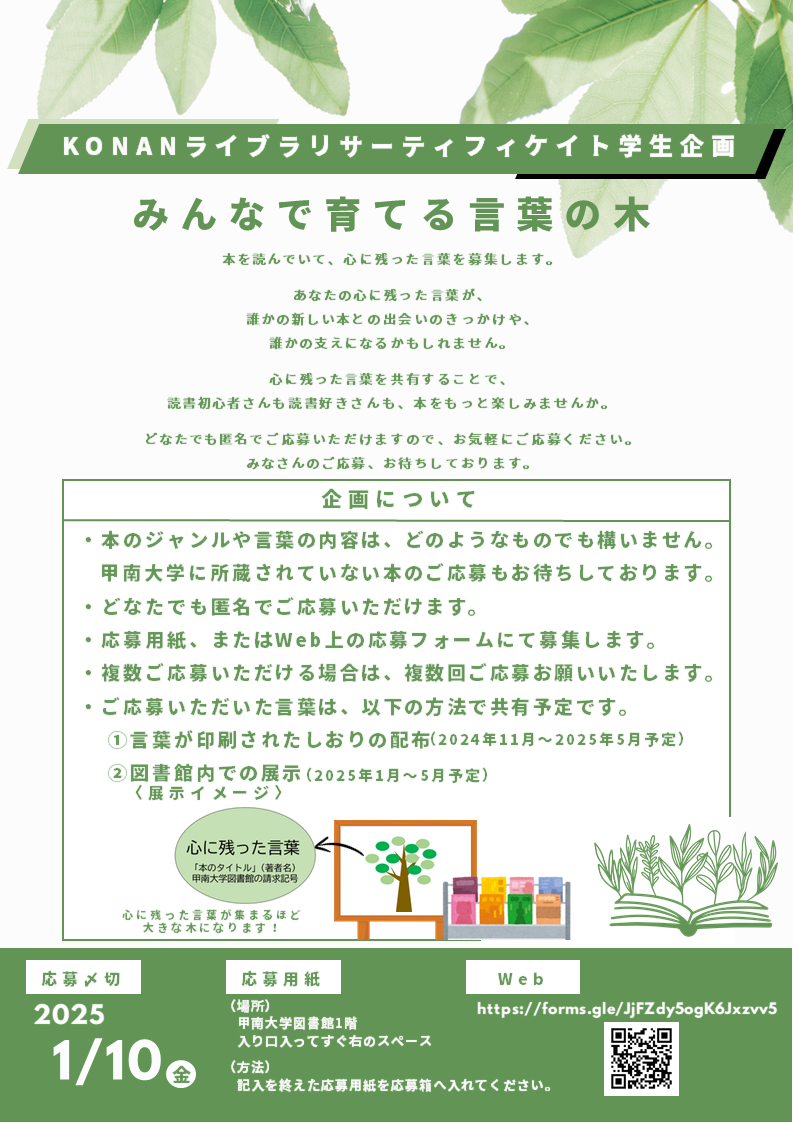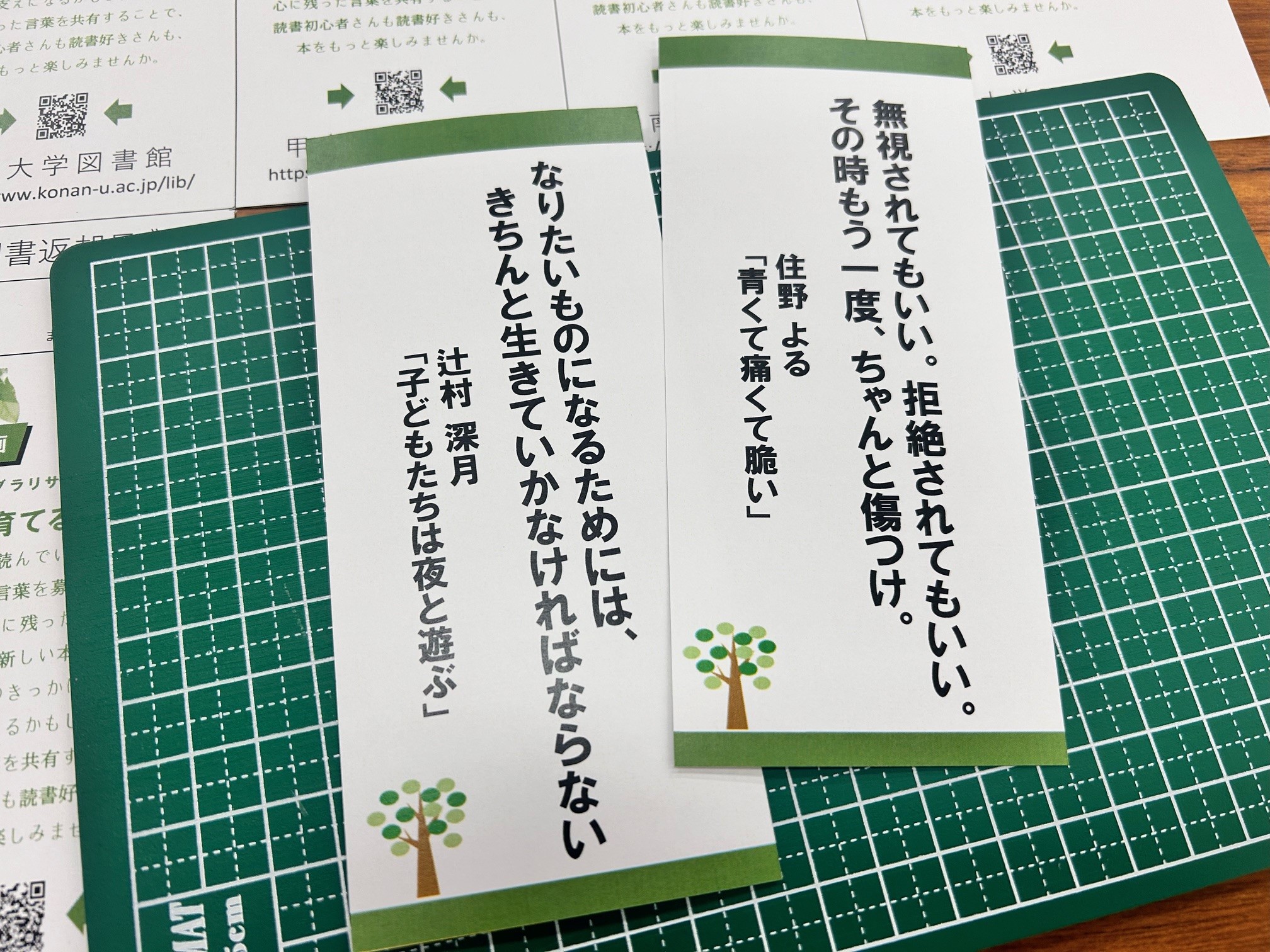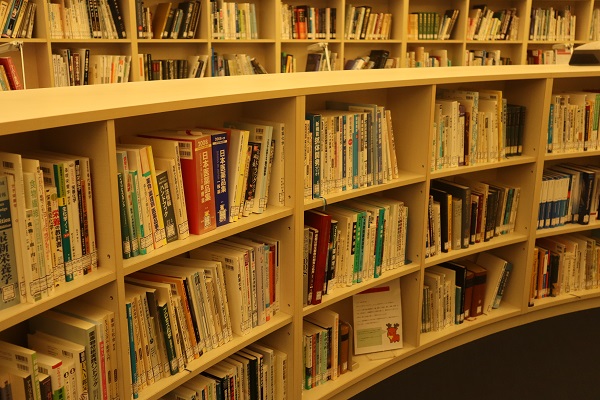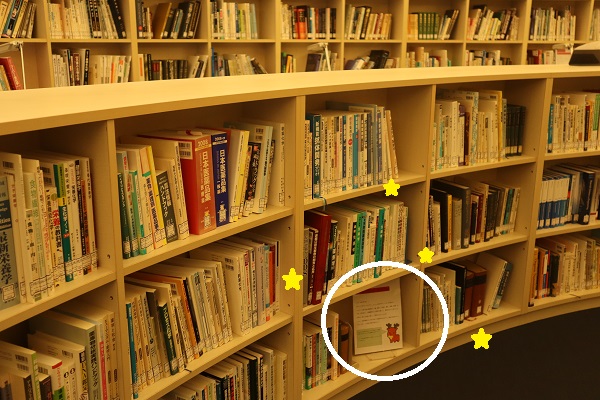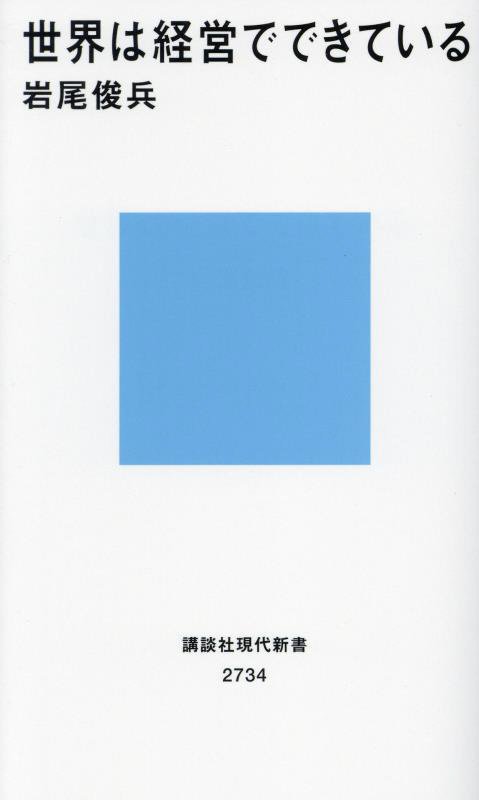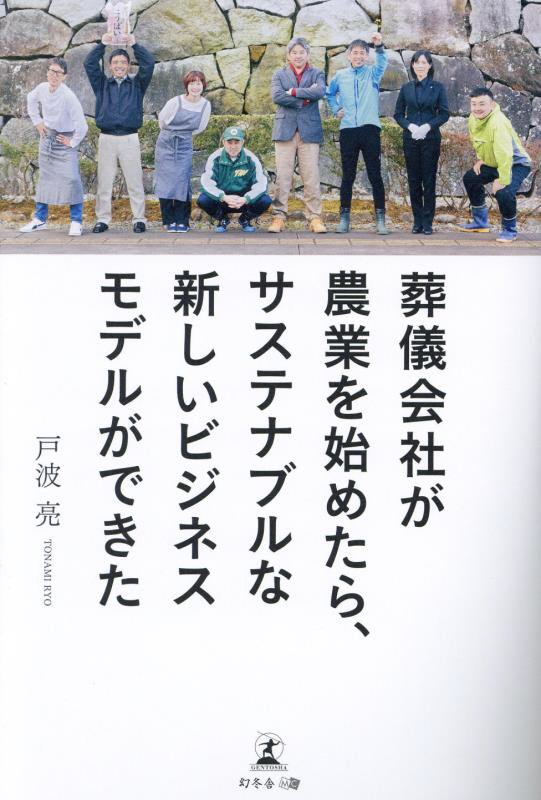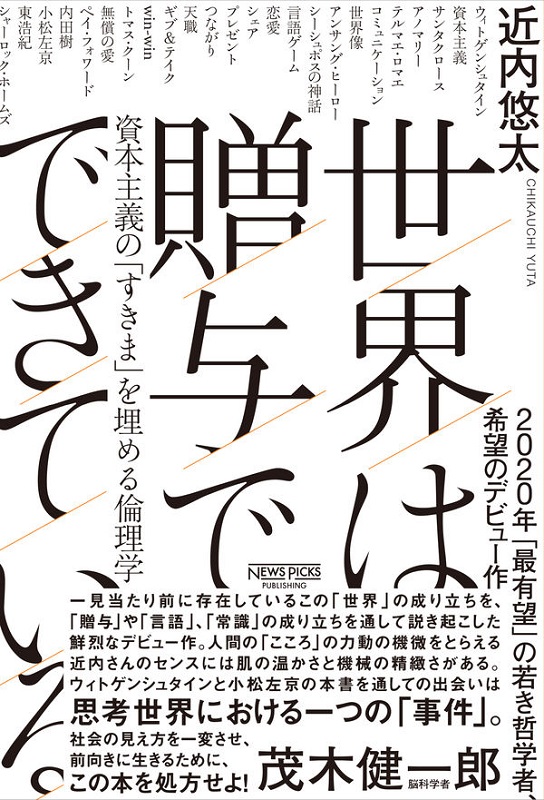KONANプレミア・プロジェクト「文学、あります」第2回「怖いものは美しい——藤野可織さん公開インタビュー」を開催
2024年11月22日(金)に作家の藤野可織さんをお招きして、「怖いものは美しい——藤野可織さん公開インタビュー」を開催しました。本イベントは、甲南大学の教員と甲南中学・高校の教員有志からなるチーム「文学、あります」と甲南大学図書館職員スタッフの教職協働によるKONANプレミア・プロジェクトの一環で、文学の場で活躍している方を毎年お招きしてイベントを開催し、大学や学問の中に囲い込まれがちな「文学」を、学生や一般の方たちに開き、共有していこうという文化貢献を目的としています。
第2回となる今回登壇いただいた藤野可織さんは、2006年にデビュー作「いやしい鳥」で第103回文學界新人賞、2013年「爪と目」で第149回芥川賞、2014年『おはなしして子ちゃん』で第2回フラウ文芸大賞を受賞されています。2023年7月には『爪と目』の英訳版Nails and Eyesも出版されました。

今年のイベントには本学の学部生、大学院生、さらに藤野作品のファンや文学好きの一般の方、高校生など、多くの方にご参加いただきました。イベントの第1部では、本学文学部教授・岩井学をコーディネーターとし、参加者からの質問に藤野さんに答えていただきました。京都での生い立ちに関する質問に始まり、「爪と目」や『ピエタとトランジ』など個々の作品についての質問、また創作方法に関するものなど、質問は多岐にわたりました。参加者たちからの熱心な質問一つ一つに、藤野さんが丁寧に答えてくださいました。さらに「爪と目」の結末部や来年刊行予定の作品の一部などを藤野さんが朗読してくださいました。

第2部はサイン会ということで、参加者のほとんどの方が列に並び、藤野さんと言葉を交わし、イラスト付きのサインをいただいていました。

イベント後のアンケートでは、「まさかお会いできると思っていなかったので嬉しかった」、「朗読していただけるとは思っておらず、感動しました。素晴らしい時間でした」、「藤野可織さんの魅力と“クセ”が分かって作品理解が深まりそうです」、また「怖い人かと思っていたらそんなことなかった」といったものまであり、予定の時間を超えて、皆が藤野ワールドを堪能しました。今回のイベントを通し、読者それぞれにお気に入りの作品があり、また同じ作品でも読者によって様々な解釈やアプローチがあることが分かり、藤野作品の奥深さを改めて知ることができました。
「文学、あります」チームでは、読むべき作品をこの世に送り出している作家の方々を今後もお招きし、イベントを開催していく予定です。来年以降も乞う御期待ください。(今回のイベントの第1部は2025年3月末までYoutubeで配信されています[動画はこちら]。)
(文: 文学部英語英米文学科教授 岩井ガク)