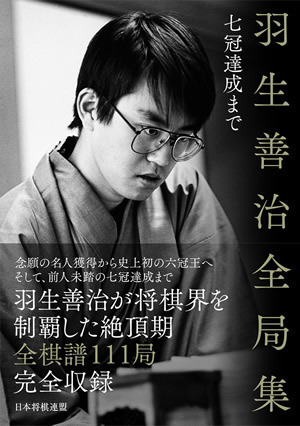
理工学部 1年生 石山 遥希さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 羽生善治全局集 七冠達成まで
著者 : 将棋世界 編
出版社:マイナビ出版
出版年:2015年
将棋界で有一、七つのタイトルを取り、七冠王になった羽生善治の名人獲得から七冠王達成までの合計111局の棋譜が載っている将棋棋譜解説本です。一局一局に解説もついていて、わかりやすかったです。将棋中級者以上の方や羽生善治ファンの人は是非とも一読してほしい一冊です。

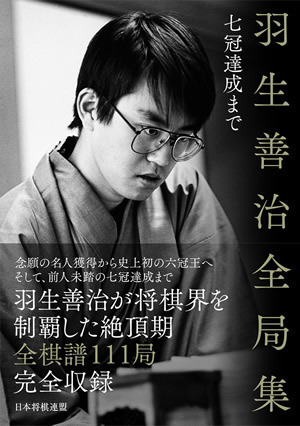
理工学部 1年生 石山 遥希さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 羽生善治全局集 七冠達成まで
著者 : 将棋世界 編
出版社:マイナビ出版
出版年:2015年
将棋界で有一、七つのタイトルを取り、七冠王になった羽生善治の名人獲得から七冠王達成までの合計111局の棋譜が載っている将棋棋譜解説本です。一局一局に解説もついていて、わかりやすかったです。将棋中級者以上の方や羽生善治ファンの人は是非とも一読してほしい一冊です。
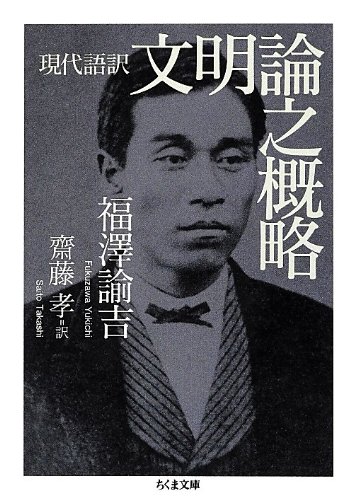
経済学部 3年生 Tさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 現代語訳 文明論之概略
著者 : 福沢諭吉著 , 齋藤孝訳
出版社:筑摩書房
出版年:2013年
筆者の福沢諭吉は、大坂の蔵屋敷で下級武士の長男として生まれた。幼少期は塾で勉強に励み、慶應義塾の基礎となる蘭学塾を開いた。以降、アメリカ、イギリス、ロシアを訪問した。彼の啓蒙思想、教育の考え方は、近代日本の発展に大いに貢献した。学問の重要性を説いた「学問のすすめ」は彼の代表作として現在も広く世間に知られている。
本書は、「学問のすすめ」と同時期に刊行された諭吉による文明論である「文明論之概略」を現代に生きる我々でも読めるように、教育学を専門とする大学教授の齋藤孝氏が現代語訳した。タイトル通り本書は文明論であり、文明を発展させるにあたり何が大切であるかが述べられているが、それは、革新的な技術や時代に合った法律ではない。文明を発展させるにあたり最も大切なことについて、物事の本質を捉えてながらも、抽象的になりすぎず、欧米、アジアなどの歴史的な出来事や身近な物事を例に挙げて説明している。そのため、難しい本を読んでいる感覚は無かった。福沢諭吉という天才の考えを普通の大学生である自分が理解できたことに感動を覚えた。
執筆当時と現在では、日本は大きく発展し、世界の中での日本の位置づけが変わっている。しかし、時代は変わったとしても、日本の文明の発展に必要なものは当時と変わらないように感じる。諭吉のメッセージは、現代に生きる我々にも通用するだろう。
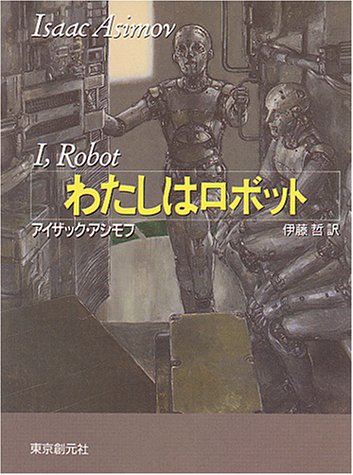
フロンティアサイエンス学部 4年生 岩田 和也さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : わたしはロボット
著者 : アイザック・アシモフ著 , 伊藤哲訳
出版社:東京創元社
出版年:1976年
本学で所蔵している本はこちら ⇨ アイザック・アシモフ著 , 小尾芙佐訳 『われはロボット 』早川書房 , 2004年
本作の人間とロボット(人工知能)の関係は「ロボット工学の三原則」に基づいている(一部抜粋)。
これらの法則はロボットが人間に従属することを示している。現在、就職活動では「将来はロボットに仕事をとられるかもしれない、人工知能が発達すると働き方も大きく変わる」と必ず1回は耳にする。現在の日本におけるロボットへの接し方は共存ではなく競争のようだ。ロボットは休む必要がなく、専門性に特化した構造を持っていれば人工頭脳を駆使して人間以上に効率的に行動し、高い生産性をもたらす。それゆえにロボットは人間に従属する存在であることを再定義すること三原則は、将来的に人間の優位性を保つうえでも必要であるといえる。
さて本作では執筆者アシモフ自身が考案した「ロボット工学三原則」の欠点やイレギュラーな条件から見えるロボットの不完全性や、人工頭脳がもたらす危険性が記されている。この書評で私は注目すべき章として「逃避!」を紹介したい。この章では、科学者が極めて優秀な人工知能に、星間エンジンを積んだ宇宙船を設計するように依頼した。その宇宙船は理論上、搭乗者が星間を移動中に必ず死亡するため、他の人工頭脳では「人間を死なせない(第一)」と「設計する(第二)」というジレンマによって思考回路が破綻、故障した。しかしこの人工頭脳ではある一つの解が提示した。移動中に一度死んで、目的地に着いたら蘇生すればよいのだ。作中でその宇宙船の搭乗者が実際に一度死亡し、魂が天国の門の手前まで行ってから現世に帰ってきた。人工知能にとってこの解は非常に合理的なものである。しかし同時に人工頭脳が目的のために人間的な解釈を超えた三原則の下で結果を導き出す危険性も秘めていることわかる。
本作が発表された1950年前後は人工知能そのものが開発されて間もない頃である。アシモフは人工知能が人類にもたらす恩恵とその背後に潜むリスクを本作で例示するかのように記している。ロボットと人工知能が一般的に普及しつつある今こそ、人工知能が生まれた頃に執筆されたこの一冊を読み直し、人間とロボット(人工頭脳)とのあり方を考えるべきではないだろうか。
フロンティアサイエンス学部 4年生 Ⅰさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : すばらしい新世界
著者 : オルダス・ハクスリー著 , 黒原敏行訳
出版社:光文社古典新訳文庫
出版年:2013年
理想郷は人々が過去に経験をもとに思い描いた幸せな機会に恵まれた世界である。ではもし人類規模の戦争、虐殺というこれ以上に感じることはないほどの苦悩を経験した場合、人々はどのような理想郷を求めるのだろうか。本作の世界その可能性の一つとして、苦悩からの逃避を選択した。
この世界では人間が工場で社会的階級別に体格や容姿、知性が調整されて生産される。この生まれつきの超えようのない壁は、人種や社会的階級の差別を根絶した。つらいことがあれば快楽剤(ソーマ)を飲んで忘れてしまえ。争いも競争もない、つらいことは忘れる理想郷を本作の人々は選んだのである。
しかし、ソーマを飲んでも解決できない苦悩もある。バーナード・マルクスは最高階級でありながらトラブルで低層階級の体になってしまった。マルクスは同階級と仲良くすればするほど劣等感を感じ、卑屈な性格になっていく。そこでマルクスは旧文化(我々の文化)を受け継ぐ青年ジョンを連れてくるなどして注目を集めたが、そこで得られたことは、人々の目当てがジョンでありバーナードは飾りである事実であった。そのジョンもまた、今まで育ってきた概念を否定した社会に困惑した。苦悩の果てにジョンはトラブルを起こし、バーナードとも切り離されたジョンは一人でこの理想郷に何を感じたのか。
本作から率直に感じたこととして、競争、苦悩することを否定した人類のコミュニティの中で、卑屈なバーナードこそもっとも人間らしい行動をしているように感じた。他者との比較、自己嫌悪、虚栄心、現実の自覚、自暴自棄など実に人間らしい行動を見せている。私はこのような人間が人間性から逃避した世界こそ、バーナードのような異端の存在が変革をもたらす鍵になると考えたが、バーナードもまた人間らしく名声を求め、栄光を手に入れたが、最後は道を誤り墜ちていった。
最後に我々と同じ概念を有するジョンは何を感じたのだろうか。ジョンが本作の世界で感じたことは、本作を読んだ我々の感想でもある。ジョンは悲惨な最後を迎えることで、この世界に解を見出したが、私がその立場であればどうなるであろうか。それを考えながら本作を読み直すことも楽しみの一環である。
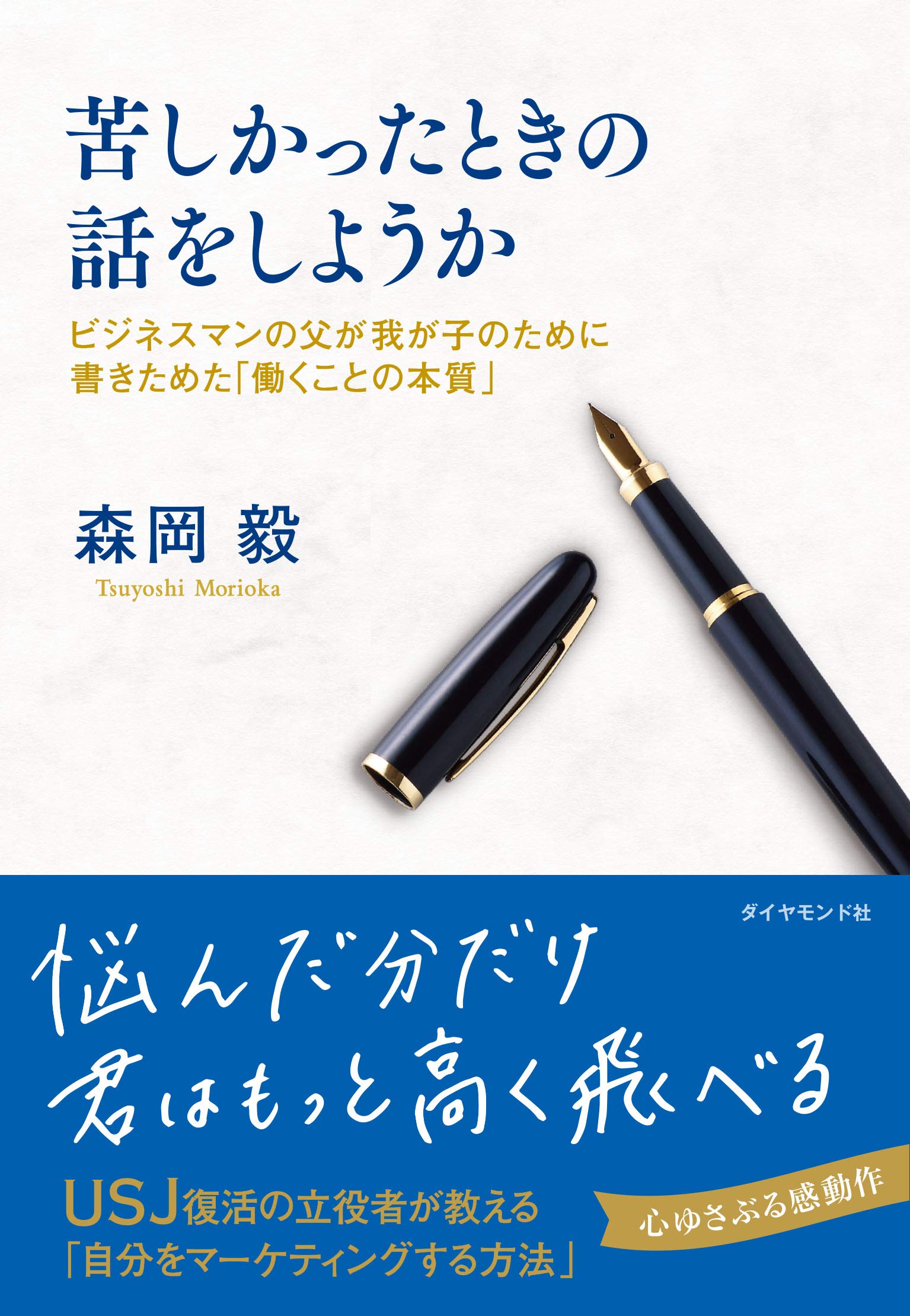
経済学部 3年生 Tさんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 苦しかったときの話をしようか
著者 : 森岡 毅
出版社:ダイヤモンド社
出版年:2019年
著者である森岡毅氏は新卒でP&Gに入社し、マーケティング本部で勤務し、米国の世界本社に移籍した。その後、27歳でブランドマネージャーに昇進、ウエラジャパン副代表を務めたのち、ユー・エス・ジェイに入社した。マーケターとして、USJの経営再建の指揮をとり、V字回復させた。また、USJだけでなく、丸亀製麺やグリンピア三木の立て直しにも成功している。そんな筆者の挫折経験が赤裸々に綴られているが、主に就活生に企業選びの方法を提示している。
筆者は、「努力の人」である。若い頃、上司が指示した訳でもないのに、憧れの上司に追いつくため、朝7時から終電まで働いた時期もあった。そのせいで疲れているのに、眠れなくなったという。その後は、効率的なパフォーマンスを行うために努め、結果を出した。昇進して、米国に移籍した際、大きな失敗をするもそこであきらめず、血のにじむような努力を続けて結果を出した。環境が変わっても自分を信じ、結果を出すために努力したことで、無敵の職能を身に付けたといえる。
昨今は、終身雇用、年功序列の概念が、大企業でも無くなりつつある。また、コロナウイルスの影響で大企業でもリストラが行われた。本書では、目まぐるしい社会の変化に適応できるようなキャリアの考え方を教えてくれる。
途中で壁にぶち当たっても、それが自分の選んだ道筋の途中にあるなら、越えるために自分を律しなければならないと思わせてくれるだろう。
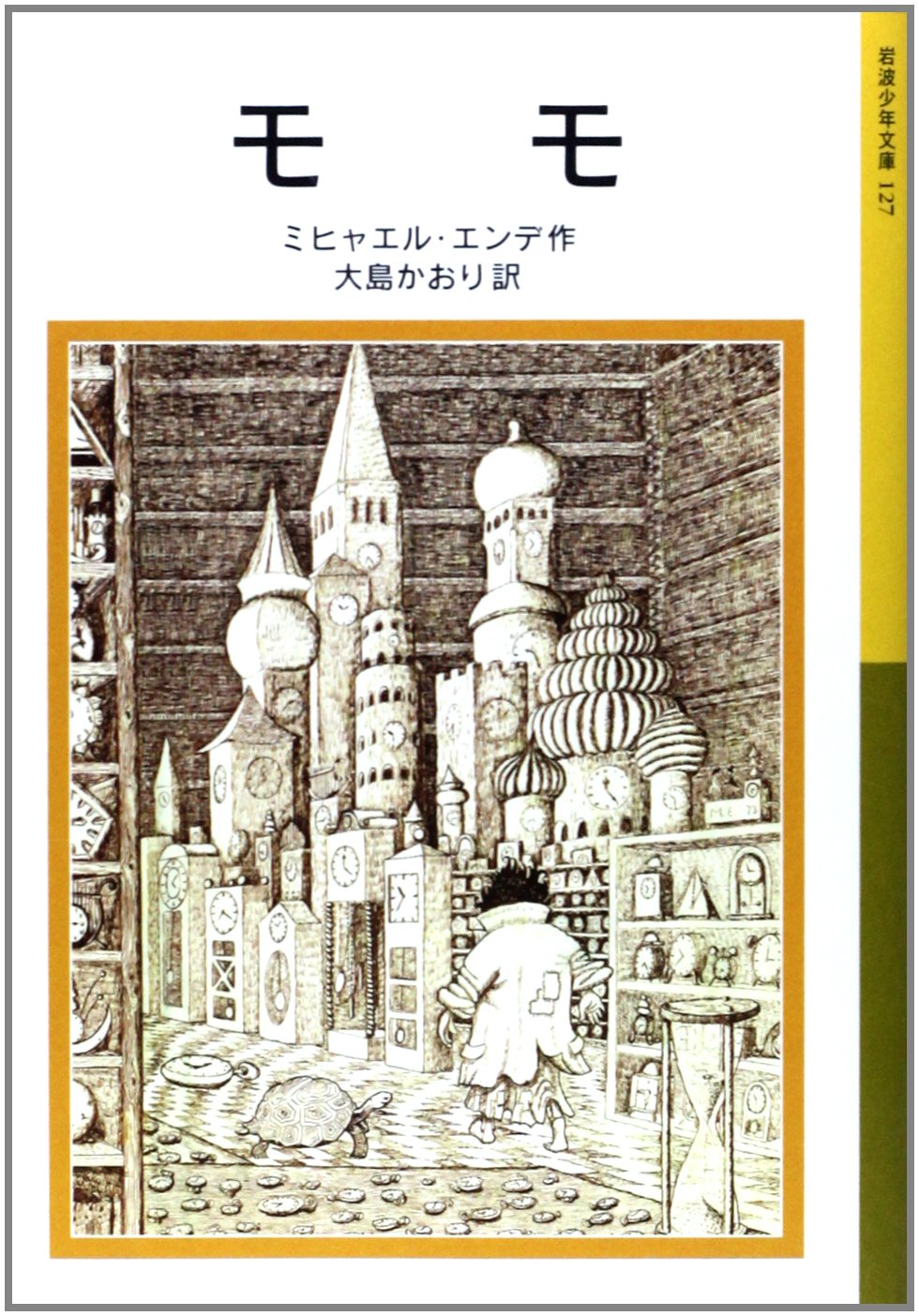
経営学部 4年生 大堀 舞佳さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : モモ
著者 : ミヒャエル・エンデ 著、大島かおり 訳
出版社:岩波書店
出版年:2005年
小学校の推薦図書の中に、この題名を見たことがある人も多いだろう。
だが、大人になった今!ぜひ読んでほしい1冊である。
主人公モモは身寄りがなく、劇場の廃墟にくらしている。髪や目はまっくろで、いつもはだし。お世辞にも清潔感があるとは言えないものの、この少女には、「ひとのはなしを聴く」特技がある。どんなに怒っていても、モモがはなしを聴けばたちまち怒りが収まるのだ。そんなモモには2人の友人がいる。道路掃除夫のベッポと観光ガイドのジジ。ベッポはいつものんびりゆっくり道路の掃除をし、ジジは本当かわからないような作り話(?)が得意。モモがくらす街はみんなおだやかでいい街だった。
しかし、そこへ灰色の男たちがやってくる。灰色の男たちはたくさんの煙を出す葉巻を吸い、みんな同じようなかっこう。互いを数字で呼び合い、せかせかと街の人々に話しかける。
「あなたはこんなに時間を無駄にしているのです。もっと節約しなければなりません」と言いより、時間を盗むのだ。みんな仕事をいやいやこなすようになり、子どもは学校につめ込まれてしまった。おだやかな街があっというまに灰色に染まってしまう。そんななか、灰色の男たちはモモが邪魔に感じてくる。モモは灰色の男たちの時間泥棒から逃げるため、カシオペイアというカメに助けを借りてマイスター・ホラというおじいさんのもとへ。
マイスター・ホラは時間をつかさどる。彼の話を聴き、モモは時間とはなんなのかを知っていく。灰色の男たちに立ち向かうため、モモとマイスター・ホラ、彼の仲間のカシオペイアが奮闘する。
この物語の素敵なところは、モモ目線の描写である。マイスター・ホラの家で食べる黄金のパン・あつあつのチョコレート。灰色の男たちから逃げるときの気持ち。時間の花から聞こえる音楽。これらが子どもらしい例えや言葉で豊かに描かれている。モモはいつも外からの刺激を全身で受け止める。この力が、「ひとのはなしを聴く」ときに活かされているのかもしれない。
大人になった今、しなければならないことに追われてせかせか生きてしまっている人も多い。私もそうだ。だが、本当にしなければならないことなどないのだ。時間とは時計で測り切れるものではなく、一瞬にも永遠にもなりうる。その時間をどう使うか、だれのために使うかを今一度考えるきっかけをくれる。
『モモ』はそんな作品である。