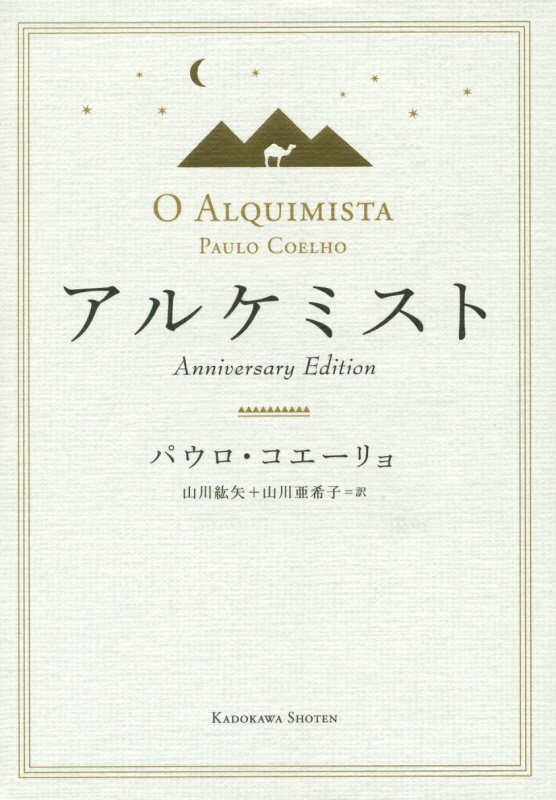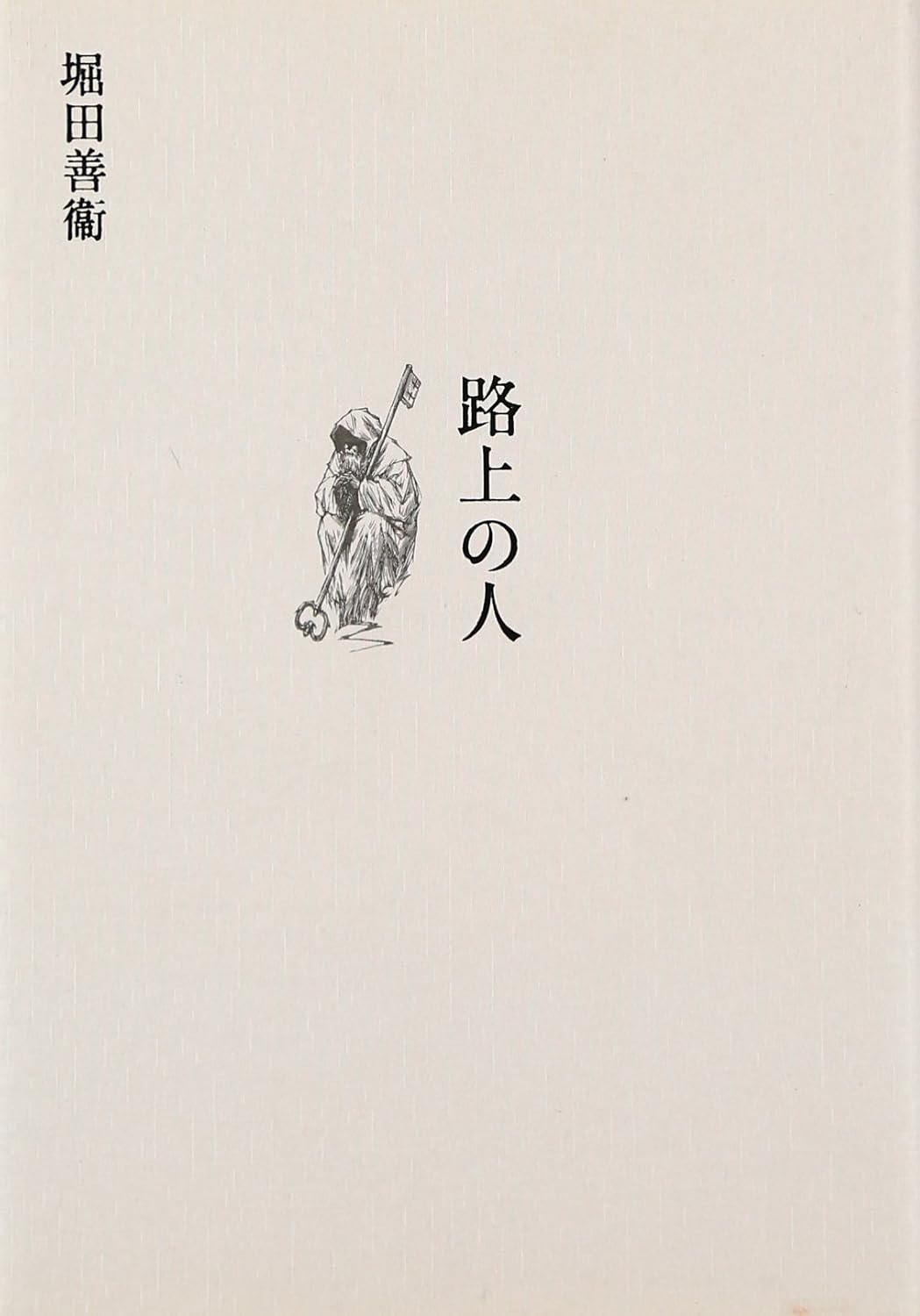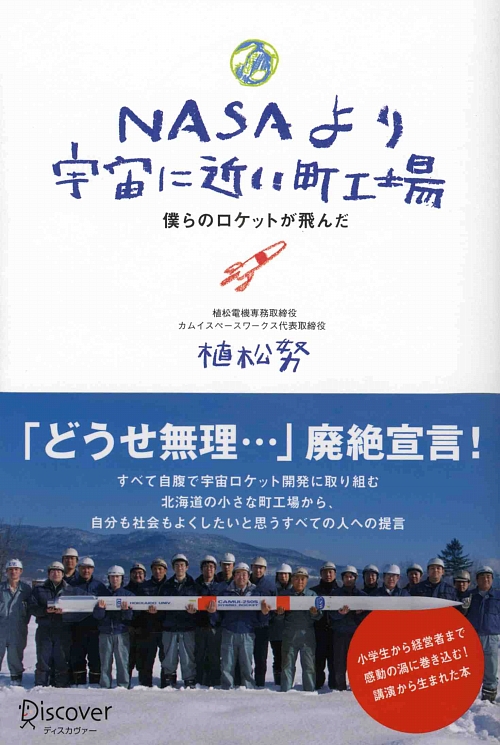
知能情報学部 4年生 船本 敬人さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : NASAより宇宙に近い町工場 : 僕らのロケットが飛んだ
著者 : 植松努
出版社:ディスカヴァー・トゥエンティワン
出版年:2015年
宇宙やロケットと聞くと、多くの人はNASAのような巨大な研究機関や特別に優秀な人だけが関われる世界を思い浮かべるだろう。しかし本書は、そのような固定観念を大きく覆す内容となっている。北海道の小さな町工場から宇宙開発に挑戦した実話が描かれており、「夢や挑戦は遠い存在ではない」ということを強く感じさせられた。
本書では、著者が経営する町工場が人工衛星や探査機に使われる部品を製作するようになるまでの過程が語られている。ミクロン単位の精度が求められる加工や極低温・高温といった過酷な環境に耐える技術など高度な内容が扱われているが、難しい専門用語は少なくて技術に詳しくない読者でも理解しやすい構成になっている。また、成功の話だけでなく、資金不足、失敗、周囲からの反対といった現実的な困難についても率直に描かれており、挑戦の厳しさがリアルに伝わってくる。
本書で特に印象に残ったのは、著者が繰り返し述べている「どうせ無理」という言葉への疑問である。周囲の大人や社会が無意識に発するこの言葉が若い人の挑戦する気持ちを奪ってしまうことを著者は自身の経験を通して訴えている。町工場という限られた環境であっても、工夫と努力を重ねることで世界に通用する仕事ができるという事実は将来や進路に悩みやすい大学生に対して大きな励ましになると感じた。
本書は宇宙開発をテーマにしながらも、その本質は「挑戦する姿勢の大切さ」にある。特別な才能や恵まれた環境がなければ夢は叶わないという考えを否定し、まず行動することの重要性を教えてくれる一冊である。特に、失敗を恐れずに挑戦を続ける姿勢や身近な場所からでも大きな目標に向かえるというメッセージは学生生活の中で進路や将来について考える機会の多い大学生にとって強く心に残るものだろう。読み終えた後に自分の中にある「できない理由」や「どうせ無理」という考えを見つめ直し、一歩踏み出してみようと思わせてくれる点に本書の大きな価値があると感じた。