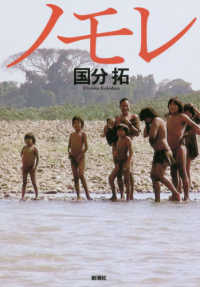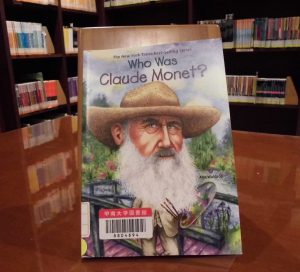-先生のオススメの本はなんですか
CUBE生、1回生に向けてなら、『市場を創る』をオススメしますね。経済学入門で初級レベルのミクロ経済学を学習した後に読むと、目から鱗ですよ。
-なぜこの本をオススメするのですか
初級レベルのミクロ経済学では、市場は効率的な資源配分を実現するが、万能ではないことを学んだはずです。しかし、「市場はつかみどころがなく、抽象的で、現実に役立たない」と思っている人も少なくないでしょう。
そのような思い込みを良い意味で裏切ってくれるのが本書です。「とにかく市場に任せておけば大丈夫」とか「市場経済は格差を生むからケシカラン」といった乱暴な議論とは一線を画します。市場がうまく機能するためには、市場を支えるルールや制度をうまく「設計」することが重要であるということを、古今東西のさまざまな市場を例として具体的に説明しています。しかも数式やグラフはまったく登場しません。一般的なミクロ経済書ではスルーされることが明快に書かれていますので、この本を読めば市場という概念がぐっと身近なものに思えるはずです。
-このようにオススメの本を探すには何が必要だと思いますか
経済・経営系の本には、経済学・経営学の知見に裏打ちされたものもあれば、著者のみに基づくものもあり、学部1回生ではなかなか判断が難しいと思います。そこで、10年以上前に出版された本でも、名著と言われる本をいくつか読んで(今回紹介した本も名著です!!)、経済学・経営学の思考回路に触れることが先決だと思います。どの本が名著と評判なのかは、大学の先生方が最もよく知っています。次に、そういった本の最後に書かれている参考文献とかリーディング・ガイドに載っている本にあたると、芋づる式に良い本に巡り合えるはずです。
<小嶋健太先生おすすめの本> ジョン・マクミラン著 ; 瀧澤弘和, 木村友二訳 『市場を創る : バザールからネット取引まで 』 NTT出版,2007年