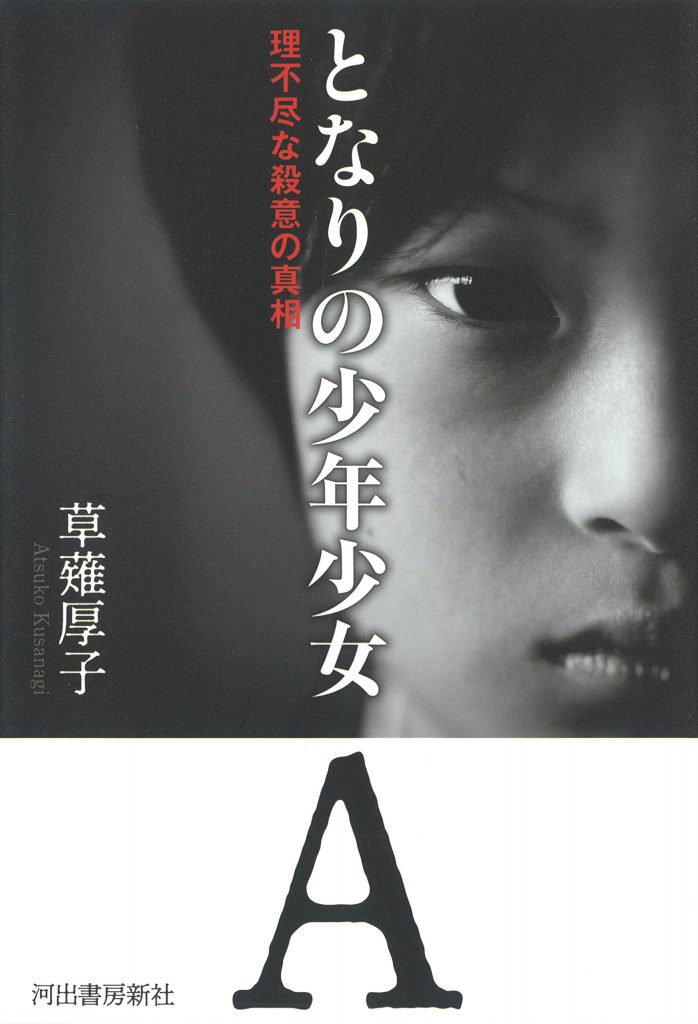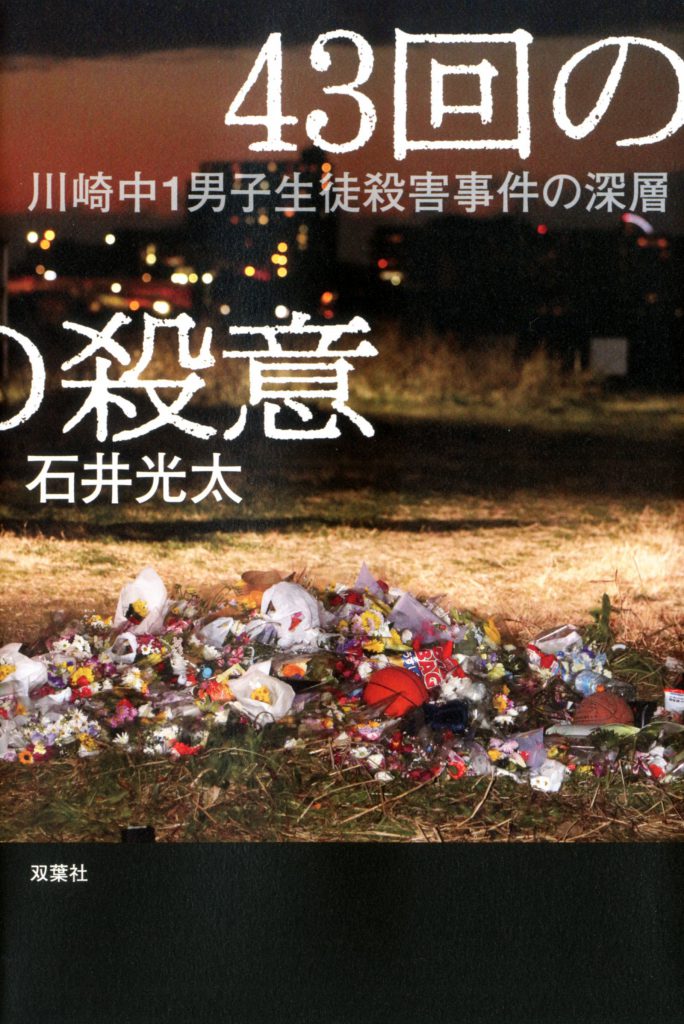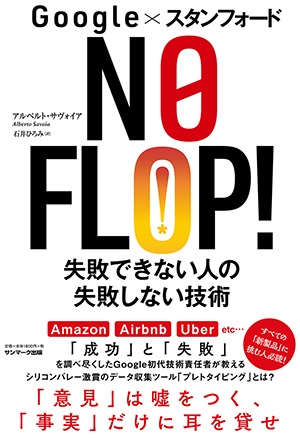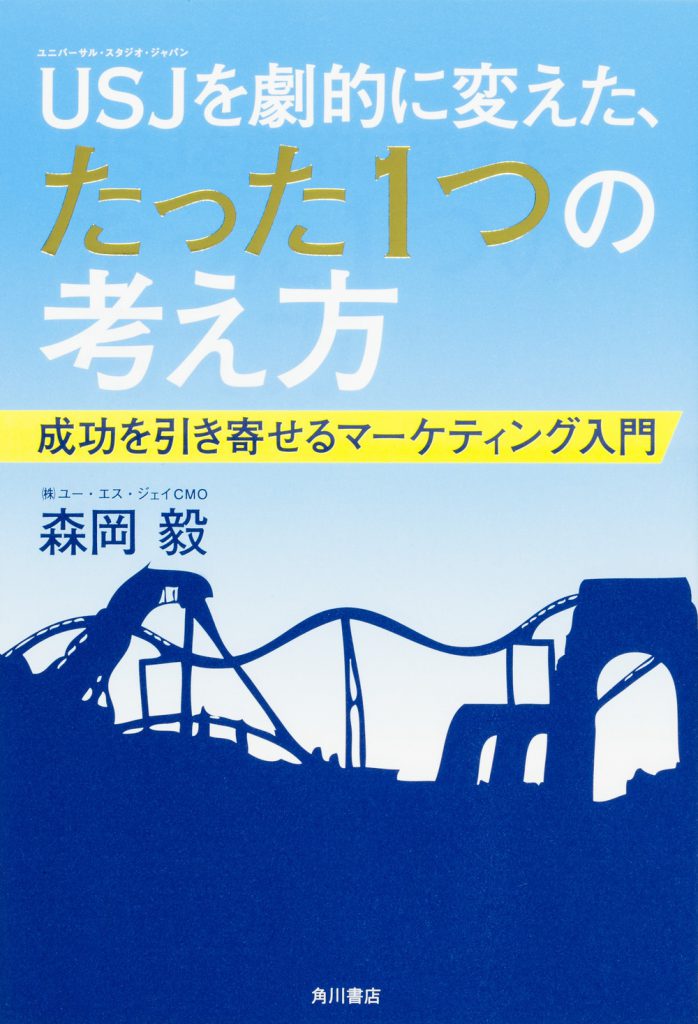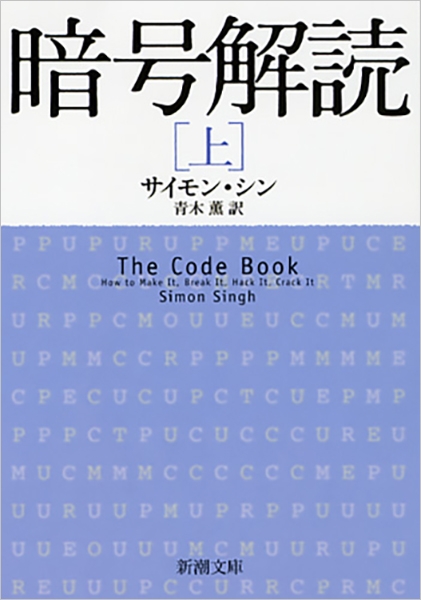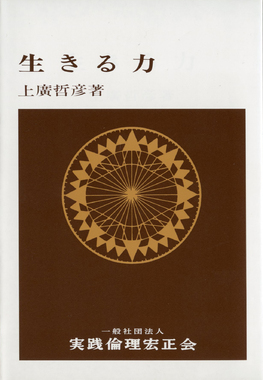
知能情報学部 4年生 植野 浩任さんからのおすすめ本です。(KONAN ライブラリ サーティフィケイト)
書名 : 生きる力
著者 : 上廣哲彦著
出版社:実践倫理宏正会
出版年:1959年
これは自宅にあった古い本だが、書名が気に入ったのと、戦後の日本人の価値観が見えてくるため読むに至った。出版数が多く、当時は人気だったようで幸せのために努力出来ていない人間に読んで欲しいと記されている。
内容では、戦後に成人期を迎えた人々が希少なものとして書かれていて、今なら古い固定概念だと言われそうな言葉も載っている。とは言え、人間はどの時代でも人間であり、約70年経った現代でも共感できる話が多々あるので紹介していく。
現代でも共感できる話には物事の感じ方等心理的な表現が多い。冒頭で日々の生活に苦楽は付き物としながらも、物事の見方によって心は明るくなるとしている。働きを楽しみ、家庭を愛し、社会に貢献する心を持てば気持ちは前向きになる。他にも「その時その場の心に生きよ」という言葉は、状況次第で柔軟に対応していけば良いという事で、状況を打開するにはそれを守れば幸福になる、という考えに専念すべきだと書かれている。これを読めばそういった適切な処理をすることで、物事を打開できるだろう。
また、この本には幅広い内容が書かれており、実践論理や反省の仕方、夫婦間の仲や商業での考え方等自分に合った精神の道しるべを見つけられる。例えば実践論理とは自分にとっての正しい筋道は何なのか、それを自分自身で実行し実験しなければならないという事である。前代未聞のコロナ禍中での学生もそうだったはずで、それぞれのやり方を色々と試したはずだが、これを論理の実践で補うことが出来るのだ。商業については終始一貫することが大切で、上手く行く時だけそれにすがるのは駄目だという、生き方に繋がる書き方をされている。
人は考え方次第で物事の見方が全く変わる。その具体的な状況から抽象的な状況までを解決する方法が述べられていて、様々な感情への対処法でもある。状況や感情というのは無限にあるものなので、生き方に迷った時はこういった本を読んでほしい。