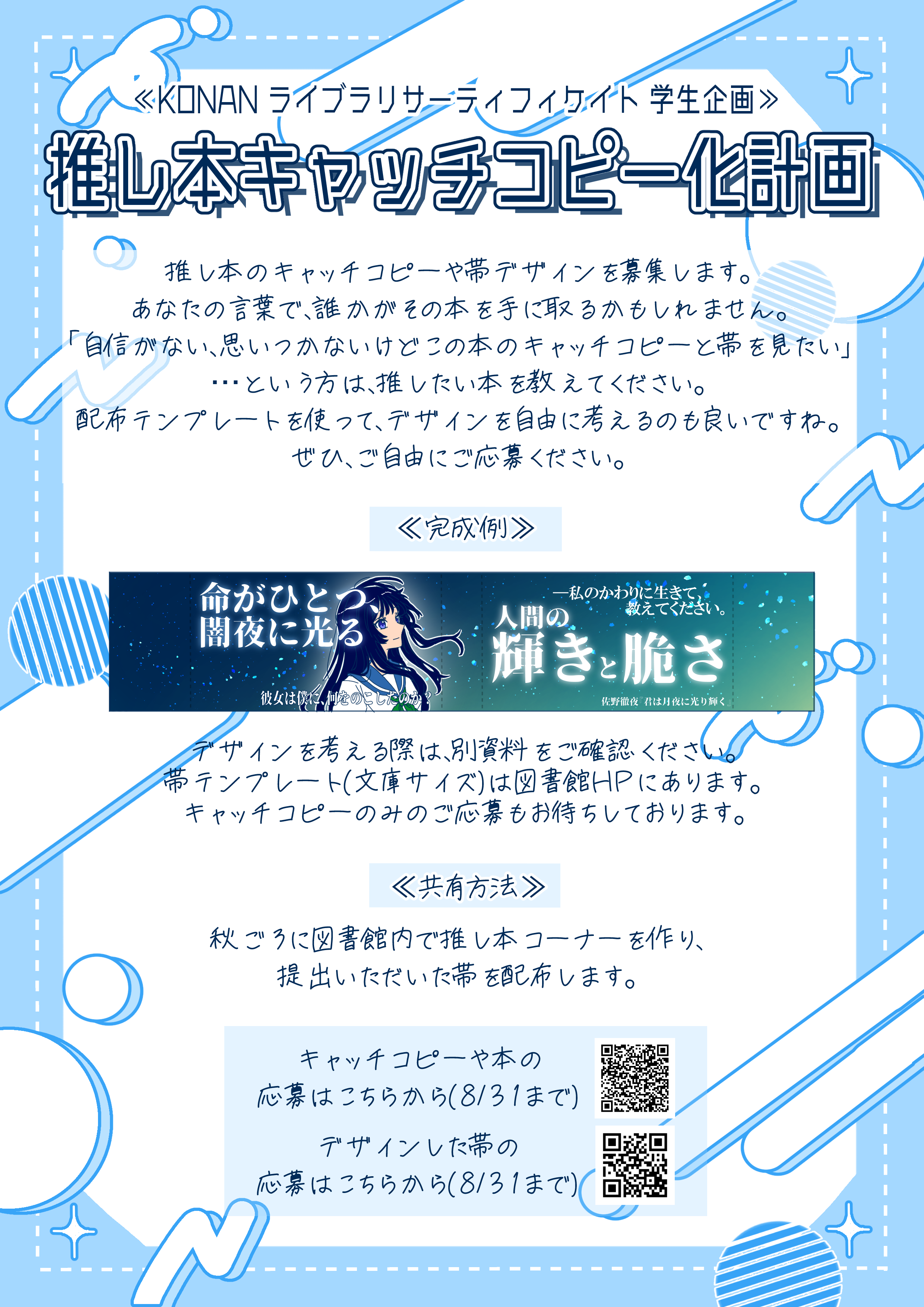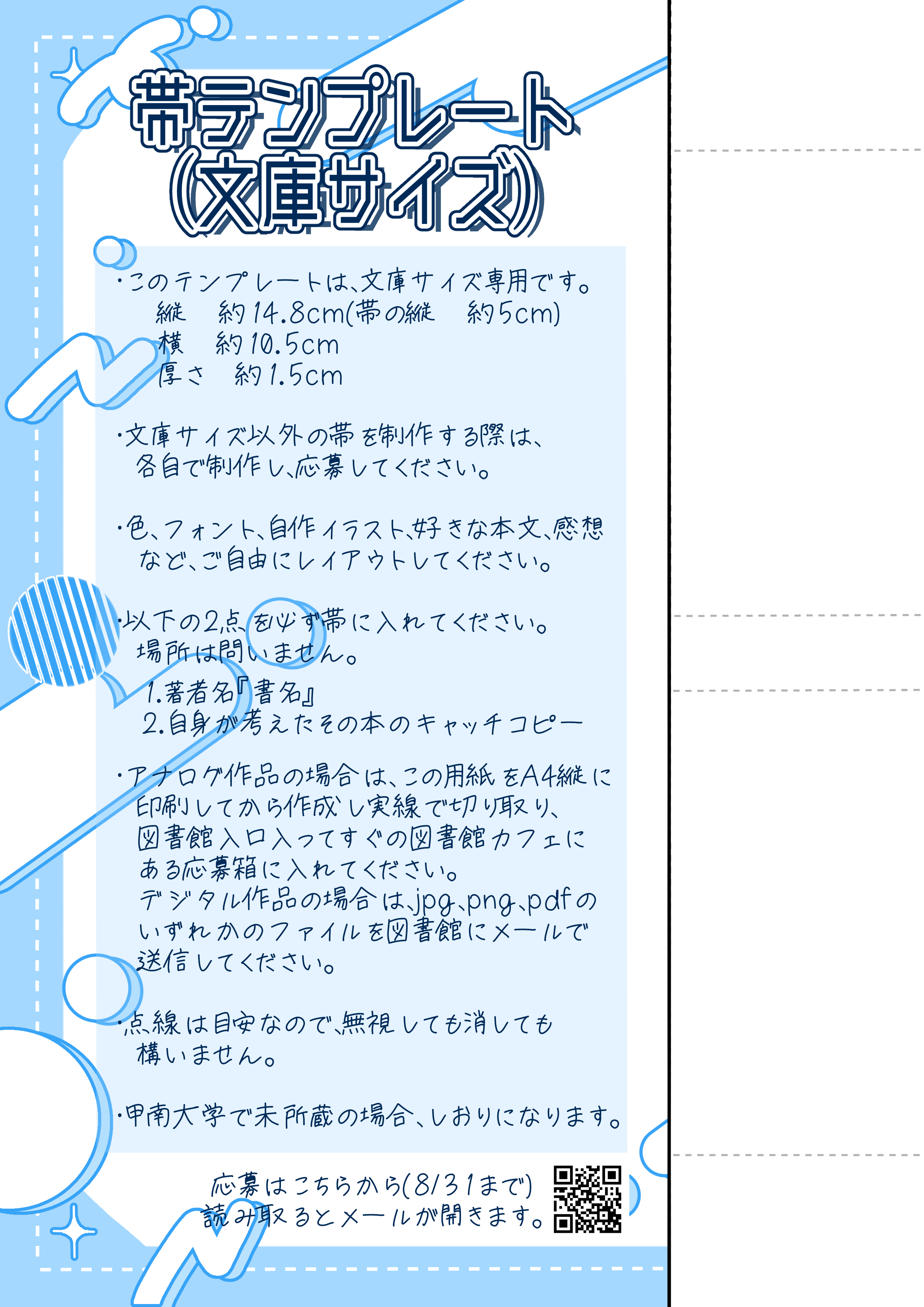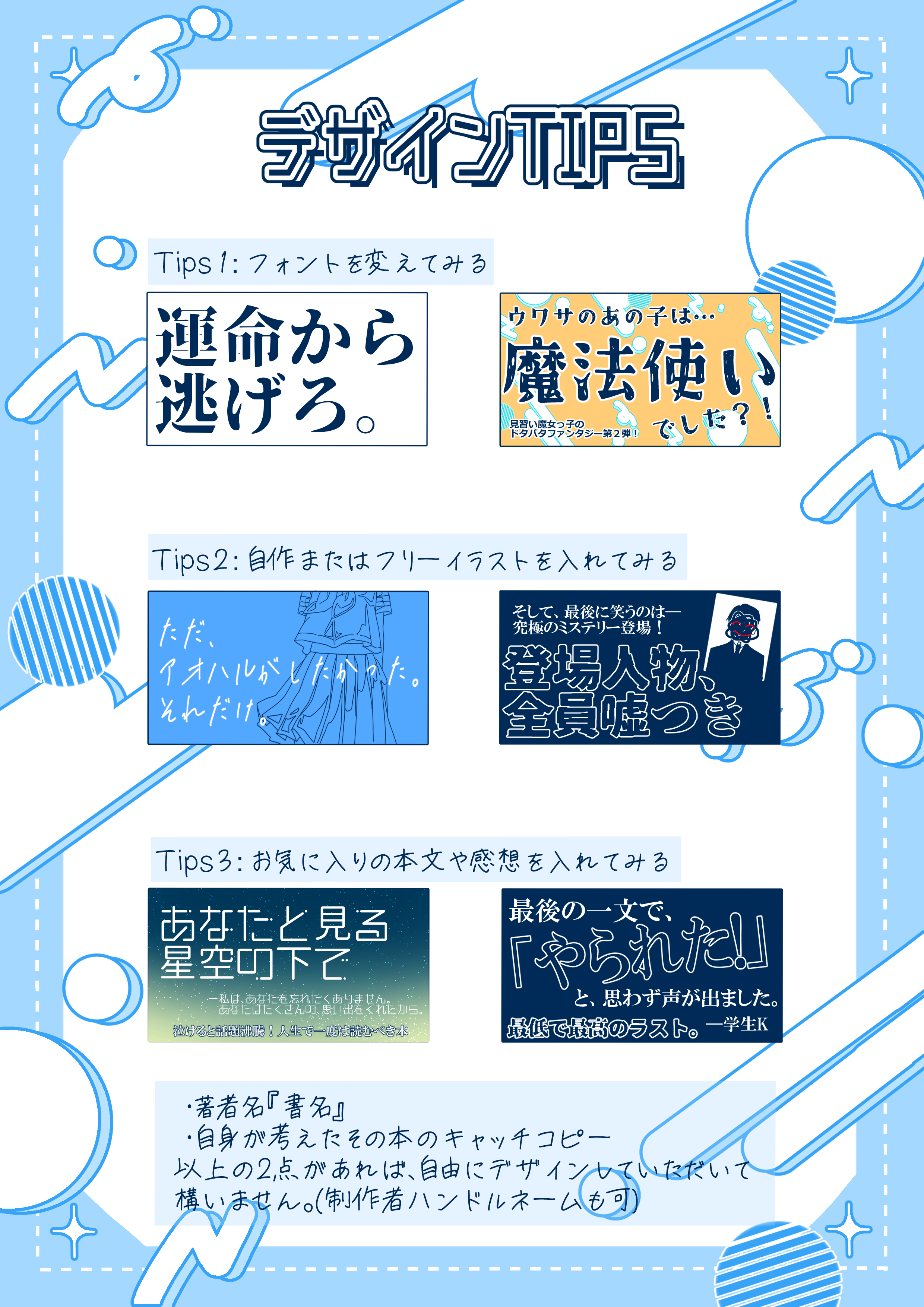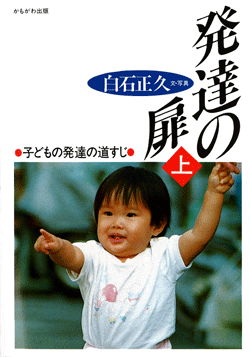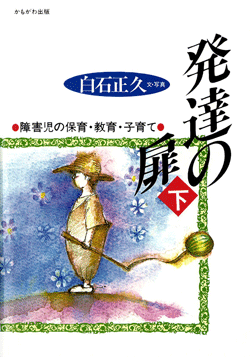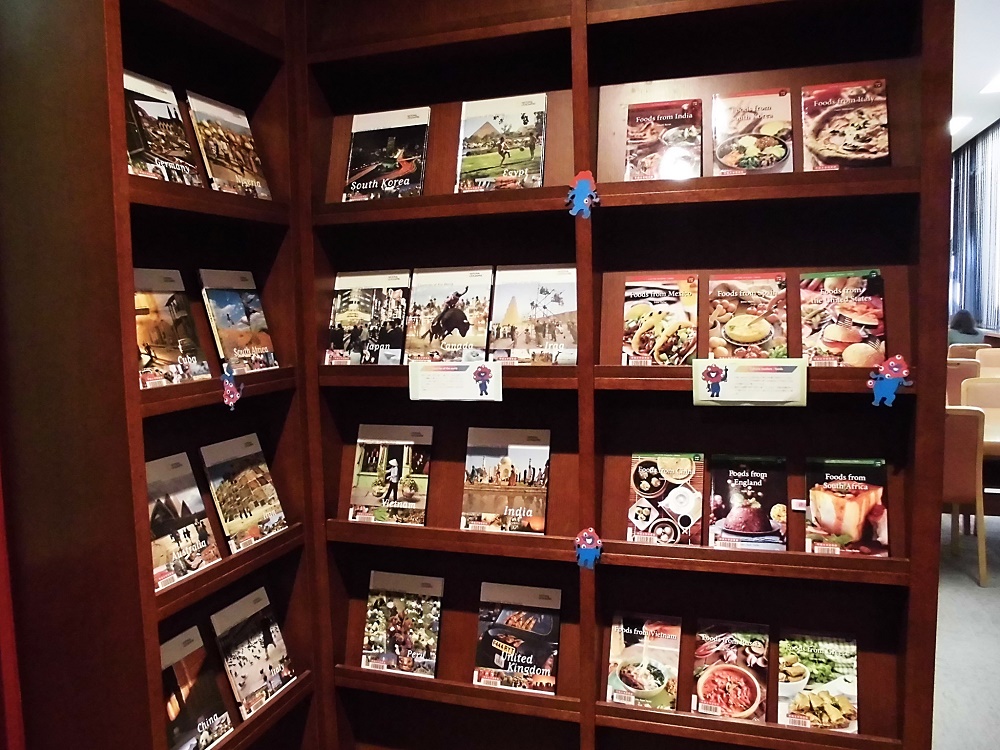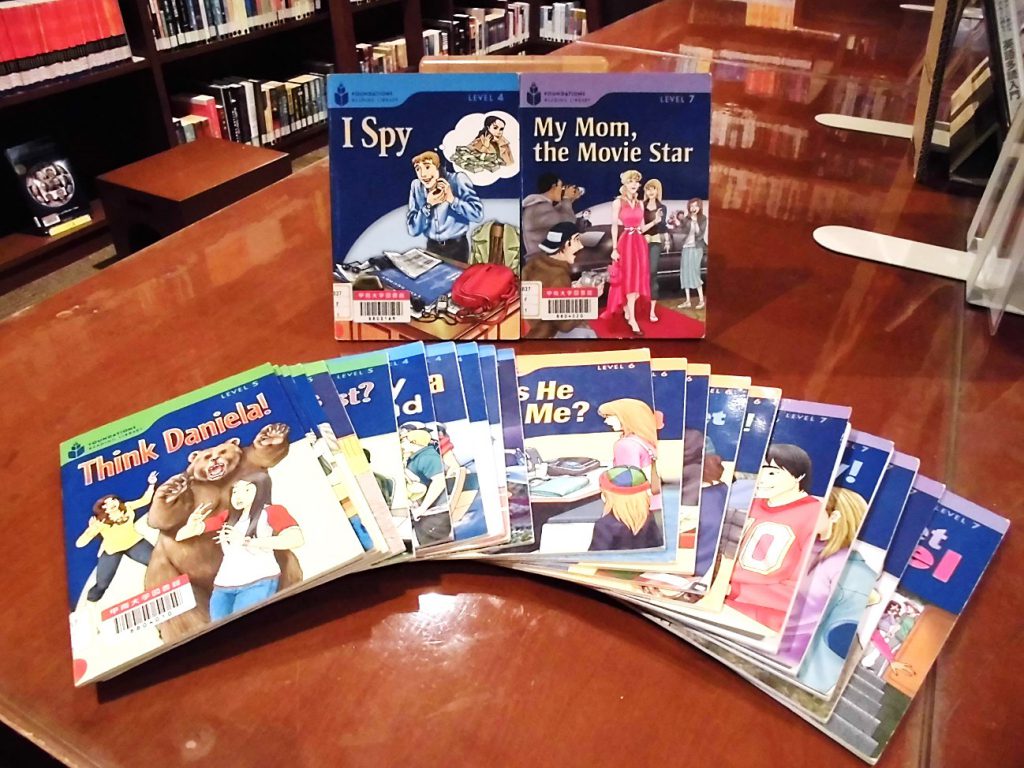図書館報『藤棚ONLINE』
理工学部・池田茂先生より
この本は、元宇宙飛行士の野口聡一さんと、元キャスターの大江麻理子さんが、自身の経験や人生観について語り合った対談集です。宇宙に行った「特別な人」が、帰還後に燃え尽き症候群に悩んだり、自分のあり方を見つめ直す姿。そして、キャスターとして活躍しながらも、「自分とは何か(=アイデンティティ)」を仕事に重ねすぎない生き方を模索する姿に、意外性と共感を覚えました。
印象に残ったのは、「半径5メートル」の人間関係や、リーダー・フォロワー双方の役割に意味があるという考え方です。また、NASAで実践されているMBTI(性格タイプ)を用いたチームづくりの話も、個性を尊重しながら協力することの大切さを教えてくれます。
この本なかでは、「成功」そのものではなく、「自分を実現するための手段」として仕事や学びがあるということが繰り返し語られています。他人に認められたいという「承認欲求」の先にある「自己実現欲求」にどう向き合うか、今の時代を生きる私たちにとって、大切なメッセージだと思います。
就職や進路に迷っている人、自分の立ち位置に不安を感じている人にとって、「悩む時間にも意味がある」「今の気持ちと向き合っていいんだ」と、前を向く力を与えてくれるような、励ましに満ちた一冊です。