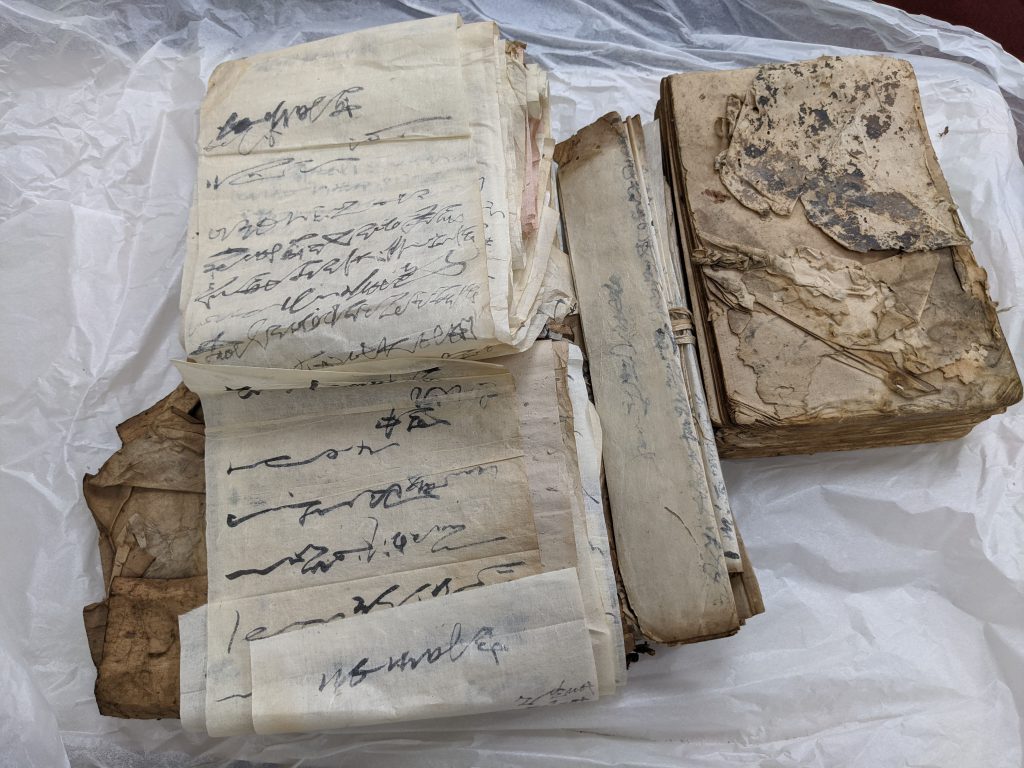甲南大学の文化会にあたる「人文地理学研究会」では、地理情報をもとに地域の観光や成り立ちの調査を行っています。現在は1年生から3年生の部員で構成されており、標高をもとにした地形図の作成や、対象地域の産業から観光など様々な分野について部員それぞれが調べています。毎年の文化祭では地理模型の作成を行うなど、地理や観光について楽しみながら活動しており、地理や観光に興味のある方にはとてもおすすめの部活動です。昨年度は淡路島の模型を作成し、その中で特に南あわじ市の地理観光について調査しました。今年の文化祭でも地理模型を作成予定なので、ぜひ足を運んでみてください。(4回生・前田彩花)