
- 経済学部
- 経済学科
- DEPARTMENT OF ECONOMICS
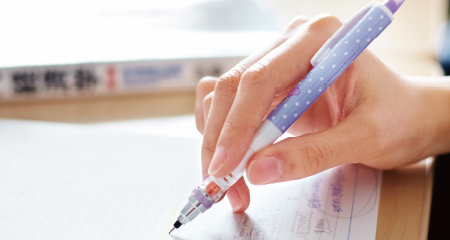
経済学部70周年企画
「学部70年の回顧と展望ー100周年に向けてー」
甲南大学経済学部は2022年に創設70周年を迎えましたが、コロナ禍の最中にあって記念行事を催すことは適いませんでした。
そこで遅れ馳せながら学部HPにこの新コーナー「甲南大学経済学部70年の回顧と展望—100周年に向けて―」を開設いたしました。
名誉教授の先輩方には、在職時のエピソードなども交えて本学部の掛替えのない特色をご指摘いただき、現役スタッフは自己紹介も兼ねながら、長期的視点に立って四半世紀後を見据えた学部の将来像を思い描くという趣旨によるものです。
ささやかな里程標としてご参照いただけると幸いです。
これからも甲南大学経済学部は学生一人ひとりが自身の個性を見出し、
自律的に成長する機会を提供することを通じて未来を切り拓く力を身につけた人材を輩出し、
人を幸せに、社会を豊かにすることを目指してまいります。
2024年11月
企画担当 奥田 敬
甲南大学経済学部創設70年によせて
1966年から2006年まで、私は甲南大学経済学部に専任教員として引き続き在職した。40年間、勤務校を変えることはなかった。他大学への転職をあまり望まなかったのは、なによりも、この大学・この学部には、教員間の上下関係が窮屈な講座制というものがなく、研究テーマの選択が自由であり、研究条件もわりあい恵まれていたからだ。
もっとも、他大学勤務の経験がないゆえに、他大学と比較しての本学部の特色を正確に把握することはむつかしい。それに、40年の間には、私のような「体制批判派」にはきびしい方向への時代環境の変化もある。およそ90年代以降には、私の労働研究に関心を寄せて批評し、また趣味の文学や映画について歓談できる親しいスタッフも限られてきた。職場の「居心地」は70年代、80年代ほどではなくなってきたとは言えよう。大学内の諸問題をめぐる教授会などの議論では、私はたいてい少数派であった。そうした変化については、これ以上、具体的に書きたくない。しかし、見解の対立はあれ、教員個人の教育内容、研究と発言の自由という原則が、本学部ではいささかも損なわれることはなかった。
ふりかえって私の本学・本学部勤務にとってもっとも恵まれていたのは、主として講義聴講生やゼミ生を通じて感じた学生のおおらかさ、明るさであった。むろん、彼らは、1957~66年という時期に私が出身大学で出会った、眉根をよせて社会の矛盾を熱く語る学生たちとは異なり、あまりにも屈託がなかった。はじめはその屈託のなさに戸惑いもしたものだ。けれども、在任中を通じ、学生のありようについて不愉快なことはなにひとつなかった。
70年代から80年代にかけて私の担当した「社会政策」の主な内容は労使関係論であった。「教育」の方針は、自分の人生観にとって「不都合な真実」も直視すること、なまの現実の歴史的・構造的な把握に努めること、いつも批判精神を忘れないこと、そして口頭表現ができるようになること・・・であった。彼ら、彼女らは、そうした「方針」にもとづいて労働問題を熱心に説かれて、はじめは辟易したかもしれないけれど、持前のまじめさゆえに、辛辣かつシニカルに受け止めることは決してなかった。そしてやがて、「先生ほどのきつい状況批判にはついてゆけない」にしても、これが本当なんだ、自分たちがこれから入ってゆく労働の世界は確かにがんばればなんとかなるというほど甘いものではないようだとほのかに気づくようにはなったと思う。教師の思い上がりにすぎないだろうか。
注目すべきことに、学生の質は、80年代末ごろからぐんぐん高まってきたように思う。ほかでもない、これまで経済学部では少数であった女子学生が増えてきたからだ。一般的に関西の私学では成績優秀者の多くは女子学生だという。その理由のひとつは、女性の大学進学率が高まるなかでも、保護者はやはりなかなか下宿の必要な東京進学を許さないため、勉学意欲の高い女性が居住地近くの関西私学に来ることが多いからだろう。甲南大学も例外であるまい。ともあれ、少なくとも私の講義聴講生やゼミ生にも女子学生が増え、彼女らはやがてそのグループのもっとも真摯な中心的なメンバーになっていった。
同じ頃、私の教育内容の重点が次第に、労使関係論・労働組合論を背景におきながらも、現代日本の企業に生きるサラリーマンや「OL」とよばれた女性社員のリアルな状況把握に徐々に移っていったことの影響もあるだろう。90年から2000年代にかけての授業では、能力主義的選別の人事管理、働きすぎや過重な仕事ノルマ、パワーハラスメントや過労死やリストラ、女性差別、そして大卒者にとってももはや無縁ではない非正規雇用などが 語られた。そのころ私が刊行した三冊の岩波新書が、好個のテキストになった。
学生の対応は女性と男性とでは少し異なるように思う。男子学生は、きびしい状況でもなんとか成功的なサラリーマンとしてやってゆかねばならないという世智にとらわれて、ゼミ生といえども本能的に「先生の言うこと」を相対化しようとする傾向にある。それは「男の規範」に生きるある種やむおえない選択だ。けれども女子学生は、「男女間の機会の平等」という時代の建前に関わらず、企業社会になお現存する多方面の差別のなかにある。その現状認識の裏面として、彼女らは企業内での「成功」を価値ある目的としてはいない。それゆえにこそ彼女らは、よりまっすぐに、労働状況の批判的考察と、歴史的または文化的な要因の理解に近づくことができるようである。能力主義に帰依する働きざまへの女性の疑いが、勉学にはある役割を果たすというべきか。
真摯な女子ゼミ生たちは、男子学生と協力して、経済学部の誇るインナーゼミナール大会で、ユニークなプレゼンテーションを企画し、台詞を書き、「出演」した。例えば、「ニュースステーション」・非正規労働者問題。富士銀行OLの過労死をめぐる裁判。セクハラに関する社内会議。卒業後3年にしてゼミの同窓会が開かれ、そこでさまざまの就職先のしんどさが語られ、その間にも起こっていたスーパー勤務者の失踪事件が解決にいたる――という群像劇「私たちの明日」。どちらかと言えばいつもは寡黙な男女ゼミ生たちの秘めていた創造力と表現力に、私はしばしば驚かされたものだ。男子学生をリードする女性たちは魅力的だった。在職時について語るとき最初に想起されるのはこうしたインゼミ企画の体験である。インゼミを通じて交際を深めのちに結婚するカップルもあった。
編集者の求める「長期的な視点」での「四半世紀後を見据えた学部の将来像を思い描く」ことは私はできない。退職後18年にしてもう80代半ばの引退の私は、その後の「団塊ジュニア」の子弟の学生の実像についても、教員スタッフたちの現実の経済社会への発信についてもほとんど知るところがないからだ。
ただ、退職後も、格差社会、過労死・過労自殺、労働運動などについて著作を重ねた私は、日本の政治や経済、わけても労働の状況についてとてもくらい診断を下している。なかんずく、周囲でなにがあってもスマホから顔を上げない――スマホはどれほど過酷なリアルを伝えているのだろう?――「Z世代」の、自己責任論の内面化と、どこの国でも生き生きと再生している社会運動への無関心に、落胆のあまり発言の気力さえ失っている。若者の批判精神の欠如においては、現代日本は世界のなかでも際立っていると思う。
それでも大学・経済学部について、虚しさにたえて「我が田に水を引く」ならば、甲南大学経済学部は、未来社会の壮大な夢を描くよりは、あるいは実務的なエコノミストを育てるよりは、すでにノンエリートである多くの卒業生を待ち受ける労働世界における、より具体的には頻繁なメンタルクライシスを招くほどの正社員の心身の疲弊と、累積する非正規労働者の貧困との相互補強という構造をしっかりとみつめ、そこからの出口を模索する若者を送り出してほしいと思う。そのためには、一般に軽視の傾向があるという人文科学的な教育の復権・充実が不可欠であろう。経済学部においても、教員スタッフは、環境・人口・人種の視野をもつ産業社会の歴史、多様な階層の人びとの喜怒哀楽をみつめる文学など、いわば文化の素養を若者たちに刻み込んでほしい。社会をdecentにする批判的知性はそこからしか生まないと思うからである。
『学生の力を伸ばす教育』
私は1976年から2012年までの36年間、経済学部で教えていました。学部の教育で特に印象に残っているのは、インゼミ大会とゼミです。
私の専門はロシア経済史・経済思想史でしたが、1980年代後半から1990年代前半にかけてのロシアの激動の時代には、学生のロシアへの関心も高く、ゼミではリアルタイムでペレストロイカの行方を追っていました。チェルノヴィリの原発事故やソ連の崩壊、ロシアの市場移行などについてゼミ生が活発に議論しながら自主的に調べ、インゼミで報告していたことを懐かしく思い出します。経済学部のインゼミは、学生の勉学への意欲を高め、プレゼン能力を磨く最適な機会であることを実感しました。
また少人数の基礎ゼミやゼミでは、私は早くからディベートを取り入れました。ディベートは自分の頭で考えながら、勝ち負けを決めるフェアで知的な競技です。一年生のクラスでは、原発や脳死などの入りやすいテーマで、また3年生のゼミでは雇用の流動化や消費税引き上げなど多くの問題を取り上げ、ディベートを何度も行いました。在職中、私が最も嬉しかったのは、回数を重ねるごとにゼミ生のプレゼンやディベートの能力が高まっていく姿を見たことです。
甲南学園の創立者が目指したのは、「人間の持つ天賦の才能を引き出し、個性を尊重する教育」でした。この理念は経済学部においても生かされています。経済学部の教育は、学生の自主性を重んじ、教員はいわばコーチとして一人一人の能力を伸ばすように考えられているからです。
建学の精神は不朽である
コロナとの戦いが続く2022年に経済学部は私に遅れること4年で70歳を迎えました。気候変動、AIの進展、既存国際秩序への挑戦、さらに人口減少という状況の中で100歳への準備をする時が来ました。学園創立者『平生釟三郎』復刻版に、明治天皇、日蓮上人、実父を尊崇し、「天運と天分こそは神の業残るは人の努力なりけり」との言葉に平生80年の生涯が表現されている。雄星と翔平を育て息子麟太郎をスタンフォード大学に進学させる佐々木監督ゆかりの地、花巻、そこを代表する文学者宮沢賢治は父の浄土真宗から法華経に改宗している。『雨ニモマケズ』は文字曼荼羅の解釈であり、眼目である、との研究がある。高校生翔平の目標達成シート(マンダラチャート)は、雄星への「憧れ」を超えるようにとの監督の教えに反応し、目標を設定してそれに向けて努力をする体系である。
学園歌のラルフ・ワルド・エマーソンの言葉「わが車星につなぐ」は、平生のアメリカ訪問時の感銘を生かすために挿入された。エマーソンは、宮沢賢治にも影響を与えたとされ、信念と努力の大事さを説き、多くの言葉を残している。
Confidence in the self what is the secret of success.
自信こそ 成功の秘訣である。
Nothing great was ever achieved without enthusiasm.
情熱なしに偉業は達成されたことはない。
To be yourself in a world that is constantly trying to make you something else is the greatest accomplishment.
絶えず人を何者かに変えようとする世にあって、自分らしくあり続けることは偉業である。
A great man is always willing to be little.
偉大な人間は常に謙虚である。
麟太郎は、授業料無償というプログラムでスポーツ推薦によりスタンフォードへの進学を決め、現在MLBドラフトリーグに参加している。法律家でハーバードに合格するも、スタンフォードの入試に敗れた人もいる。いくつかの大学評価でスタンフォードはハーバードより上位にある。
スタンフォード大学の登記名にはスタンフォード夫妻の若くして亡くなった息子名が入る。夫妻の財産をハーバード大学へ寄付する意向であったが、西部地域での建学に至る経緯がある。首席卒業のエマーソンの母校であるハーバードはリベラルアーツに、スポーツと企業家と学費援助プログラムを重要視するスタンフォードに理念の違いがあるが、いつでもどこにでも求められている人材の育成は、大学・学部の使命である。学園創立100年を経て、各人の天賦の特性を伸張させる建学の精神は「百世不磨(ひゃくせいふま)」、つまり「不朽」である。
2024年7月15日
共に学ぶ
経済学部の特徴の一つに学生と教員の距離の近さがあったと思います。それに具体的な形を与えたのが少人数教育です。少人数クラスの授業は共に学ぶ貴重な場でした。それぞれに思い出すことが多くあります。
一年次の「基礎ゼミ」では、できるだけ多くの教員と接することができるようになっています。私は甲南学園創立者の平生釟三郎のことを知ってもらうために、その生涯と教育理念のかんたんな紹介とグループワークをおこないました。創立者の名前を覚える、漢字でその名を書けるようにする。はじめにそれを言いました。
二年次での「キャリアゼミ」では学生たちの真剣な参加がありました。私のゼミの卒業生に就活・仕事の話をしてもらったり、企業訪問をしたりしました。キャリアセンターの若い職員さんとコンビを組んでの授業は新鮮で、学生たちの反応も上々でした。
そして、ゼミナール。やはり経済学部教育の中心といえます。ゼミⅠでは、その年のテーマに関してグループでの発表、ゼミⅡでは、インゼミへの参加とそのための準備、ゼミⅢは卒論の作成を内容としました。
インゼミでは参加テーマの決定に毎年時間がかかったこと、当日が迫るにつれ高まる集中力、発表の緊張感、そしてグランプリをとったときの学生たちの歓喜を思い出します。30代初めで甲南に赴任したときには、参加数は10ゼミに足りませんでした。後の隆盛ぶりには目を見張ります。
卒論の作成では、ゼミⅢの単位付与要件としました。個人研究ではありますが、毎回各自が進捗状況とアイデアや構成・内容の発表を皆の前で行い意見交換をします。努力の末に仕上がった論文は『杉村ゼミナール卒業論文集』として冊子を作り、卒業式間近に手渡しました。学生たちの達成感を目の当たりにできました。
教員生活を通して、学生たちから多くを学びました。経済学部への彼らの期待に応えられたことを願うばかりです。学生たちの希望に満ちた目を忘れることはありません。
インナーゼミナールの思い出
甲南大学在職中の楽しく有意義なイベントは、インナーゼミナールの発表会でした。私の専攻は財政学でしたが、身近な社会・生活問題をとりあげ発表テーマとしました。例えば住宅・交通・公害・就職などでゼミ生を数班に分けて、それぞれ発表し、インゼミは各班の代表者で構成し、対応しました。
年度は忘れたが住宅問題をテーマにして、将来、結婚し住宅をどうするかについて発表したとき、経済的対応と社会的対応に区別して処理したとき、同席していた教授から社会的対応は経済学部と対応してふさわしくないとの批判があり、私は反論して紛糾しました。実際、新婚夫婦は住宅ローンを組んでも戸建住宅の購入は不可能で、また賃貸住宅では家賃に追われて問題解決になるまい。むしろ両親をふくめて全体で対応するのが問題解決へのベターな対応策ではないかと反論し、論争となった。
経済学部で金融論、財政学、経済政策などを学んでも、卒業後の具体的な個人資産の管理・利殖は別問題である。せめて銀行預金は少なくし証券会社の投資信託などへの分散投資とするのがベターである。学生には実感のないテーマであるが、将来、必ず直面する課題であり、インナーゼミナールは、そのような現実の対応への門戸を開く有益な機会となるはずである。
AIとSDGsを見定めて
1990年代中頃といえば、もう30年も前のことになる。あの当時のゼミ生諸君は、皆でお金を出してパソコンを購入しゼミ室で使えるようにした。当時のパソコンやプリンターは今と違って桁違いに高価で、とても個人で簡単に買うことができなかったからである。なぜパソコン購入か、それは情報革命が始ったからである。インターネットを活用することが必ず重要となってくる、それを明敏に感じ取り、まずはパソコンに触れてみよう、という熱意からであった。当時のゼミ生諸君が集まると、必ず、ゼミ室のパソコンが話題となってくる。当初は自前購入のパソコンであったが、数年のうちに経済学部の全てのゼミ室に大学の費用でパソコンが設置された。それから間もなく、甲南大学は全学をあげて情報教育に取組み、情報革命に対応していった。確か1990年代末だったと記憶しているが、神戸三宮で情報革命のシンポジュームがあり、当時の学長の吉沢先生は情報革命と大学教育について基調講演をされている。
あれから30年後の現在、A Iを中核とする第4次産業革命が始った。情報革命は第3次産業革命と言われているが、第1次産業革命から第3次産業革命までの道のりは数百年以上の時間が必要だった。ところが第3次産業革命から第4次産業革命までは、僅か30年の超短期である。情報革命が社会の仕組みを変えて行ったように、これからはAIが必ず社会を変えていく。車は自動運転となり、介護はロボットがするようになり、外国語もたちどころに自国語と同じにようになり…。もうすでにスマホに話しかけると、どんな問題でも人工知能エモバーが答えてくれる。また、ITの将棋力は将棋の大天才の藤井 聡太と互角である。想像もできない世界が近づいてきた。
AI革命と並んで重要なもう一つの問題は、SDGsである。2015年のパリ協定で気候変動抑制に関する国際的な協定が結ばれた。人間による地球環境の破壊、この危機感が全世界で共有されるようになった。また、2015年の国連宣言ではSDGsがキーワードとなり、気候変動抑制や較差解消と多様性尊重を目指して、具体的なゴールが設定された。将来を展望すると、AI革命とSDGs、この問題が最重要な課題となる。日本ではAIとSDGsを結合して Society5.0が議論されるようになってきた。
AIとSDGs、この二つを見定めること。これが今後の甲南大学が立ち向かう課題であろう。甲南大学は情報革命をわが物にした。甲南大学には創立者平生釟三郎先生の平生理念が根底にある。この精神が新たな課題を見定める力となるに違いない。
一心不乱の教授会
固定電話が、連絡手段の主役だった頃の話である。いまから25年前1999年(平成11年)のことである。
その年の2月に、前年の「大学共通センター試験」利用の甲南大学の入試で、経済学部の指定した国語科目の扱いを、コンピューターに間違ってプログラム入力していたために、間違った資料で合否判定をしてしまっていた。一年経つまでこの間違いに気付かなかった。20数名の受験生を本来合格なのに不合格にしてしまっていた。一年前のことなので、これらの受験生に、謝罪して改めて合格のお知らせをし、これからの大学の対応をお伝えしなければならない。経済学部教授会がこの作業の任に当たることになった。
そこで教授会で謝罪の行脚をするため先方にまず電話を入れ、訪問のアポをとることになった。しかし電話の仕方についてどういうのが一番適切なのか、先方の名誉を損なってしまっているので、こういう言い方はどうか、こうした方がいいのではないか、そこは先方の気持ちを大事にしなければ、など、それはそれは真剣に話し合った。最後にまとめとして、3組ぐらいペアを作って実際どうなるか試してみよう、となり、一組目で中島将隆先生と私でやってみた。以下がその時のやり取りだった。
「もしもし ○○さんのお宅ですか?」「はいそうです。」「息子さんの△△さんいらっしゃいますか?」「いえ、いま外出しています。」「お母さまでいらっしゃいますか。」「はい、そうですが…」「私 甲南大学経済学部の教員の𠮷沢と申します。突然の電話で恐縮ですが、新聞報道にありましたように、昨年の私どもの入学試験であってはいけない合否判定ミスをしてしまい、△△さんが合格していたにもかかわらず、不合格の通知を出してしまっておりました。一年もたって大変申し訳ありません。今年になってミスをしていたことが分かり、お詫びを申しあげ、経緯をご説明させていただくために、ご迷惑と存じますが、明日以降でご都合つくお時間を拝借し、ご自宅に伺わせていただければと、失礼ですが電話で連絡させていただいています。私どもの今後の措置についても、誠意をもってお話しさせていただければありがたいのですが。突然のことですので、いますぐ日時をご指定いただかなくとも、当方の電話番号お知らせしますので、申し訳ありませんが、お電話いただけないでしょうか。」「突然のことで、なんと言ってよいのか分かりませんが、息子に相談をしてから連絡させていただきます。」「そうしていただければありがたいです。こちらの電話番号は078-431-・・・・です。お電話お待ちしています。」「では、そうさせていただきます。」
謝罪の行脚は兵庫県、大阪府はもちろん、岡山県、新潟県にもおよびましたが、私ども教授会の一心不乱の誠意をお受け戴くことができました。
私は足立泰美と申します。本学部では財政学および地方財政を専門とし、特に社会保障財政をテーマに研究を行っております。国や地方公共団体、企業の支援を受け、現場に赴き、税および社会保障の財源と給付の視点から個票データを用いて検証を行っています。例えば、地方自治体の社会保障政策の効果を分析し、政策提言を行うこともあります。
甲南大学経済学部は70年の歴史を誇り、多くの優れた人材を輩出してきました。この長い歴史の中で、学部は常に時代の変化に対応し、進化を続けてきました。今後の四半世紀を見据えた学部の将来像について、私の考えを述べたいと思います。
経済のグローバル化を踏まえ、本学部ではダブルディグリーをはじめ、国際的な視野を持つ人材の育成を目指してきました。例えば、学生が海外の大学で学びながら本学の学位も取得できるプログラムを提供しています。今後も海外留学プログラムや国際交流をさらに強化し、学生が世界で活躍できる環境を整えることが一層重要になると考えます。一方で、地域社会との連携を図り、地域経済の発展に貢献することも重要です。例えば、地域企業との共同研究やインターンシッププログラムを通じて、学生が実践的な経験を積む機会を提供しています。これにより、学生は地域の課題解決に貢献しながら、実務経験を積むことができます。さらに、デジタル技術の進化に伴い、経済の構造も大きく変わっています。データサイエンスやフィンテックなど新しい分野の教育を充実させることで、学生が現代の経済環境に適応できるようにすることが求められています。例えば、プログラミングやデータ分析のスキルを身につける機会も提供しています。研究、教育、社会貢献の相乗効果を最大限に引き出すことが、これからの大学の使命であると考えます。これらの要素が互いに補完し合うことで、学生はより深い学びと実践的な経験を得ることができ、社会に対しても大きな貢献が可能となります。
甲南大学経済学部は、これからも時代の変化に対応しながら、優れた人材を育成し続けることでしょう。私自身も学部の発展に貢献できるよう、引き続き努力してまいります。皆さんと共に明るい未来を築いていけることを楽しみにしています。
「正志く、強く、朗らか」な人材を輩出するために
2023年度、経済学部では私たちのありたき姿として「自律的に成長する個性豊かな人材の輩出により人を幸せに、社会を豊かにする」と定めました。天賦の個性を発揮し、自らの倫理や規範に則って行動できる人材を輩出するためにも、私たちは学園創設者である平生釟三郎先生の「正志く、強く、朗らかに」を体現する人物教育をさらに進めていくべきだと考えています。
人口減少・少子化・超高齢化社会が到来し、高等教育機関のあるべき姿が議論されて久しいですが、環境や情勢が激しく変化する社会において、どんな予測不能な状況に陥っても、信念を貫き常に前向きに行動するしなやかな強靱さ(レジリエンス)を備える(=正志く、強く、朗らかに活躍する)人材を育成する場を提供することが高等教育機関の役割であると認識しています。この点で、私は自身の教育・研究活動を通じて大学生が「立ち止まり、自己を知る」機会を作ることができればと考えています。
現代社会において、私たちはソーシャル・メディア等で繰り広げられる論戦に巻き込まれ、惑わされる環境に晒されています。ともすれば「思考停止」を引き起こしてしまうこの情報過多の時代において、(私自身を含め)じっくりと「自分自身」に向き合う機会を作ることが難しくなっているのではないかと感じています。「大学生活の期間はモラトリアム」であると揶揄された時代もありましたが、モラトリアムだからこそ、自分自身と向き合い、不安を感じ、もがき苦しみつつも、果敢に挑戦できた期間だったと思います。その点では、総じて今の大学生活はモラトリアムと評するには忙しく、タイパ(タイムパフォーマンス)を重視しがちな気がしています。
加速する社会の中で、改めて「一見無駄・不毛に見えること」がワクワクを生みだすことを知ってほしい。タイパ重視ではなく、結果に至るまでの曲がりくねった長い道のりが物事の本質を捉える強さにつながることを感じてほしい。こういったことを大学の授業や研究を通じて学生に伝えることができれば、大学に身を置く教員としてこれほど嬉しいことはありません。私のやるべきことはまだまだたくさんありそうです。これからも「人を幸せに、社会を豊かにする」ために、私自身「正志く、強く、朗らかに」邁進していきたいと思います。
甲南大学経済学部での30年
2022年に甲南大学経済学部は創設70周年を迎えました。1994年に経済学部に着任し、2024年現在で60歳の私にとっては、経済学部創設後の半分弱を、また、人生のちょうど半分を経済学部で過ごしてきたことになります。ここでは、私が経済学部で過ごしてきた30年を簡単に振り返りたいと思います。
講義では、助教授となった1996年度から財政学関連の講義を担当してきました。講義にあたっては、現実の財政の諸問題について、理論、制度、歴史、政策に目配りしながら解説を行うことを意識してきました。聴講した学生のみなさんが財政に少しでも興味・関心を持つことができたのであれば嬉しく思います。
学部教育の華といえばゼミでしょう。ゼミを運営できるということが、私が大学教員になりたいと思った最大の理由であると言っても過言ではありません。ゼミ生のみなさんには、ゼミでの勉強を通じて、テーマは何でもよいので、問いを立てて自分で調べて考え、論理的に整理する方法を身につけてもらえたらと思っていました。それを達成するための手段が、経済学部では3年次のインナーゼミナール大会と4年次の卒業論文・卒業研究でした。4年次の最後までゼミに参加し、卒業論文・卒業研究を完成させたゼミ生から、「成長できた」「この経験を活かし、自信に繋げたい」「達成感を感じた」などの声を聴くことができたのはとても嬉しく、教師冥利に尽きます。その一方で、4年次になるとゼミに参加しないゼミ生も少なからずいたことは、ゼミを運営する立場からはショッキングなことでした。自ら課題を見つけ、時間をかけて論理を組み立てる訓練をする大学生最後の機会が卒業論文・卒業研究であると思うので、それを自ら放棄するのは残念に思います。
経済学部の紀要である『甲南経済学論集』には、30年間で論説・研究ノートを12本投稿しました。着任した時に、先輩の先生方から1年に最低1本は投稿するようにとの助言をいただき、それを目標にしてきましたが、惨憺たる結果です。自由に投稿できるせっかくの機会を無にしてきたことは反省すべきでしょう。今更ですが、初心に帰って精進したいと思います。
これからも継続してインナーゼミナール大会が開催され、『甲南経済学論集』が刊行されることと、これからは4年次生の多くが最後までゼミに参加し、ゼミが賑やかな学問の交流の場となることが私のささやかな希望です。甲南大学経済学部がますます発展して100周年を迎えることを心より願っております。
33年余の甲南大学教員生活をへて思うこと
私は1991年4月に甲南大学へ赴任した。当時は1919年の甲南学園創立当初からの校舎で唯一残る旧1号館が聳え立っていた。この校舎は1995年の阪神淡路大震災で打撃を受け、解体された。新米の常であろうが、赴任当初の私も新環境への適用に苦慮した。授業は殊更だった。甲南に来る前の大学院時代は概ね研究に専念し、教育活動のことなどほとんど念頭になかった。また、甲南大学経済学部では今日までゼミを重視する伝統というべきものがあり、私の赴任当時にもそれがあった。私はフランス文学を専攻した学部時代に「演習」という名称の授業を受講したものの、その実態は甲南大学経済学部のゼミのそれと大きくかけ離れていたため、ゼミ授業を受け持つにあたっては暗中模索以外の何物でもなかった。爾来33年余りの甲南大学教員生活を送ってきた私である。短いとはいえない時間であるから、苦痛・悲憤・落胆の経験も少なからずあったが、研究活動においては、マルクスやケインズといった巨人に関する著書・査読論文を発表できたことなど、自身の専門分野である経済学説史の研究を現在まで持続しえたことをうれしく思う。教育活動では、闇夜の手探りからはじまったゼミにおいて、歴代のゼミ生と忘れがたい佳き思い出を築き上げてきたことが何よりの宝財である。ただ、33余年の教員生活をへた今も、「大学教育のあるべき姿」なるものをはっきりと描けない。正直、そのようなものなど存在しないのではないかとも思ってしまう。しかしおそらくそれは私の至らぬ故であろう。実際、「授業改善アンケート」での、学生による私の授業の総合的評価は、その全学平均の半分程度の低さである。したがって、Student First をモットーとし、「学修者本位の教育」なるものが声高に叫ばれる現在の甲南大学において、その将来を語る資格が私にどれほどあるだろうか。また、教員生活が残り少なくなった私には、それについての特別な思いもない。ただノルマとしてあえて述べるならば、学園校歌の4番にある「世の常に 媚ぶるなく わがくるま 星につなぐ」の詞が学生と教職員の精神に生き続ける甲南大学と経済学部であってほしいものだ。
生成系AIの普及と今立つ分岐点
私が甲南大学経済学部へ着任したのは2024年であるが、縁あってこの拙文を寄稿させていただくことになった。経済学部が70周年を迎えた2021年から私が着任する2024年までの高々3年で、我々は“生成系AI”と呼ばれる強力なツールを手に入れた。ChatGPTをはじめとした生成系AIは、あらゆる質問に対して、文章“らしきもの“を生成し、回答を与える。これは文章作成および校正、プログラム開発、アイデア起こしなど、幅広い分野において応用され、既に我々の知的活動に大きな影響を与えている。
学部教育の中で生成系AIの影響を現状最も受けているのは、レポート課題であろう。例えば、ChatGPTのプロンプト(指示文)として「25年後の日本の大学学部教育はどうなっているべきだろうか?代表的な予測を100文字程度で教えてください。」と入力すると、次のような文章が生成される。
25年後の日本の大学学部教育は、デジタル技術の進化によりオンライン学習が主流となり、AIやデータサイエンスを中心としたカリキュラムが強化されると予測されます。(筆者注:ChatGPT/GPT-3.5を利用、2024年7月生成)
仮に、課題で与えられた文をそのままプロンプトとすれば、同じように、適切と思われる文章“らしきもの”を生成してくれる。さらに、同じプロンプトを入力したとしても、得られる回答は一般に同じにならない。学生のレポートにはもってこいの機能である。学部教育がこれまで課してきた形式のレポート課題であれば、生成系AIの機能は脅威である。
我々は現在、重要な分岐点に立っている。一つの道は、生成系AIを脅威と見て、学生に対して自重した利用を求め続けることだろう。今一つの道は、新たな技術に適応して、生成系AIを使いこなすような人材を育成するように、教育方法のアップデートを行うことだろう。技術の普及に歯止めはかからない。我々は教育手法のアップデートを続けることを選択するべきだろう。より具体的には、例えば、レポート課題では生成系AIを用いた回答を前提とした問いの設定を行い、よりうまく利用するために必要な知識や技能の獲得を目的としてゆくべきだろう。
自発する甲南生
わたくしが本学に着任したのは1990年の春、「冷戦」は収束しつつもバブルの喧噪は末期、「経済学」が正念場を迎えていた季節でした。
阪急岡本駅からの通勤途上で追い越しかけた二人組(先輩と後輩/それとも同窓生か)の徒然めいた会話に耳に欹てた記憶があります。
《なんと経済学って3種類もあるんだって?》《うん、ミクロとマクロとマルクスと…》
《ミクロって?》《まあ、細かすぎるな。》《じゃマクロって?》《ちょっと大げさかな。》
《ではマルクスは?》《古くさいみたいだね。》(案外率直な感想かも知れません。)
学会や研究会の懇親会などの折に、このエピソードを披露したところ、《さすがは甲南、君に向いてますね》と先生方は微笑まれ、学友たちからは羨ましげに声援されました。
前職は一橋大学社会科学古典資料センター助手、西洋の古書とばかり馴染んでいたので、教師が務まるのか心許ないところへ「経済学A」という1回生向けの週2回の入門科目を2クラス担当する仕儀となり、佐伯啓思・間宮陽介・宮本光晴『命題コレクション 経済学』(筑摩書房、1990)に挙げられた50冊から(単独でもチームでも)任意の一篇を選び、図書館で現物を確認した上で(批判的に)紹介するという設定で進めることにしました。
その結果は嬉しい悲鳴、漸くパソコンが普及し始めた頃ですから、ほとんどが(丁寧な)手書きでしたが、みんな詳しいレジュメを作成して、自分の言葉で報告してくれました。まだ残されていた〈経済学〉の可能性に眼を開かれた一瞬でした。
受講者の一人から《「帝王学」の読書会を立ち上げたいと思います。先ずは『君主論』。先生はイタリアがご専門ですから、ぜひ御参加願いたいのですが》と誘いがありました。
《マキアヴェッリが希望を託したのは「新しい君主」―〈innovatori〉とも呼ばれています。つまり「革新者」ですね。》《では世継ぎの皇子のための指南とは言えませんね。だいぶ期待外れだな。》そんな遣り取りもありました。今なら差し詰め「事業継承」と「起業」の兼ね合いとも言えましょうか。その後は、ウェーバーやヒルファーディングやバーリ&ミーンズ等々、発題者が交代で司会する形式で、彼らが学窓を巣立ち、わたくしが在外研究に旅立つ1994年春まで続きました。もちろんゼミとは別枠で、学部や学年も様々でした。
〈STUDENT FIRST〉を自発的に実践した三半世紀前の甲南生たち。その忘れがたい姿を、先行きの知れぬ未来への〈よすが〉として書き記しておきます。
七十年目を超えて
甲南大学経済学部創設70周年お喜び申し上げます。
私は2024年度に本学経済学部に着任したばかりですので、70年という歴史の中で本学部が積み重ねてきたものをまだ十分に理解できていません。でも、伝統ある本学部のこれまでの蓄積を活かすことが100年目に向けても大切になるだろうと思っています。
グローバリゼーションが急速に進展する今世紀、経済格差、地球温暖化、国家や民族間の対立、国内の分断など、様々な問題が世界で顕在化しています。このような諸問題に気づき、向き合い、その背景を理解し、問題解決の方法を考える。そんな力が予測不可能な現代においてますます必要とされるでしょう。また、大学においては、そのようなことができる学問的な力を学生に対して育むことがさらに求められるでしょう。
幸い、経済学は、そのような力を育むことに適した学問といえます。というのも、経済学は基本的にモデル分析を用いる学問だからです。モデルというのは、現実を抽象化し、本質的な要素を用いて作った現実社会の模型のことです。現実社会の様々な出来事はそのままではあまりにも複雑すぎて理解することができない。だから、現実を大胆に単純化した模型(モデル)を使って、対象とする出来事が起こるメカニズムを理解し、その原因を特定化し、その対応方法を考えるというアプローチを経済学では一般的に用います。このモデル分析というアプローチそのものが、混迷する現代社会の諸問題を、自ら考え、理解し、問題解決へ取り組むということに適っています。したがって、時代の流れに合わせながらも、経済学の学問知を基本からしっかりと学生に身につけさせて、会得したことを使うという実践的なこともさせること、つまり、本学経済学部がこれまで追求してきたであろうことを、これからも地道に行っていくことが必要であるといえるでしょう。本学部のこれからの蓄積に、私自身も教育・研究の面で少しでも貢献したいと考えています。
「世の常に媚ぶるなく ─100周年に向けて─」
私は、甲南大学経済学部が創設50周年を迎えた2002年に着任しました。
十二支がもう一巡すると、私も定年を迎えることになります。
私の場合には、公募ではなく、縁あってお誘いをいただいたことをきっかけとして、
甲南大学経済学部に着任しました。
お誘いをいただいた方からは、
「甲南はアカデミックだから、寺尾君にとても向いているよ」
というお声掛けがあり、その一言で私はお誘いを受けることにしました。
私の考えでは、「アカデミック」であるための要件のひとつは、
甲南学園歌[https://www.konan-u.ac.jp/gakuen/gakuenka/]の第四番第一節にあるように、
「世の常に媚ぶるなく」という姿勢を貫くことです。
「世の常に媚ぶるなく」という姿勢は、端的には、
現在でもかたちとしては維持されている「学年暦(academic calendar)」に示されています。
「学年暦」では、「世の常」における平日が休日とされ、
「世の常」における休日が平日とされます。
「アカデミック」とは「世の常」と異なるということであり、
ときとして「世の常」に反することも厭わないということです。
しかし、いつの頃からでしょうか。
「社会のニーズ」「社会課題」といった言葉が学内で飛び交うようになり、
最近では「社会実装」という言葉もよく目にするようになりました。
「社会のニーズ」「社会課題」「社会実装」というとき、
その「社会」が指し示すものは、はたしてほんとうに社会なのだろうか
──そうした疑問を抱かざるを得ないことが、私自身は少なくありません。
経済学は社会科学であり、それゆえ、経済学徒が最も避けるべきは、
社会を自明視することであるはずです。
100周年に向かっていくなかで、次代を担う先生方が、
世の常に媚ぶるなく、「アカデミックな甲南」を堅持されますことを切に願っています。
甲南大学経済学部70年の回顧と展望—100周年に向けて—
経済学部の中川真太郎です。授業は、公共経済、公共政策、震災と地域経済Ⅰ・Ⅱ、および、ゼミ科目を担当しています。専門は公共経済学で、リスクに対応するための公共財を集合的に供給する状況を理論的に研究しています。たとえば、新型コロナウイルス感染症のような感染症の世界的流行リスクに対して各国がワクチン開発や検疫などを通じて対応する状況、あるいは、同盟が外部からの侵略のリスクに共同で対応する状況などを、経済学の視点から研究しています。
私が本学に着任したのは2017年4月ですが、現在までを振り返りますと、経済学部として大きな出来事の1つに、ダブルディグリー・プログラムの導入があげられると思います。このプログラムは、米国ユタ州の州立大学であるウイーバー州立大学との協定に基づくプログラムで、入学から3年次前期までは本学で学修し、3年次後期から同大学に留学し、2年間学んで同大学を卒業した後、修得した単位を本学の単位に読み替えて本学も卒業して、両大学の学位を取得することを目指すというプログラムです。ただし、これは全てが想定通り進んだ最速のケースであって、両大学での学位の取得が予め保証されているわけではありません。このプログラムは留学期間も長く、求められる学力・語学力の水準も高いため、誰もが利用できるものではありませんが、高校生の関心も高く、経済学部の魅力を高める上で幾らかの貢献をしているのではないかと思います。
経済学部100周年を展望しますと、「世界に通用する紳士・淑女」を育てていくために、学生にいかにして海外を経験させるか、ということが今後も課題となるのではないかと考えています。インターネットを通じて海外と容易に交流できる時代になってはいますが、それでも、現地に行って、その空気を吸って、その場で人と接することは、学生の識見を広げ人間的成長に大きく寄与すると考えています。経済学部として、今後も学生の留学機会を広げる取り組みを強化していく必要があると考えています。
経済学部の林健太です。
私が甲南大学経済学部に赴任して、20年が過ぎました。
この間、毎年20名ほどのゼミ生の卒業に立ち会ってきたため、気づけば400名近いゼミOB・OGがいることになります。
彼らの内の何割かとは今でも交流があり、関東にいる人たちは、私が上京する際に声をかければ集まってくれますし、新卒で関東勤務になった後輩ゼミ生の面倒をよくみてくれます。また、地元に残っている人たちは度々ゼミの食事会に参加し、現役学生に対して就職活動等に関するアドバイスを送ってくれます。
このように、教員生活の20年間で私が接してきた甲南大学生は、人懐っこくて気持ち良く付き合える人が多い印象を抱いています。
翻って、私の専門である情報通信分野に目を向けると、20年前は、ようやく一般の人々にインターネットが認知され始めた頃であり、SNS(ソーシャルネットワーキングサービス)の黎明期でした。当時の日本の携帯電話サービスは世界一のクオリティで提供されており、学生にとって、PHSから携帯電話に乗り換えることが誇らしく感じられる、そんな世の中でした。
時は経ち、今や学内でスマートフォン未所持の学生を見つける方が難しく、2023年にはChatGPTに代表される生成AIブームが世界中で巻き起こり、また一つ大きく時代が変わろうとしています。
かつての産業革命やインターネットの登場時にも言われたことですが、生成AIの普及は、私たちの働き方や教育のあり方を大きく変える可能性が高く、大学においては、単に知識を教授するだけの教員は時代遅れの存在となり、学生にしても、物理的に大学に通うことの意味を自問するようになるでしょう。
四半世紀後に、甲南大学経済学部がどのような状況にあるのか私には想像もつきませんが、少なくとも私は退職するまでの間、”student first”を意識して学生との交流を図り、現役学生とOB・OGの間を取り持つ、ゼミの人的ネットワークのハブ役として尽力したいと考えています。
四半世紀後の経済学部-変化するべきものと変化するべきでないもの-
甲南大学経済学部に所属しております林亮輔と申します。経済学部では公共経済、公共政策、地域政策などの授業を担当しており、持続可能な地域経済システムの構築という目的のもと、「地域経済力の強化」や、地域政策の担い手である地方自治体の「行政運営の効率化」を柱として研究を進めています。
甲南大学には2018年度から在籍しており、今年度で在籍7年度目になります。他の先生に比べてまだまだ短い在籍期間ですので、四半世紀後を見据えた経済学部の将来像を思い描くには経験も実力も不足していますが、甲南大学経済学部に在籍した6年半の経験を踏まえ「四半世紀後を見据えた経済学部の将来像」について思いを巡らせたいと思います。
この6年半という在籍期間中、大学を取り巻く環境は大きく変化してきました。2020年から世界中で大流行した新型コロナウイルス感染症(COVID-19)や、2022年に公開されたChatGPTを始めとする生成AIの登場などは代表的な例ですが、これらの環境変化に応じて大学の教育も変化を遂げていきました。コロナ禍で普及したZOOMなどのツールは、キャンパスでの授業が再開した今もなお活用されていますし、生成AIを用いた授業があるという話も伺っています。四半世紀後の環境を予測することは不可能ですが、環境変化に常に敏感であり、環境変化に即時的に対応する「日々進化を続ける経済学部」でなければならないと考えています。
しかしその一方で、「甲南大学経済学部」として変えてはならない普遍的な役割もあると考えています。甲南学園の創立者である平生釟三郎が述べた「天賦の才は凡ての人にあり」という言葉の通り、一人ひとりは異なった存在であり、一人ひとりに備わった才能は異なるということを、私自身この6年半で学びました。「学生・生徒を正しく導いて行くには、何よりも先ず先生の質をよくすること」という創立者の言葉を胸に、「学生一人ひとりに備わった才能を見出し、その才能を引き出すことができる教員が集う経済学部」が、現在と同様、四半世紀後も続いていれば良いと考えています。
自己紹介を兼ねながら、長期的視点に立って四半世紀後を見据えた学部の将来像を思い描く。
宮川敏治と申します。甲南大学に赴任して、5年目です。ゲーム理論、特に、交渉ゲーム理論、を研究しています。ゲーム理論は、世間的には数学者と認知されているジョン・フォンノイマンやジョン・ナッシュが創始者とされ、応用数学の一分野とみなされています。そして、その理論は、経済学はもちろん、経営学、政治学、社会学、生物学、工学など様々な分野で応用されており、学際的な側面も併せ持っています。そのような学問の特性も影響しているのかもしれませんが、「ホワイト・ボードや黒板を囲んで、学生、教員、研究者分け隔てなく、また、国籍を越えた様々な人たちが、ゲーム理論にまつわる様々な問題ついて議論し、意見を出し合い、数学的な証明の方法や問題の解決策を考える」という場面に数多く遭遇してきました。私が1年間滞在したペンシルバニア州立大学では、ほとんどの研究室のドアが開いていて、大学院生、研究者、学部の教員が入り乱れて、様々な研究テーマにういて議論が行われていました。毎年行われるストーニーブルックでのゲーム理論の国際ワークショップでは、ノーベル経済学賞の受賞者も加わって、朝食の場から夕食の時間まで、世界中から集まった研究者がお互いの研究について話し合うということが1週間にわたって行われています。私がお世話になった岡田章先生や入谷純先生の研究室では、ゲーム理論だけでなく経済学、数学の様々な問題について、毎週のように、大学の垣根を越えて、学部生、大学院生、研究者が議論をする風土がありました。私はこれまで、それらの議論の中から、トップジャーナルに掲載される研究や何十、もしかしたら、何百の研究論文が生まれてきたのを見てきました。甲南大学経済学部でも、同じような状況ができたら良いなと思っています。まだ、経済学部のフロアで研究室のドアが開いているのは数人です。私の研究室には、学生や学外の研究者は来ますが、経済学部の同僚はまだあまりいらっしゃらないのが現状です。少しでも議論の風を吹かせたいと思って今日も研究室のドアを開けています。
私は甲南大学経済学部を2012年に卒業し、神戸大学経済学研究科博士課程前期課程・後期課程を修了後、他大学での勤務を経て、2022年に甲南大学経済学部に講師として赴任しました。甲南大学との出会いは20年弱前、環境問題解決に関する勉強がしたいと思い、環境経済学の専任講師がいる本学へ入学しました。環境経済学が学べると本学に入った割には、経済学と経営学の違いもよくわからず入学した私に、経済学の面白さや有能さを教えてくれたのは甲南大学経済学部の先生方でした。さらに、学問的な教えだけでなく、ゼミでのグループ研究を通して、協働することの難しさや大切さを教えてくれたのも本学の先生方や共に学んだ仲間です。甲南大学経済学部での学びがあったからこそ、さらに経済学を学びたいと院へ進学しましたし、研究機関ではなく大学への就職を選んだのも本学で過ごした4年間が楽しかったことが何よりの理由です。甲南大学経済学部に入学していなかったならば、大学教員として働く今はなかったと思います。
その反面、甲南大学の学びを支える一員となった今、自分が与えてもらったものを振り返ると、学生たちに同じかそれ以上のものが与えられるのか不安になります。私が学生だった時より、学生たちが卒業後に思いを馳せた時に想像する社会は重苦しい空気が立ち込めており、より多くの知識や力を身につけて社会に出る必要があると感じます。そのために、私ができることは惜しみなく協力するからとゼミ生などには伝えています。もちろん、私のできることには限りがありますが、誰かに助けてもらったら次は誰かを助けようとする優しく、倫理的な学生が本学には多くいることには希望を感じています。私も自身の恩師達にお礼を伝えると「自分たちには返さなくていいから次の世代に返してあげなさい」とよく言われていたことを思い出します。まだまだ教員として未熟である私には甲南大学経済学部の将来像まで思い描くことはできませんが、これまでの甲南大学への感謝を恩返しすべく、これからの学生の学びを微力ながら支え、将来の甲南大学を支える人材を育成できればと思います。
30年前/30年後
甲南大学経済学部が1952年の創設から70周年を迎えたことをお慶び申し上げます。私の甲南経済での教員歴は,2015年4月の着任以来,2024年度で10年目となります。2023年度までは主に研究・教育に専念しておりましたが,2024年度より国際交流・広報担当の学長補佐を拝命し,微力ながら大学全体の運営にも携わっております。
映画「バック・トゥ・ザ・フューチャー」が印象的に描写するように,30年で世の中は大きく変わります。40周年の1992年,まだ世の中にスマホは存在せず,パソコンのOSはMS-DOSで,教室にエアコンはなく,黒板に板書の授業でした。100周年の2052年を想像するのも楽しいですが,映画「バック・トゥ・ザ・フューチャーPART2」より当たらないでしょう。そこでまずデータを確認してみます。
総務省「人口推計」によると,2023年10月1日現在の18歳人口は108万9千人,0歳人口は75万7千人です。したがって移民の流入がない限り,2041年10月1日時点の18歳人口は75万7千人以下となります。今後10年間で出生数が下げ止まり,増加に転じなければ,2052年の18歳人口は70万人を割るかもしれません。文部科学省「令和5年度学校基本調査」によれば,2023年度の大学入学者数は63万2902人と前年度より僅かに減少しており,今後は大学・学部の再編・淘汰が加速しそうです。2052年の甲南経済は果たしてどうなっているでしょうか?
教育の効果は「伸びしろ」で測るべきものです。「人物教育」で勉強する習慣を身につけさせ,「彩り教育」で個性を伸ばし,入学者を1人も脱落させずに卒業させる「面倒見の良い大学」であることが,受験生と保護者にとって最大の魅力になるはずです。そのような教育を経済学部が率先し,2052年も甲南大学が「選ばれる大学」であるように,尽力して参りたいと存じます。
経済学部の復活を!
春は花咲き、夏茂り、秋は紅葉の錦いろどる甲南大学に赴任して、およそ20年の歳月を過ごしてきた。初めて甲南大学を訪問した時のことが昨日のように思い出される。摂津本山駅を降りると、そこは石畳の広場と色とりどりの花々を店頭に並べた花屋が、異邦人を出迎えてくれるような光景であった。
大学に勤めてから先輩の先生方からは大変よくしていただいた。特に、歴代の学部長の親切な心遣いは。赴任したての頃、大学近くの中華料理店で食事をしながら、利用できる研究・教育費について教えていただいたこと。兵庫県の近隣高校への出張講義の際には自家用車に乗せてもらい訪問したことは今でも脳裏にある。出張講義は格も楽しいものかと思った。研究の上でもいくつもの大学のファンドを利用させていただく機会にも恵まれたことや、いち早く海外研修の機会も与えてもらったことは、歴代の学部長の情報提供による。こうした華々しい機会を提供できる学部が経済学部であった。
しかし、時代は移り変わっていった。大学は緊縮財政政策をとった。経済学部独自の事務室は、知らぬ間になくなり、法学・経済・経営3学部の合同事務室となり、専任職員の数は減らされ、学部の経費は削られた。
一方、大学は新たな学部や専門職大学院を創設していった。2004に法科大学院(2023年廃止)を、2006年に会計大学院(2016年廃止)を開設、2009年にはマネジメント創造学部(CUBE)とフロンティアサイエンス学部・研究科(FIRST)を創設した。当初は、設立に際して「既存学部の予算は削減しない」という約束であった。しかし、現実にはそうならなかった。時代は小泉改革の新自由主義的な「改革路線」がまともな政策であると考えられていくような時代であった。甲南大学においては、既存学部の文学・経済・法学・経営など文系大学部は経費削減の対象となった。
緊縮財政をとり続けると、組織全体がどのようになるかは明らかであろう。主要先進諸国の自国通貨建てGDPがこの25年間(1995年~2020年)成長していないのは日本だけである。伊・独・仏国の欧州諸国は約2倍に、英国・加国・米国は2.5~2.7倍と約3倍になっているのに、緊縮財政をとり続けた日本だけはこの25年間成長していないのである。 今こそ、既存学部、とりわけ大勢の学生を毎年輩出している既存の文系学部を大切にすべき時ではないだろうか。
